易経一日一言をBlogで読めるようにして欲しい、
FBをやっていない人は見られないと連絡がありました。
Blogにも書いています。
~~~~~~~~~~~~~~
易経一日一言は10月3~9日の7日分です。
※易経一日一言を一年間通して読まれれば、
易経に書かれているおおよその内容を把握出来ます。
☆本当は一日一言は毎日投稿した方が良いのですが、
出張や資料作りに追われていて、数日分を纏めてUPします。
~帝王学の書~10月3日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆幾(き)を知る☆
幾を知るはそれ神(しん)か。
(繋辞下伝)
「幾」とはわずか、微妙な、機微を意味する。
物事が大きく動く微細なきっかけであり、別の言い方をすると兆しである。
「幾を知る」とは、萌芽を見て春を知ることではない。
まだ現象面に現れない、眼に見えないものを察することをいう。
たとえば、「桐一葉落ちて天下の秋を知る」
(桐の一葉が落ちるのを見て、天下衰亡の時と腑に落ちる)という句のように、
一瞬にして結果を知る。
これは常人には及ばない直観力であると易経はいう。
~帝王学の書~10月4日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆通塞(つうそく)を知る☆
戸庭(こてい)を出でずとは、通塞を知ればなり。
(水沢節)
水沢節(すいたくせつ)の卦名(かめい)「節(せつ)」は竹の節(ふし)。
竹は「通塞」を重ねて伸びていく。
節(ふし)が伸びている時は通じ、節目(ふしめ)では塞(ふさ)がる。
通じているのは進むべき時であり、
塞(ふさ)がっているのは退き、止まるべき時である。
「節(せつ)」を知る者は家から一歩も出なくても
通塞(つうそく)を知り、進退の時を知る。
それを悠然と楽しむのである。
『老子』にも「戸(こ)を出でずして天下を知る」
という言葉がある。
~帝王学の書~10月5日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆感性の源☆
君子もって虚(きょ)にして人に受く。
(沢山咸)
この「虚」は心にある空虚な隙間をいう。
これは心が動く空間であり、感じる能力、感性の源である。
人の言葉や心を受け容れるには、いくら知識や経験を積み重ねても、
「まだ知らないことがある」と、虚心坦懐な姿勢で向かうことが大切である。
思い込みで一杯になっていたり、知識だけにとらわれていたら、
どんなに素晴らしい出来事や人物に出会っても、
受け容れられず、何も感じられない。
~帝王学の書~10月6日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆類は友を呼ぶ☆
聖人作(おこ)りて万物観る。
天に本づく者は上に親しみ、地に本づく者は下に親しむ。
すなわち各各その類に従うなり。
(文言伝)
聖人を皆が仰ぎ見るように、人も物も同じ類に感応する。
生命を天から受ける動物は頭を上にして、
地から受ける植物は、その根を下に張る。
人に長たる者が現れたとき、同じ志を持つ類同士が求め合い、感応し合う。
国家や会社組織も、そのようにして成り立っていくものである。
~帝王学の書~10月7日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆三駆(さんく)して前禽(ぜんきん)を失う☆
王もって三駆して前禽を失う。(水地比)
殷(いん)王朝の初代の王である湯王(とうおう)が
狩りの獲物を追い込んだ時、
「残りの三方は囲んでおいて、
一か所だけ自由に逃げることができるようにしなさい。
それでもかかる獲物はいただきましょう」
といったことに由来する言葉。
どんなに実力があっても、弱い者に対して
肩を怒らせて力をふるってはならないという教えである。
逃げ道がなくなるまで追い詰めず、
相手の自由意志を尊重することを説いている。
~帝王学の書~10月8日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆時を待つ☆
天地閉じて、賢人隠る。
(文言伝)
たとえば、天を政府、地を国民とする。
政府が国民の気持ちを考えず、国民が政府の方針に従わなければ、
どちらも意思の疎通を図れず、国は乱れる。
これが「天地閉じて」という状態である。
賢い人は、そういう時代には自分の能力を活かせないと知り、
口を閉じ、財布の紐を堅く結んで、遠く隠遁するようになる。
一見卑怯に見えても、時を待つしか術がない時もある。
そういう時は、じっと堪えて、来るべき時代に備えるしかない。
~帝王学の書~10月9日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆明(めい)夷(やぶ)る☆
箕子(きし)の明夷る。
貞(ただ)しきに利(よ)ろし。(地火明夷)
箕子は殷王朝の将来を憂い、甥である殷の紂王を諫め続けたが、
聞き入れられず、紂王は暴君と化した。
箕子は暴虐無尽の時代を察し、狂人を装って難を逃れた。
自らの明徳を破り、自分の聡明さを見せなかった。
艱難の時にあって、「明、夷(やぶ)る」という手段で心の明かり、
希望を失うことなく、自分の道を守ったのである。
『易経一日一言』(致知出版社)
ジャコメッティ 歩く男

☆ ★ ☆
~~~~~~~~~~~~~~
【大人に学び、基本の型を身に付ける】
陰陽の話を思い出してください。
「見る」には聞く、従うという意味もあると話しました。
聞く、従う、真似る、学ぶ、受け容れることは、すべて陰の力です。
見龍が「大人を見るに利ろし」を実践するうえで重要な点は、
こうした陰の力を強めていくことです。
そうすることで、逆に陽の力が育っていきます。
それには、「このやり方は真似るけれど、
これに関しては自分のやり方、考え方のほうがいいのではないか」
という疑問を差しはさんで、自分の利口を出さないことです。
とにかく受け容れて、従うことが結果的に近道になります。
『超訳 易経 陽』赤本より
☆ ★ ☆
【じたばたしないこと】
たとえいまが何をやってもうまくいかない、
また身動きの取れない「人生の冬」のような「時」であっても、
必ず問題は解決し、春を迎えることができます。
ところが季節は、自然にめぐっていきますが
人間は「苦しい時」をなんとか好転したいと、懸命に努力し、じたばたします。
にもかかわらず一向に状況が良くならない。これはなぜなのでしょうか?
生きていくうえでは、思いだけではどうにもならないことがたくさんあります。
思いを実らせるためには、その「時」、その「時」にあった解決方法、
アプローチ方法を取らなければうまくいきません。
易経は自然の法則に学び、それに順(したが)えば
問題は解決し願いはかなうと教えているのです。
たとえ話をします。
実りを得たいという思いがいくら強くても
凍った冬の大地に種をまいたら秋の実りはありません。
でも、春に種をまけば、実りの秋を迎えることができます。
人間の思いが自然の法則にぴったりと合致した時にはじめて実るのです。
早く苦境を脱したいと焦って、冬に種をまいても何にも実りません。
天の気候と、大地の栄養の準備が整った、春に種をまくことが
一番の近道、最善の道なのだよ、と易経は教えています。
『超訳 易経 陰』青本より
~~~~~~~~~~~~~~
ニコラ・ド・スタール「灯台(アンティーブ)」

~~~~~~~~~~~~~~
☆2023年度 各地の
一般の方が参加可能な易経講座やセミナーのお知らせです。
※全国各地、どなたでもご参加いただけます
☆講演やセミナーで私が主催するものは一つもありません。
それぞれ主催者がいらっしゃいます。
予約が不要のものもあります。
※ほとんどの私の講演は、企業や官庁関係の主催のため
一般の方はお聴きいただけません。
こちらに紹介する講演やセミナーは、一般の方もご参加いただけます。
「NHK文化センターでキャンセル待ちNo.1の帝王学講座」と紹介されました。
↓
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000071793.html
27年目に突入(月2回)夜の名古屋NHK文化センター易経講座。
NHKビルの大会議室が教室(100人までOK。残席が若干あります)
キャンセル待ちが解消‼
☆NHK文化センター名古屋教室「易経」講座募集中。
●2023年10月期の募集が始まりました。
☆NHK文化センター名古屋教室「易経」講座募集中。
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_440408.html
2023年10月に27年目に突入します。 四半世紀継続の長寿講座 感謝❣
※現在、易経全文を読む2周目。十翼の繋辞伝を(64卦を復習しながら)
19年ぶりに3年前から読んでいます。


☆中国古典「易経」を占いでなく、古代の叡智を学ぶ目的でスタートした講座です。
※易経全文を15年かけて読み込んでいます(1997年10月より)
※占いの講座ではありません。
※帝王学のTOPとされた中国古典『易経』を読み、古代の叡智を学びます。
※途中受講できます。
※NHK文化センターは他に新規の超入門 易経講座を名古屋で開催しています。
その講座も募集中です。
☆
★
☆
午後の名古屋NHK文化センター超入門「易経」講座。
●2023年10月期の募集が始まりました。
乾と坤の理解が深まれば、残りの62卦は楽に読めます![]() ※今回のテーマでは、時間の縛りを気にせずに、 青本の卦をかなり詳しく深読みしていくことにしま なので1~2年間の予定を、〇?年間に変更しました。☆易経超入門講座 10/18、11/15、12/20・・・ ☆途中受講OKです。
※今回のテーマでは、時間の縛りを気にせずに、 青本の卦をかなり詳しく深読みしていくことにしま なので1~2年間の予定を、〇?年間に変更しました。☆易経超入門講座 10/18、11/15、12/20・・・ ☆途中受講OKです。
【陰の時代を生きる~泰と否_対称的な二つの卦】
9月は天地否を読了。
☆10月18日から「天火同人」を読み始めます。読む予定の卦は、天火同人・習坎・火沢睽・水沢節ほか 

☆ご注意! 占いではありません。
乾と坤の理解が深まれば、残りの62卦は楽に読めます✌
NHK文化センター名古屋教室
<易経超入門 時の変化の法則を読む>
【教室】毎月1回 第3水曜 15:30~17:00(全6回)
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1224661.html
『超訳易経 陰 坤為地ほか』~陰の時代を生きる〜
【オンデマンド】(2週間の配信)募集中❣申込先
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1226306.html
易経は最古の帝王学でその時の解決策を教えてくれます。
「坤為地―大地と牝馬の物語」をメインに「天雷无妄」「山天大畜」「火天大有」「水風井」「艮為山」など十数卦を〇?年間かけて読み、「時中」(物事の解決策)を学びます。
※この講座は、分からないことを気にせず読み続けていけば、難解な易経と思われがちな多くの約束事や基礎知識が、知らず知らずのうちに身に付くように工夫しています。
※また途中受講もOKで、半年受講後、多忙になり3ヶ月休んだ後に受講を再開されても大丈夫です。
サボりながらでも継続されていけば、必ず理解出来るようになります。
#易経
#竹村亞希子の易経講座
#時の変化の法則の書
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆
★
☆
第1回博多易経リアル会場は満席ですが、オンラインは余裕があります。
どなたでも参加可能なハイブリッド易経講座❤
博多易経セミナー第1回「龍の物語」(乾為天)
令和5年10月6日(金)14時~17時
会場:ホテルクリオコート博多
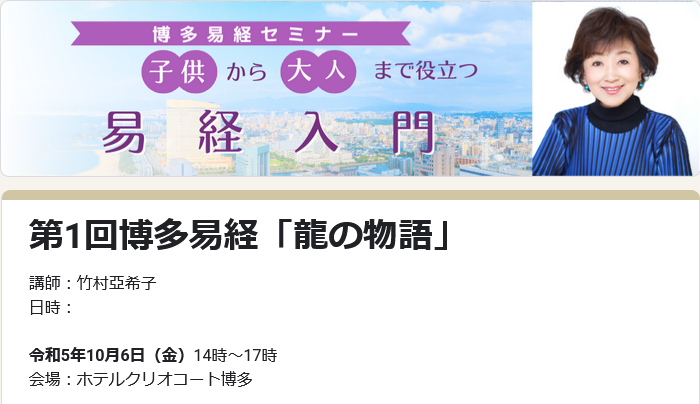
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Cq9qPGFuU-GGtrwhP6GnLkX1f_ZFFCEb8tKPR_H-3Rpd6g/viewform
箕浦 雅子(主催者):
竹村亞希子先生(易経研究家)の講座が博多で始まります(⋈◍>◡<◍)。✧♡
リアル講座は何年もキャンセル待ちが続いているほどの大人気講師!!
先生は古代の叡智を現代に分かりやすく伝えてくださる方です。
今回は易経を初めて聞かれる方のために、一番わかりやすい「龍の物語」をテーマにお話しくださいます。
先生のお話は何といってもリアルで聞くのが一番!!。
ここ3年は泣く泣くオンラインで我慢していましたが、やっぱりリアルがいい~!!
ぜひ博多に来てほしいと先生に懇願。やっと念願が叶いました!
易経って難しい・・・とお思いの方は目から鱗( ゚Д゚)!間違いなし!
先生曰く、易しくて簡単♡っと。
易経を学べば怖いものが無くなったと多くの経営者から厚い信頼を寄せられる亞希子先生。
「君子占わず」占わなくても出処進退がわかるという易経は人生に必須と思っている学びです(^^♪
皆様ぜひ会場に足をお運びください💛
※ちなみに易経は占いの講座ではありません。
リアル会場は先着50名限定です。お早めにお申し込みください。
・会場で参加(1人)10,000円
・会場参加(2名ペアチケット)18,000円
・webで参加(1人)8,000円
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Cq9qPGFuU-GGtrwhP6GnLkX1f_ZFFCEb8tKPR_H-3Rpd6g/viewform
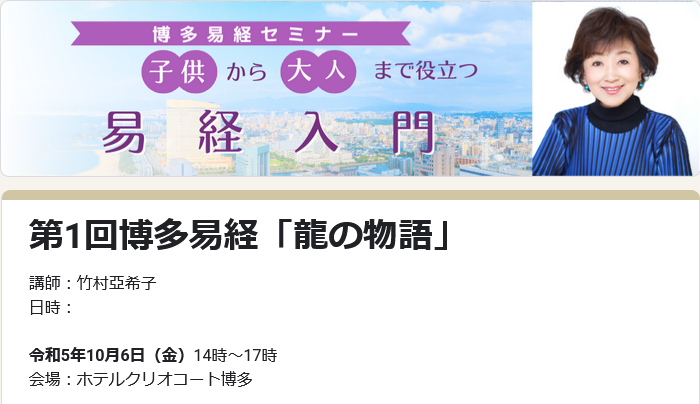
☆ ★ ☆
☆ ★ ☆
☆ ★ ☆
★一般の方がご参加いただける易経講座
【東洋文化振興会】易経は年1回のみ。予約不要。
人生に生かす易経 ※ご注意‼ 占いではありません。
2023年10月14日(土)14~16時
演題:【天沢履~虎の尾を踏む】
※儒家の基本書「五経」の一つ「易経」
会 場 : 新日本法規出版本社別館・名古屋支社4F「大会議室」
名古屋市中区栄1-26-11
(地下鉄伏見駅6番出口徒歩10分)
会 費 : 1,000円(予約不要)
主催・事務局 : 東洋文化振興会

