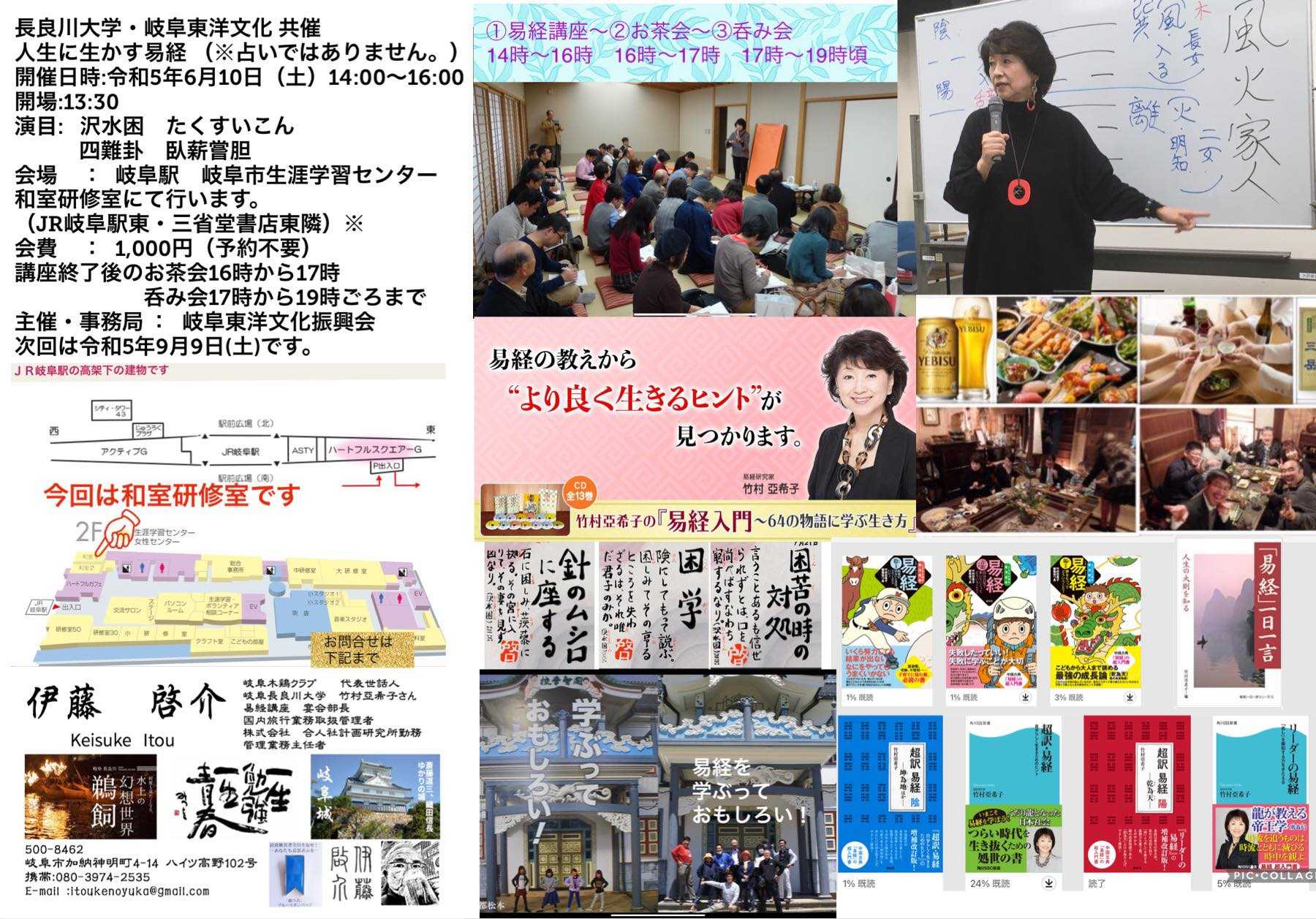☆時の流れに従って生きる/わからないままに受け止める
☆リーダーの役割~帝王学の書~6月1~6日の6日分の『易経一日一言』(致知出版社)
☆6/10 岐阜駅構内で一般参加OKの易経講座❣(予約不要)
~~~ ☆☆☆ ~~~
【時の流れに従って生きる】
エネルギー切れでものごとが停滞する時に
必要なことは、まず充電です。
無理せず、焦らず、頑張りすぎず、ゆったり過ごすこと。
健康と体力を維持しながら、時の流れに従って生きることが大切です。
一見、消極的なようですが、
そういう陰の力を積極的に使いなさいと易経は教えています。
なぜなら、むやみに焦ってさらに消耗してしまうと、
長い陰の時代に新たな希望を貫いていけないからです。
次の陽の時代への遠い光をたよりに、歩んでいくのが陰の時代です。
真っ直ぐに進んでいくためにも、力を温存していくことが必要なのです。
『超訳 易経 陰』青本より
~~~ ☆☆☆ ~~~
【わからないままに受け止める】
易経は古典の中でもとくに難解といわれますが、
学ぶ時のコツは、わからないことはわからなくてもいい、
わからないままに受け止める、これが大切です。
考えても混乱するだけですから無理に考えず、
自分の考えで決めつけず、繰り返し読んでいくことです。
そして、わかることから学んでいくと、そこから、
わからないと思っていたことにつながって、
あとから理解がついてきます。
見龍の学びもこれと同じで、
大人から教わることを自分の物差しに当てず、
まるごと素直に受け容れなければ型が身につきません。
大地が天の働きをすべて受け容れて、万物を化成するように、
まず受け容れることが自分を育てるのです。
これはわかるけれど、これはいくら考えてもわからない、
できないから違う、などと選り好みしていたら、
歯車の歯がところどころ抜けたような学び方になり、
型が形成されないのです。
「学ぶ」は、もともと「まねぶ」といって、
「真似る」と語源が同じです。
まずは教えられたことを素直に受け容れて真似てみる、
そして自分に問いかけていく。
これが学びの原点であると易経は教えています。
『超訳 易経 陽』赤本より
~~~ ☆☆☆ ~~~
易経一日一言は 6月1~6日の6日分です。
※易経一日一言を一年間通して読まれれば、
易経に書かれているおおよその内容を把握出来ます。
☆本当は一日一言は毎日投稿した方が良いのですが、
出張や資料作りに追われていて、数日分を纏めてUPします。
~帝王学の書~6月1日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆楽天知命☆
天を楽しみて命を知る。故に憂えず。 (繋辞上伝)
天の理法を楽しみ、自分の運命を生きる喜びを知るならば、人に憂いはない。
「楽天」と「知命」は同じ精神である。
いかなる運命でも受け容れ、喜び感謝して生きていく。
これは、天の働き・情理を楽しむ精神である。
この言葉は、楽天家、楽天主義の出典である。
易経は天の理法を学ぶ書。
よく学んだなら、真の楽天家となりうるだろう。
~帝王学の書~6月2日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆無作為☆
耕(たがや)さずして獲(え)る。
しせずしてよする時は、往くところあるに利あり。
(天雷无妄)
田畑を耕さなくとも収穫がある。
また、「しせずしてよする」開墾せずとも田畑がこなれる。
思い込みを捨て、洞察力を持ち、自然に則して生きるならば、
本来、耕作や開墾すら必要ないという意味である。
天雷无妄(てんらいむぼう)の卦(か)は、
作為せず自然の法則のままにまかせたなら、天は万物を養うと説いている。
我々は時として「何もしない行為」を知らなくてはならない。
~帝王学の書~6月3日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆品物形を流(し)く☆
雲行き雨施し、品物形を流く。 (乾為天)
「品物」とは「万物」と同じであるが、
生きとし生けるもの、その一つひとつのものをいう。
人間ならば個々人を指す。
天に雲が巡り、恵みの雨を降らし、地上を潤し、あらゆるものを育てる。
その天の働きによって、品物が「形を流(し)く」、
すなわち個々のものがそれらしく形成される。
これは個々の性質、持ち味、特性を生かし、力を発揮させるということ。
この天の働きは遍く流布するものである。
~帝王学の書~6月4日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆万物資(と)りて生ず☆
至れるかな坤元(こんげん)、万物資(と)りて生ず。(坤為地)
「坤」は天地の「地」、陰陽では「陰」を表す。
「天の気」である太陽の光、雨が地上の至るところに降り注ぎ、
大地はそれを受け取って形あるありとあらゆるもの、万物を育成する。
陰の徳は限りない受容と包容力である。
順(したが)い、受容して育成する、
女性、母、妻、臣下の徳は陰徳である。
ちなみに化粧品メーカーの資生堂は、
この「資りて生ず」から社名をとっている。
~帝王学の書~6月5日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆心の鏡を磨く☆
みずから明徳を昭(あき)らかにす。
(火地晋)
太陽が自ら地の上に昇っていくように、自ら、明徳を明らかにする。
「みずから」とあるのは、自分の心を明るく保つのは自分自身であって、
人に頼ることではないという意味。
明徳は私欲に囚われていると曇ってしまう。
だから、自分の心の鏡が曇らないように、
日々、自分で意識して磨かなければならないのである。
火地晋(かちしん)の卦(か)は、太陽が昇るように前進して、
明徳が明らかになっていく時を説く。
~帝王学の書~6月6日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆幽明の故(こと)を知る☆
仰いでもって天文を観(み)、俯(ふ)してもって地理を察す。
この故(ゆえ)に幽明の故(こと)を知る。
(繋辞上伝)
「幽明」の「幽」は形なく眼に見えないもの。
「明」は形あって眼に見えるもの。
たとえば、身体は明、精神は幽であり、
現在は明、過去と未来は幽である。
天の巡りを仰ぎ観て、伏して地上の理(ことわり)を観察するとは、
物事の情態を真っ直ぐに観て、その真相を知るならば、
必ず裏の眼に見えない情態も見えてくるということである。
『易経一日一言』(致知出版社)
#易経
#易経一日一言
#致知出版社
#帝王学
#竹村亞希子の易経
~~~ ☆☆☆ ~~~
岐阜駅で一般参加OKの易経講座(予約不要)
6/10(土)午後、岐阜駅構内の易経講座❣
一般参加可能です❤(予約不要)
【長良川大学・岐阜東洋文化 共催】
人生に生かす易経 ※ご注意‼ 占いではありません。
2023年6月10日(土) 14~16時
演題:【沢水困~四難卦~臥薪嘗胆】
目的を遂げるために苦心し、努力を重ねる。
※サンプルモデルは春秋時代の呉越の戦い。
会 場 : 岐阜駅 岐阜市生涯学習センター
今回は、和室研修室です。
(JR岐阜駅東・三省堂書店東隣)
会 費 : 1,000円(予約不要)
主催・事務局 : 岐阜東洋文化振興会
☆講座終了後にお茶会・飲み会もあります。
☆2023年度 開催予定日:9/9、12/9、2024年 3/9
(いずれも第2土曜日)
☆リーダーの役割~帝王学の書~6月1~6日の6日分の『易経一日一言』(致知出版社)
☆6/10 岐阜駅構内で一般参加OKの易経講座❣(予約不要)
~~~ ☆☆☆ ~~~
【時の流れに従って生きる】
エネルギー切れでものごとが停滞する時に
必要なことは、まず充電です。
無理せず、焦らず、頑張りすぎず、ゆったり過ごすこと。
健康と体力を維持しながら、時の流れに従って生きることが大切です。
一見、消極的なようですが、
そういう陰の力を積極的に使いなさいと易経は教えています。
なぜなら、むやみに焦ってさらに消耗してしまうと、
長い陰の時代に新たな希望を貫いていけないからです。
次の陽の時代への遠い光をたよりに、歩んでいくのが陰の時代です。
真っ直ぐに進んでいくためにも、力を温存していくことが必要なのです。
『超訳 易経 陰』青本より
~~~ ☆☆☆ ~~~
【わからないままに受け止める】
易経は古典の中でもとくに難解といわれますが、
学ぶ時のコツは、わからないことはわからなくてもいい、
わからないままに受け止める、これが大切です。
考えても混乱するだけですから無理に考えず、
自分の考えで決めつけず、繰り返し読んでいくことです。
そして、わかることから学んでいくと、そこから、
わからないと思っていたことにつながって、
あとから理解がついてきます。
見龍の学びもこれと同じで、
大人から教わることを自分の物差しに当てず、
まるごと素直に受け容れなければ型が身につきません。
大地が天の働きをすべて受け容れて、万物を化成するように、
まず受け容れることが自分を育てるのです。
これはわかるけれど、これはいくら考えてもわからない、
できないから違う、などと選り好みしていたら、
歯車の歯がところどころ抜けたような学び方になり、
型が形成されないのです。
「学ぶ」は、もともと「まねぶ」といって、
「真似る」と語源が同じです。
まずは教えられたことを素直に受け容れて真似てみる、
そして自分に問いかけていく。
これが学びの原点であると易経は教えています。
『超訳 易経 陽』赤本より
~~~ ☆☆☆ ~~~
易経一日一言は 6月1~6日の6日分です。
※易経一日一言を一年間通して読まれれば、
易経に書かれているおおよその内容を把握出来ます。
☆本当は一日一言は毎日投稿した方が良いのですが、
出張や資料作りに追われていて、数日分を纏めてUPします。
~帝王学の書~6月1日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆楽天知命☆
天を楽しみて命を知る。故に憂えず。 (繋辞上伝)
天の理法を楽しみ、自分の運命を生きる喜びを知るならば、人に憂いはない。
「楽天」と「知命」は同じ精神である。
いかなる運命でも受け容れ、喜び感謝して生きていく。
これは、天の働き・情理を楽しむ精神である。
この言葉は、楽天家、楽天主義の出典である。
易経は天の理法を学ぶ書。
よく学んだなら、真の楽天家となりうるだろう。
~帝王学の書~6月2日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆無作為☆
耕(たがや)さずして獲(え)る。
しせずしてよする時は、往くところあるに利あり。
(天雷无妄)
田畑を耕さなくとも収穫がある。
また、「しせずしてよする」開墾せずとも田畑がこなれる。
思い込みを捨て、洞察力を持ち、自然に則して生きるならば、
本来、耕作や開墾すら必要ないという意味である。
天雷无妄(てんらいむぼう)の卦(か)は、
作為せず自然の法則のままにまかせたなら、天は万物を養うと説いている。
我々は時として「何もしない行為」を知らなくてはならない。
~帝王学の書~6月3日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆品物形を流(し)く☆
雲行き雨施し、品物形を流く。 (乾為天)
「品物」とは「万物」と同じであるが、
生きとし生けるもの、その一つひとつのものをいう。
人間ならば個々人を指す。
天に雲が巡り、恵みの雨を降らし、地上を潤し、あらゆるものを育てる。
その天の働きによって、品物が「形を流(し)く」、
すなわち個々のものがそれらしく形成される。
これは個々の性質、持ち味、特性を生かし、力を発揮させるということ。
この天の働きは遍く流布するものである。
~帝王学の書~6月4日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆万物資(と)りて生ず☆
至れるかな坤元(こんげん)、万物資(と)りて生ず。(坤為地)
「坤」は天地の「地」、陰陽では「陰」を表す。
「天の気」である太陽の光、雨が地上の至るところに降り注ぎ、
大地はそれを受け取って形あるありとあらゆるもの、万物を育成する。
陰の徳は限りない受容と包容力である。
順(したが)い、受容して育成する、
女性、母、妻、臣下の徳は陰徳である。
ちなみに化粧品メーカーの資生堂は、
この「資りて生ず」から社名をとっている。
~帝王学の書~6月5日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆心の鏡を磨く☆
みずから明徳を昭(あき)らかにす。
(火地晋)
太陽が自ら地の上に昇っていくように、自ら、明徳を明らかにする。
「みずから」とあるのは、自分の心を明るく保つのは自分自身であって、
人に頼ることではないという意味。
明徳は私欲に囚われていると曇ってしまう。
だから、自分の心の鏡が曇らないように、
日々、自分で意識して磨かなければならないのである。
火地晋(かちしん)の卦(か)は、太陽が昇るように前進して、
明徳が明らかになっていく時を説く。
~帝王学の書~6月6日の『易経一日一言』(致知出版社)
☆幽明の故(こと)を知る☆
仰いでもって天文を観(み)、俯(ふ)してもって地理を察す。
この故(ゆえ)に幽明の故(こと)を知る。
(繋辞上伝)
「幽明」の「幽」は形なく眼に見えないもの。
「明」は形あって眼に見えるもの。
たとえば、身体は明、精神は幽であり、
現在は明、過去と未来は幽である。
天の巡りを仰ぎ観て、伏して地上の理(ことわり)を観察するとは、
物事の情態を真っ直ぐに観て、その真相を知るならば、
必ず裏の眼に見えない情態も見えてくるということである。
『易経一日一言』(致知出版社)
#易経
#易経一日一言
#致知出版社
#帝王学
#竹村亞希子の易経
~~~ ☆☆☆ ~~~
岐阜駅で一般参加OKの易経講座(予約不要)
6/10(土)午後、岐阜駅構内の易経講座❣
一般参加可能です❤(予約不要)
【長良川大学・岐阜東洋文化 共催】
人生に生かす易経 ※ご注意‼ 占いではありません。
2023年6月10日(土) 14~16時
演題:【沢水困~四難卦~臥薪嘗胆】
目的を遂げるために苦心し、努力を重ねる。
※サンプルモデルは春秋時代の呉越の戦い。
会 場 : 岐阜駅 岐阜市生涯学習センター
今回は、和室研修室です。
(JR岐阜駅東・三省堂書店東隣)
会 費 : 1,000円(予約不要)
主催・事務局 : 岐阜東洋文化振興会
☆講座終了後にお茶会・飲み会もあります。
☆2023年度 開催予定日:9/9、12/9、2024年 3/9
(いずれも第2土曜日)