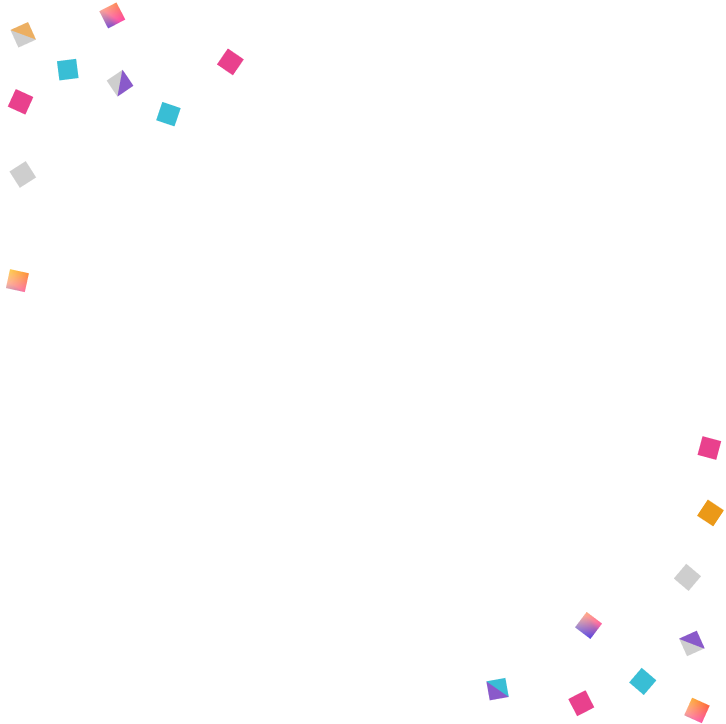
8/15 BSフジ 佐賀さんナビゲートにて、「小早川秋聲 ~旅する画家の魅力!~」
♪私を泣かせてください 佐賀さん自らの歌 BGに 京都画壇最後の大家と呼ばれた
小早川秋聲の魅力を探る番組。
✩Wikipwdiaより
小早川 秋聲(こばやかわ しゅうせい、秋声とも、1885年(明治18年)9月26日 - 1974年(昭和49年)2月6日)は、大正から昭和中期にかけて活動した日本画家。文展・帝展を中心として活躍、今日では「國之楯」を始めとす戦争画で知られている。
鳥取県日野郡日野町黒坂の光徳寺住職、小早川鐵僊の長男として、母・幸子の実家、神戸市の九鬼隆義子爵邸内で生まれる。本名は盈麿(みつまろ)。秋聲の号は、青年時代に愛読していた『古文真宝』収録の歐陽修の詩「秋聲賦」から取ったという。父は京都東本願寺の事務局長を勤め、母は元摂津三田藩九鬼隆義の妹である。幼少時代を神戸で過ごす。弟の小早川好古も日本画家である。
幼い頃から、「おやつはいらないから紙をくれ」とねだるほど絵を好み、ある南画家に就いて日本がの手ほどきを受けたという。父の跡を継ぐよう求められ、1894年(明治27年)9歳で東本願寺の衆徒として僧籍に入り、1900年(明治33年)務めを終えた父に連れられ光徳寺に帰郷する。しかし、画家になる夢を捨てられず、寺を飛び出し、神戸の九鬼家に戻る。翌年、真宗高倉大学寮(現在の大谷大学)に入学。ただ、その後も時々帰郷したらしく、地元には秋聲の初期作が幾つか残っている。 1907年(明治40年)特科隊一年志願兵として騎兵連隊に入隊、陸軍予備役少尉になる。その後の年次訓練などで大正期に陸軍中尉に上がっている。
1906年(明治39年)4月20歳で、四条派に属する谷口香嶠(幸野楳嶺門人)の画塾「自邇会」に入る。1909年(明治42年)香嶠が教授を勤めてる京都絵画専門学校(現在の京都市立芸術大学)開設の年に入学するが、同じ年に早くも退学。祖母利佐の紹介で松平恒雄を頼り、水墨画を学ぶため中国へ渡る。中国では1年半ほど過ごし、文部次郎厳修邸に寄宿しながら、北京皇室美術館で東洋美術を研究し、その合間に名勝古跡を巡る。1912年(明治45年)から日本美術協会展に出品し始める。1915年(大正4年)香嶠が亡くなると、山元春挙主催の「早苗会」に参加、のちに同会幹事を務めた。
この頃からの秋聲の目覚ましい活躍が始まる。1914年(大正3年)の第8回文展に「こだました後」で初入選。以後、文展に4回、帝展に12回、新文展に3回入選し、力作を次々と発表していく。一方で九鬼家の援助で経済的に恵まれていた秋聲は、当時の日本人としては異例なほど頻繁に海外へ出かけている。文展初入選と同年から3年間、度々中国へ渡って東洋美術の研究に励む。更に1920年(大正9年)の3年間は今度はヨーロッパを外遊、翌年ベルリン国立アルトムゼーム研究室で2年学び、帰途にはインドやエジプトにも立ち寄った。他にも1926年(大正15年)3月から7月にかけては、日米親善のためアメリカに渡っている。こうした研鑽から、秋聲の絵は文展・帝展の中でも異彩を放ち、中国やヨーロッパに題材を求めた異国情緒漂う作品も珍しくない。私生活も充実に、1922年(大正11年)に渡欧中ながら結婚、翌年の帰国後、京都市左京区下鴨森前町に豪邸を建てる。
1931年(昭和6年)の満州事変後から1943年(昭和18年)まで、関東軍参謀部、陸軍省の委嘱により、従軍画家として中国や東南アジアなどの戦地に度々派遣され、戦争画を多く描く。画家の従軍が本格化するのは、1937年(昭和12年)の日中戦争後であり、秋聲の従軍はかなり早い。1941年(昭和16年)には大阪朝日会館で、洋画側の代表藤田嗣治と共に、従軍日本画家の代表として講演している。一般に戦争画は、華々しい戦闘場面や勇壮な日本兵の活躍を描いた作品が多いが、秋聲の作品にはそうした絵はあまり無く、戦場での兵士たちの苦労や、兵士の死を悼む作品が散見される。終戦時の秋聲は、自分が「戦犯」として捕らえられるのを疑わなかったという。
秋聲は将官待遇で従軍していたため、戦地でも贅沢が出来たはずだが、共に戦う者として自身にも厳しい従軍生活を課していた。ところが、従軍生活の長さからくる凍傷で体調を崩し、1944年(昭和19年)には肺炎をこじらせる。1946年(昭和21年)日展委員となるも、多作や大作がこなせるまでは回復せず、戦後は依頼による仏画を手がけたと言われる。1974年(昭和49年)老衰により京都で亡くなった。享年89。墓所は大谷祖廟。
- 「國之楯」 紙本著色 額1面(151.0×208.0cm) 京都霊山護国神社蔵(日南町美術館寄託) 1944年(昭和19年)(1968年(昭和43年)に一部改作)
- 日本兵の遺体を全面に取り上げた、戦争画の中でも異色の作品。黒一色で塗りつぶされた背景に、胸の前で手を組んだ日本兵が大きく横たわっている。顔には「寄せ書き日の丸」が深く覆いかぶさり、この名も知れぬ兵士がお国のために死んだ事実が明瞭に示される。手や腕、胴体はやや誇張的に重量感をもって描き出され、観者は「動かなくなった人間の肉体」を強く意識させざるを得ない。
- 当初は「軍神」という題名で、遺体となって横たわる兵士の頭部背後には金色の円光、背後には桜の花弁が降り積もるように山なりに描かれていた。しかし、後述の返却後、秋聲は背景を黒く塗りつぶし「大君の御楯」と改題、更に23年後『太平洋戦争名画集 続』(ノーベル書房、1968年)に収録される際、一部改作して「國之楯」と再び題を変えて現在の状態になった。こうした度々の改題・改作は、戦中から戦後の社会通念の変化に伴い、尽忠報国から追悼・哀惜へと作品を転化させる操作とみられる。
- 本作品は、元々天覧に供するために陸軍省から依頼された作品である。絵の完成を聞きつけた師団長や将校たちは、この絵の前で思わず脱帽・敬礼し、搬出を手伝いに来た女性は絵を前に泣き崩れたという。しかし、戦死者の視覚化は戦争表現や「死の美化」に必須な一方、厭戦感を引き起こすとして、軍部・美術家共に非常に神経質な命題だった。代表的な戦争画である藤田嗣治の「アッツ島玉砕」でも、画中の死体は全てアメリカ兵である。最終的に陸軍省は本作品の受け取りを拒否し、秋聲の手元に残された本作は前述のような改作を受けることになった。






























