▼本日限定!ブログスタンプ
ひな祭りは、古くは「上巳の節句」「弥生の節句」などの呼び名があり、五節句(「人日」「上巳」「端午」「七夕」「重陽」)の一つにあたります。女の子がいる家ではこの時期にひな人形を飾り、白酒や桃の花を供えてお祝いします。
ひな祭りの起源は中国までさかのぼれるとされています。昔、漢の時代の徐肇(じょちょう)という男おり、3人の女児をもうけたにも関わらず、3人とも3日以内に死んでしまいました。その嘆き悲しむ様子を見た同じ村の人たちが酒を持ち、3人の女児の亡骸を清めて水葬したことに由来しているとされています。それが平安時代になると、「上巳の祓い」といって、3月3日に陰陽師を呼びお祓いをさせ、自分の身に降りかかる災難を自分の生年月日を書いた紙の人形(ひとがた)に移らせて川に流しました。この厄払い様子は今でも下鴨神社で行われる「流しびな」の行事に再現されています。
この紙のひな人形が発展し、現在の豪華なひな人形になったとされています。また、ひな壇を設けるようになったのは、江戸中期からだそうで、それまでは畳に直にじゅうたんを敷き、人形や調度を飾っていたとか。
ちなみに、京都では宝鏡寺が別名「人形寺」とも言われ、光格天皇遺愛の品のほか、多くの人形が納められています。10月には人形供養の行事も行われます。
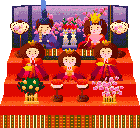
 京都・ひな祭りのお作法
京都・ひな祭りのお作法
①ひな人形の配置について
②桃の花と柳を飾るわけ
③おひな様とお嫁入りの深~い関係
 ひな祭りの和菓子(雛菓子)
ひな祭りの和菓子(雛菓子)
 |
| ひな祭りには欠かせない、伝統の ひな菓子「ひちきり」。(甘春堂製) |
ひな人形を飾って、桃の花と、白酒、菱餅、ひなあられ・・・。女の子節句だけあって、女性の大好きなピンクとホワイト、パステルカラーで楽しいですよね!
ところで、京都ではひな祭りには、「ひちきり」をいただく風習があります。ひちきりは赤・白・緑など、優しい色合いのカラフルな上生菓子です。
形は「阿古屋(あこや)貝」を模していると言われ、片方の先端がピッて切れていて、成形するときに生地を「ひっちぎって」作ることから 「ひちきり」の名がついたと伝えられています。
一説に阿古屋貝は、女性の性を表現したもので、 「子宝に恵まれるように」という願いが込められているとか。
全国に知られた菱餅は5色のお餅。茶色→黄色→緑→白→赤 の順ですが、これは土から葉が伸びて、茎があって、花が咲く順だよと聞いたことがあります。3色のものは、赤(桃の
 |
| 最近は、さまざまなひな菓子があります。 これは干菓子のおひな様。(甘春堂製) |
伝統のひな菓子には、「菱餅」「ひなかご」「ひなダンス」などがありますが、初孫や初めての子供さんの初節句にはぜひとも、飾っていただきたいものです。
最近は、おひなさまのお干菓子や、夫婦の深い縁を表した「貝あわせ」のお菓子もおひなさま用に作られています。お好みのひな菓子を用意して、楽しいひな祭りをお過ごしくださいね。



