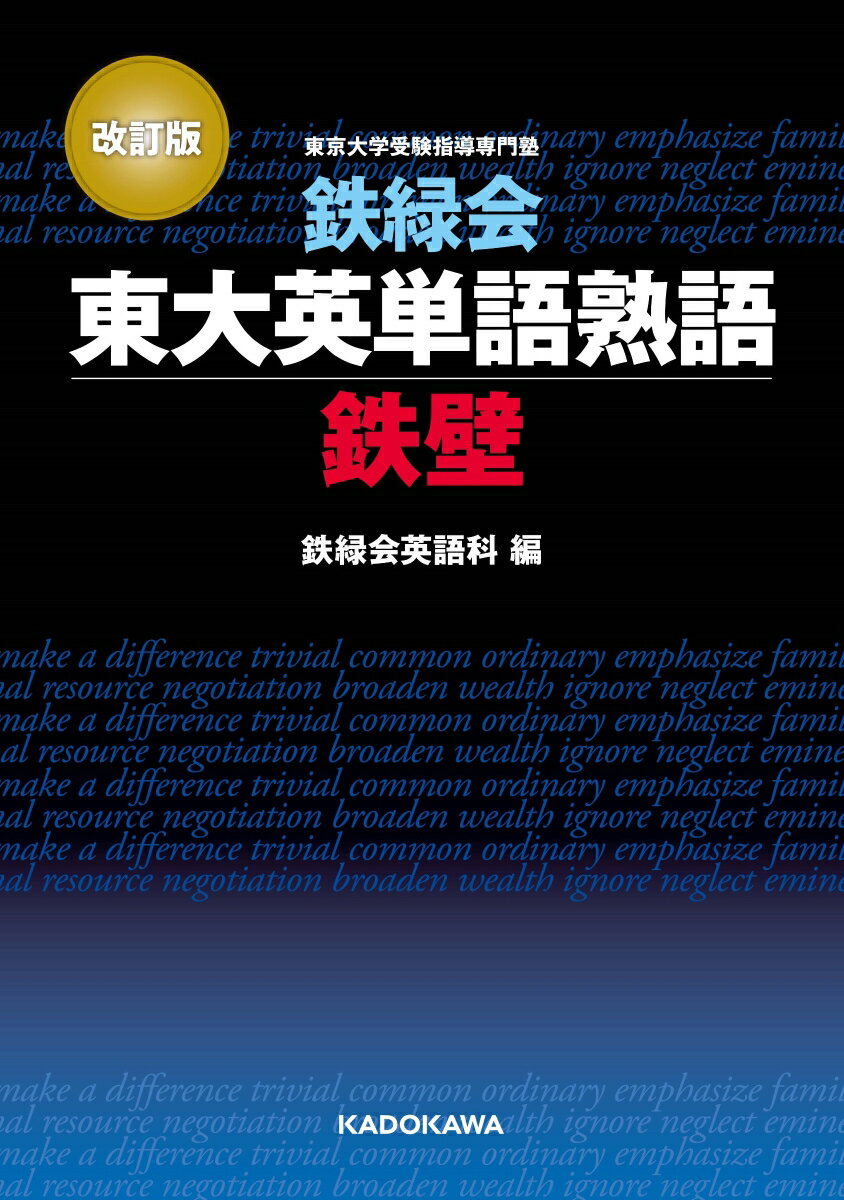・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・
生徒の満足度90%超!
大学受験の予備校で、現代文の指導をしているaikoです。
「大学の、その先」を考えた教育を提案します。
はじめましての方はこちらもどうぞ。
・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・
春。
学校と同時期に 塾の通常授業も始まりました。
小中高どの学年であっても
新しいクラス、新しい先生つまり新しい環境
久しぶりの登下校
だけでも慣れずに疲れていると思います。
ゆっくり休ませてあげてくださいね。
もともと鉄緑会という塾は
どの方面からも否定されがちですが、
SAPIXに対する批判も相当で、
もっと言うと御三家など進学校に対する批判も
多々 見受けられる傾向が
最近強いなと感じています。
東大など高学歴に対する批判はもともとあるけど
個人的な感想としてはこの現象は
学力的に至らない人々が
妬みにより
上層部の足を引っ張っている
状態だと思っています。
もちろん、
社会に出てみたら
本当に使えない高学歴の人材もいるし
女性をモノのように扱う高学歴の男性もいるし
すごく差別的な高学歴の人達もいるし
「お勉強だけできても、ねぇ···」
と言いたくなる人は たくさんいると思います。
でもそれ以上に、
優秀な人がたくさんいるし
差別的であることを指摘されたら
自分を変えられる人が多いのも
高学歴層の印象です。
どんなに指摘されてもいつまでも直せないのって
高学歴の人達ではないように思う。
結局は個人の問題
と言ってしまえばそれまでなんですけど、
高学歴の人達は総じて優秀ですよ。
少なくとも社会的には。
家庭でどうかは本当にその人による
SAPIXも鉄緑会も、
たいていの生徒・学生にとっては
学習量が多いのは事実です。
それで結局、歪みが出てしまう。
両方とも
通っていい生徒
通うのに向いている生徒を
選ぶ塾だと思います。
かなりの割合が
通うのに適していないのに無理して通うので、
歪んで 批判に繋がってしまうのだと思う。
1つ言うなら、
大学生アルバイトが多いという指摘は
まぁ分からなくはないです。
でもしっかり研修しているし、
本当にプロの講師に習いたいなら
上のクラスに入るか 他の塾を選べばいい話。
「プロ講師のみです!」と宣伝していて
実は大学生を使っているなら
批判されてしかるべきですけど。
そうではないですよね。両塾とも。
なのでSAPIXや鉄緑会を批判していいのは、
通う資格のある人達だけです 本来は。
これは進学校にも言えます。
私立の学校に通うなら
学校の基準を満たしていることが条件です。
満たしていないのに「自主退学を命じられた」と
SNSに学校批判を書き込むのは
違うんじゃないかなぁ···と私は思ってしまう。
モンペでしょこれ
きちんと塾や学校を選ぶのが大切です。
その子に適した環境
かつ
少しその子より上だから
その子を伸ばしてくれる環境
を選んでいきましょう!