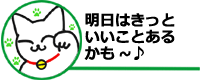社会一般:国民健康保険法
国民すべてが何らかの医療保険に加入している=「国民皆保険」である我が国の医療制度
その中で、すでに勉強した「健康保険」は、労働者(+被扶養者)を対象した「被用者保険」です。
(※被用者≒労働者)
それに対して、国民健康保険は自営業者や農業者など、被用者保険に加入していない人を対象としています。
イメージとしては、広く国民を対象として、その中で他の被用者保険等に加入している人は除く感じ。。。
大きく医療制度を支えていると言えますね。
●目的
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、
もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
国民健康保険には、被扶養者という概念がありません。
ですから、たとえば、自営業者の一家。
自営業を営むお父さんも、専業主婦のお母さんも、学校に通う子供たちも、隠居しているおじいちゃんやおばあちゃんも、みんな被保険者なんです。
●保険者
国民健康保険の保険者は、市町村(特別区を含む) & 国民健康保険組合です。
国民健康保険組合というのは、同種の事業や業務に従事する者で。組合の地区内に住所を有する者を組合員として組織する法人です。
例えば、医師や税理士、美容師などで組織する組合があります。
(東京芸能人国保組合なんてのもあるんですよ。)
建設業に従事する人が加入できる「全国建設工事業国民健康保険組合(建設国保)」が、「関係ない人を加入させていた」と、数年前ニュースで取り上げられていましたよね。
組合を作ろうとするときには、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行います。
そして、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければいけません。
(地域ごとですから、厚生労働大臣ではありませんよ。)
●被保険者
市町村のおこなう国民健康保険の被保険者は、一般被保険者 & 退職被保険者とその被扶養者です。
(組合の被保険者は一般被保険者だけです。)
一般被保険者というのは、市町村の区域内に住所を有する者のことです。
ただし、以下の者は被保険者とはなりません。
・健康保険法の規定による被保険者
・船員保険法の規定による被保険者
・公務員など、共済組合の組合員
・上記制度に規定する被扶養者
・日雇特例被保険者手帳の交付を受けている者(印紙を貼る余白が残っている者)とその被扶養者
・後期高齢者医療制度の被保険者
・生活保護法による保護を受けている世帯
・国民健康保険組合の被保険者
・その他、厚生労働省令で定める者
簡単にまとめると、他の制度でフォローされている人は、国民健康保険には入らないということです。
退職被保険者というのは、国民健康保険の被保険者のうち、被用者年金各法などに基づく老齢 or退職を支給事由とする年金たる給付を受けることができる者のうち、以下に該当する者をいいます。
・年金保険の被保険者等であった期間が20年以上
・40歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であった期間が10年以上
この制度は実はもう廃止されたんですが、経過措置としてH26まで残されています。
●保険給付
実施が義務付けられている法定必須給付と、特別の理由があれば行わなくてもいい法定任意給付、行うかどうかが任意である任意給付の3種類があります。
健康保険法で出てきた給付のうち、出産育児一時金と葬祭費(葬祭給付)が法定任意給付です。
また、傷病手当金、出産手当金は任意給付です。
で、それ以外の給付は法定必須給付となっています。
また、健康保険にはなかった給付として、特別療養費があります。
(特別療養費の内容は後述します。)
自己負担額(一部負担金)ですが、原則は3割負担です。
~6歳3/31と70歳~については2割負担ですが、70歳~であっても一定以上の所得がある人は3割負担となります。
・・・というのが法律どおりの割合なんですが、「平成26年3月31日以前に70歳以上の方」については減額措置が取られており、1割負担となっています。
健康保険法のところでも書きましたが、「うちの子は小六だけど医療費タダだよ。」というのは、みなさんのお住まいの自治体が独自に補助をしているからです。
●給付制限など
保険料を滞納すれば保険証を返さなければいけません。
でもいきなり取り上げて、「お金を払わないんだから後のことは知らないよ!」なんていうことは、人道的にもちょっと・・・
ということで、滞納者に対しても段階をふんだ手続が取られています。
納期限から1年6ヶ月を経過しても、なお滞納しているときには、(あらかじめ通知して)一時差し止めにかかる保険給付の額から、滞納している保険料額を控除することができます。
ここまでが基本的な流れです。
18歳3/31までの子供がいる世帯については、被保険者資格証明書を交付されている世帯の子供であっても必要な医療を受けれれるよう、被保険者証を交付されます。
(親が滞納していても、子供は療養の給付を受けれるようになっています。といっても有効期間が6ヶ月しかありませんから、問題をちょっとだけ先延ばししただけ、、、のような気がしますが。。。)
ところで、被保険者証と被保険者資格証明書の違いですが、証明書では療養の給付が受けることができません。
ということは、風邪をひいて病院に行った場合、被保険者証を持っていれば窓口負担は3割ですが、証明書の場合は全額自己負担です。
で、後から特別療養費として、自己負担分を除いた額が現金給付されるというシステムです。
(療養の費用の給付と同じような方法ですね。)
保険料を払えないから証明書になっちゃったのに、(仮にとはいえ)窓口で全額自己負担するのは大変でしょうね。。。
↓サクラ咲くために、毎日1クリック↓