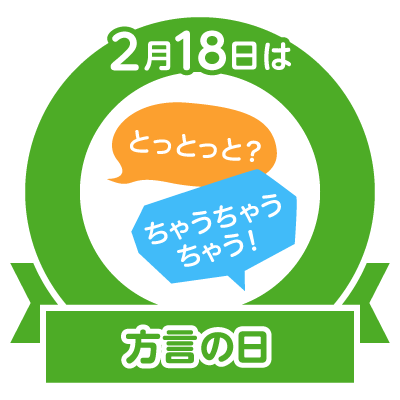■ 2月18日は「雨水の日」
雪から雨へと季節が移ろい、雪氷が融け始め雨水となり始める。
寒さも峠を越え始める。「春一番」が吹く。しかし一方で、大雪が降ったりもし、「三寒四温」を繰り返しながら春に向かう。
鶯(うぐいす)の鳴き声が聞こえ、草木が芽生え、農耕の準備を始める。
「雨水の日」に雛人形を飾ると良縁に恵まれるとの言い伝えがある。
一昨日~今日の三日間は、暦とは違い、冬型の気圧配置に戻って冷たい北西の風が吹いた。
"ステイホーム"の一日だった。
否! モスバーガーを買いに行った(笑)。
実況気象衛星画像
20210218--12:00

日没の西空
20210218--16:58 (日没の27分前)

**
■ 2月18日は「方言の日」
「鹿児島県大島地区文化協会連絡協議会」(大島支庁総務企画課)が、近年、衰退しつつある奄美方言を保存・伝承して行くことを目的として、2007年に制定した。
*
□ お題「方言が可愛い芸能人といえば?」
▼本日限定!ブログスタンプ
佐々木希さんの秋田弁・・・1988年2月8日秋田市生まれ。2003年秋田市立飯島中学校卒業。

鈴木ちなみさんの岐阜弁・・・1989年9月26日岐阜県土岐郡笠原町(現・多治見市笠原町)生まれ。2005年金城学院中学校卒業。2008年金城学院高校(名古屋市東区白壁)卒業。2013年立教大学コミュニティ福祉学部コミュニティ福祉学科卒業。

川口春奈さんの五島弁・・・1995年2月10日長崎県五島列島福江島(福江市、現・五島市)生まれ。2010年五島市立福江中学校卒業。2013年堀越高校(東京都中野区中央2丁目)卒業。

◇--------------------------------------------------------------
NHK-E「サイエンスZERO」
「"withコロナ時代" にいまこそ知りたいウイルスの正体」
初放送2020年7月12日(日) 23:30~24:00
再放送2021年2月20日(土) 11:00~11:30
■ 出演者
主なゲスト:
朝長啓造(京都大学/ウイルス・再生医科学研究所ウイルス感染研究部門/教授)
長﨑慶三[高知大学/農林海洋科学部長﨑(水圏ウイルス)研究室/教授]
MC: 小島瑠璃子(タレント)、森田洋平(アナ)
ナレーション: 川野剛稔(声優)
*
■ 番組概要
ウイルスとは何なのか?
新型コロナと向き合って行く時代に、知っておきたい情報を専門家とともに深掘りする。
感染の仕組みや、病原性を左右する要素など、ウイルスが我々に脅威をもたらす背景を明らかにする。
そして今、 ウイルス研究自体も大きな転換点を迎えている。
ウイルスと生物の関わりは、長い進化の過程を経て驚くべきバランスを生み出していた。
これまでの常識から大きく飛躍する最新の「ネオウイルス学」にも迫る。
**
■ 番組詳細
□ 細菌とウイルスの発見
▽ 細菌(微生物)
17世紀に、細胞の存在が認識され始め、レーベンフックが17世紀後半に顕微鏡で「細菌(微生物)」を観察した。19世紀に掛けて、研究者によって生命に関する疑問がまとめられ体系化し「細菌学」ができた。
①微生物は化学物質(有機物)。
②生命特有の現象だと考えられていた発酵は、触媒(酵素)による微生物の化学反応。
③自然に発生することなく、微生物自身からしか生まれない。
④微生物の感染によって生物の病気(感染症)が起こる。
⑤1個の微生物が生物に侵入(感染)すると、同じ微生物は二度と侵入しなくなる(免疫の発生)。
⑥微生物による感染症と思われるのに、顕微鏡では見えない病原体があり、それがウイルス。
1860年前後の微生物自然発生説を否定する「パスツールの微生物学実験」と、1876年の「コッホの4原則」とが、「近代細菌学の開祖」とされた。
*
▽ ウイルス
19世紀末にはウイルスとそれが引き起こす感染についての科学的研究が始まり、1931年にドイツのマックス・クノールとエルンスト・ルスカらによって電子顕微鏡が発明された。
1933年にイギリスのウィルソン・スミス、クリストファー・アンドリュース、パトリック・レドローは、ワシントンで発生したインフルエンザの患者から分離されたウイルスを使って、フェレットの気道に感染させてヒトのインフルエンザとよく似た症状を再現できることを実験的に示し、
インフルエンザの病原体がウイルスであることが明らかとなり、「インフルエンザウイルス」(後にA型インフルエンザウイルス)と名付けられた。
1939年に初めてウイルス粒子の観察が可能となり、20世紀後半はウイルス発見の黄金時代でウイルスの多くが発見された。
▽ 新型コロナウイルス
1960年代には風邪をひいたヒト患者の鼻腔からヒトコロナウイルスが発見され、
電子顕微鏡写真でウイルス構造との類似が指摘され、1968年には 「コロナウイルス」 と命名された。
最初の4種類は風邪の病原体となる症状の軽いウイルスだったが、以下のウイルスが重篤化傾向を示し始めた。
2003年、「SARSコロナウイルス (SARS-CoV)」・・・病気名:重症急性呼吸器症候群 (SARS)。
2012年、「コロナウイルス (MERS-CoV)」・・・病気名:中東呼吸器症候群 (MERS)。
2019年、「新型コロナウイルス (SARS-CoV-2)」・・・病気名:新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)。
ウイルス自体は自己増殖できない。他の細胞に侵入(感染)することで増殖する。
コロナウイルスは王冠を示すように、突起を持っていて他細胞膜にあるレセプターと言う突起を利用して細胞内に侵入する。
コロナウイルスの突起は石鹸やエタノールなどに弱く壊れやすい。手洗いや消毒が効果的。
鼻や口から吸い込んだ空気は喉頭(こうとう)を通り気管に入る。気管は左右の肺の中に入ると2つに分かれて気管支となり気管支はさらに細かく分かれて肺胞(はいほう)という空気が入った小さな袋がブドウの房のように付いている。
インフルエンザウイルスは主に喉頭などの軟膜などに感染するが、
新型コロナウイルスは、重篤化した場合には肺の奥まで感染し肺だけでなく心臓などにも大きなダメージを与え、呼吸不全を起こすので人工心肺(エクモ)が必要になる。
狂犬病ウイルスも侵入点(犬に咬まれた箇所)から神経に沿って脊髄に移動し、更に脳に移動して増殖し、ほぼ必ず死に至る。
*
□ 生態系のメカニズム
▽ オオバコアブラムシ・デンソウイルス
オオバコアブラムシが増え過ぎて一つの植物(オオバコ)上で "密" になると、オオバコを枯らしてしまう。そこで個体数を減らすメカニズムが働く。
植物に感染しているオオバコアブラムシ・デンソウイルス (パルボウイルス科) が、動物のオオバコアブラムシに感染し通常は現れない個体が誕生する。つまり感染したオオバコアブラムシが羽を生やす (羽の生えた個体を発生させる)。
羽が生えたアブラムシは他の植物に飛んで行く ("密" の状態を分散させる) ことができるから、アブラムシの "密" も解消されて生存に有利となりウイルスも別の植物に移動できることになる。
▽ ヘテロシグマ・アカシオウイルス
海には10の31乗個のウイルスが存在すると言われ、それらの中には養殖魚に感染して病気を引き起こすような「人間にとって都合の悪いウイルス」がいる一方で、「人間にとって都合の良いウイルス」も存在する。
例えば、漁業・養殖などで大きな被害を与える「赤潮」は藻類の異常な増殖により引き起こされる現象。
「赤潮」の発生に関与しているプランクトンにヘテロシグマ・アカシオウイルス(HaV)が感染すると、細胞内でウイルスが繁殖して分解され「赤潮」も解消する。ウイルスの感染によって宿主となる生物の "密" が解消される仕組みが自然界の中で出来上がっている。天敵となるウイルスがいても「赤潮」が絶滅する訳ではない。年が変わればまた同じ赤潮が発生し、ウイルスが増え、そんなサイクルを繰り返す。ウイルスは、宿主と或る種の友好関係、即ち、お互いを決して絶滅させることはない---という約束の下に共存関係を果たしている。
▽ 生態系(まとめ)
普通の生物は栄養を取り込み細胞分裂により自己増殖する。ウイルスも増殖するが、感染可能な相手(宿主)がいない限り増殖することはできず、「他者(宿主)に依存する人」という意味ではパラサイトであり宿主を殺すこともできる。宿主がウイルスを増殖するだけの関係だったら、宿主は死に絶えウイルス複製の場は無くなってしまう筈。
しかし実際は多くのウイルスと宿主は平和的に共存・共生している場合が多く、増減調整で丁度良いバランスの個体数を維持しており、それがマクロで考えると地球の生態系を形作っている。
地球上の人口は僅か十数年のうちに現在の77億人から約85億人に増え、更に2050年までにほぼ100億人に達する見込み。世界の飢餓人口の増加は続いており、2017年には8億2100万人、9人に1人が飢えに苦しんでいる。2050年までに60%も食料生産を増やす必要があり、また、これも人間の行為で二酸化炭素排出量が産業革命後に急速に増え、温暖化現象が起こり気候不順で農産物も漁獲量も減る傾向にある。
現在、地球の生態系の頂点に君臨する人類。その天敵となっていたのが天変地異と病気。天変地異については台風・地震・津波など昔に比べれば死者はかなり減少して来た。しかし病気については、古代から天然痘・ペスト・コレラなどの伝染病で人類の存在を危うくするような死者を出し、伝染病との戦いの歴史を積み重ねて来た。それは人類から見れば戦いの歴史だが、地球の生態系から見ればバランスを調整しているとも言える。
18世紀以降は細菌そして20世紀に入るとウイルスについても治療を見つけ出すことができるようになり、死者が減少し生態系のバランスを超えて人類だけが増加している。更に人類は遺伝子操作で新たに細菌・ウイルスを作ることができ、理論的にはクローン人間も作れる「神の領域」に踏み込んでいる。
近年、耐性菌が増え抗生物質が効かなかったり新型コロナのようなパンデミックが増えて来ており、「神の領域」に踏み込み地球の生態系を壊し、やがてそれは人類の滅亡に繋がる警鐘かも知れない。
*
□ ウイルス研究でも「ネオウイルス学」が注目されている。
これまでDNAでも遺伝子・遺伝子配列のみが注目され、それ以外の98~99%はゴミと言われた部分の働きに注目が集まっている。
「ウイルス学」も20世紀後半に様々なウイルスが発見され、病気・毒性などに注目が集まっていた。DNAのゲノム解析の進歩で、親密なウイルス間の共生、ウイルスと宿主の共生・共進化、あるいは生態系でのウイルスの隠れた機能が見えて新しい局面を迎えている。
20世紀後半はウイルス発見の黄金時代と言われているが、まだまだ多様で個性的なウイルスが多く存在する。
2015年の発見数は4,225だったが、2020年には200倍強の865,000に急増。それはゲノム解析技術の急速な進歩があったからに他ならない。