◆『私がここで論じているのは、多く学び、多く聞き、多く見ることを尊ぶ朱子学のような学問とは違って、〈無の中から有を生じさせる(無中生有)〉工夫についてのことなのです』
昨年11月に入稿した中江藤樹の評伝が、なかなか刊行に至らないので、今は、『口語訳「伝習録」下巻(仮)』の執筆を急いているところです。
久々に、王陽明の言葉が心に響きました😊。
今回、ズシリと来たということは、かつては分かったようでいて、実際のところは、よく分かっていなかったということを意味するのでしょう(冷汗)。
正直、数十年前から、こうした状態の連続です。言い換えれば、陽明学とは、それほど奥が深いということなのです。
今回、う~んとうならされた個所は、以下です。
ただし、私が、私がうなったからと言って、これを読んだ方が皆、私と同じ思いをすることはあり得ませんよ😊。( )内は、原文。一部、分かりやすくすすために、加筆しました。
「私がここで論じているのは、多く学び、多く聞き、多く見ることを尊ぶ朱子学のような学問とは違って、
〈無の中から有を生じさせる(無中生有)〉
工夫についてのことなのです。
君たちは、とことん信じることが必要です。
そのためには、しっかりと志を立てるしかありません。
学ぶ者の心の内に兆し芽生える善行への志というのは、たとえるなら樹木の種のようなものなのです。
助長することなく、かといって忘れさることもなく、ただひたすら大切にして養い育てていけば、自然と日夜を通して成長し、生命エネルギー(生気)は日に日に充実し、枝葉は日に日に生い茂っていきます。
ただし、苗木の段階で、余分な枝を選んで摘み取っておかなければなりません。そうしてこそ、根や幹は、大きく育つことができるのです。
学問を学び始めた人も同じです。だから、志を立てるときには、一心不乱(専一)であることを尊ぶのです」(『伝習録』上巻116条、参照)
「〈無の中から有を生じさせる〉工夫」とは、王陽明の教え、つまり陽明学のことです。
「学ぶ者の心の内に兆し芽生える善行への志」というのは、「良知」のことです。その善行への芽、つまり良知を大切にして養い育てなさいというのです。
◆「善人を演じて生きるのではなく、真の善人になるぞ」 との志をしっかりと立てることができていない人が、いくら陽明学や禅仏教や、その他の自己啓発の本をたくさん読みあさったところで、真の自己修養にはなっていない
陽明に言わせれば、
「絶対、聖人になるぞ」
との志、換言すれば
「善人を演じて生きるのではなく、真の善人になるぞ」
との志をしっかりと立てることができていない人が、いくら陽明学や禅仏教や、その他の自己啓発の本をたくさん読みあさったところで、真の自己修養にはなっていないと言うのです。
知識が増えることと、私欲を減らすこととは、別問題なのです。私欲が減らない限り、心を正し、真の善人になることはできない相談なのです。
▼『「伝習録」標註傳習録』全四冊
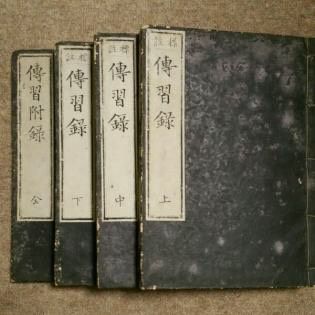
![]()
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
ランキングに参加しました。
クリックしてください。