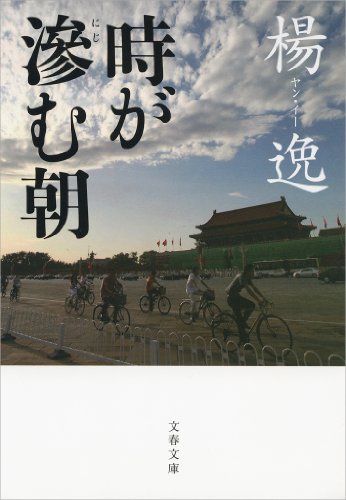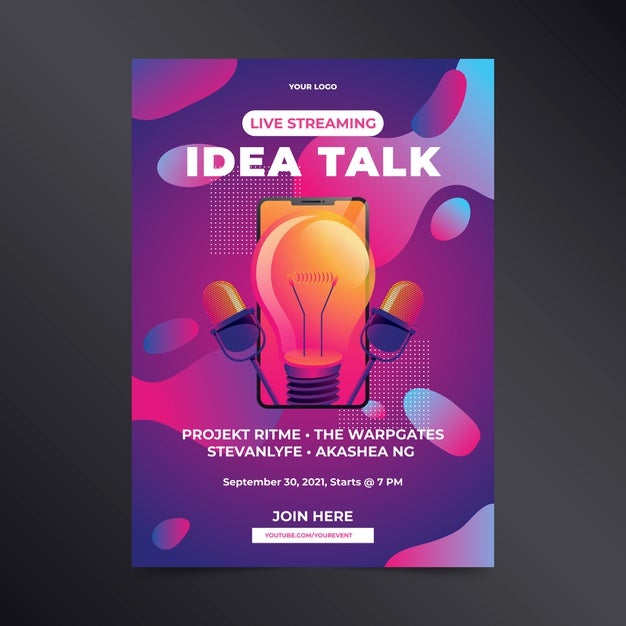∂さいはての中国(小学館新書)
安田峰俊 (著)
形式: Kindle版
∂読者レビューから引用・加筆
中国の繁栄を、どう解釈すればよいだろうか?
経済規模は、既に日本の3倍になり、未だに日本より遥かに高い経済成長を実現している。統計操作をしているからだろ!と突っ込む人がいるかもしれないが、経済規模だけではなく、科学技術や学術分野でも、多くの分野で日本を圧倒している。
そんな状況の中で、以前は中国経済「ヤバい論」(良い意味でも、悪い意味でも)、
「一党独裁の政治体制への批判」、「人権問題」、そして、「中国脅威論」や「嫌中論」
また中国のIT分野などを見て、「中国スゲー論」や爆発的な訪日観光客の増加に伴う、
一部の「中国人の行動」を見て「イラっとする論」など、バランスを欠いた見方が目立つ。この本は、割とバランスが良いと思う。
著者は、専門が中国現代史だけに、
その豊富な知識と、おそらく高い語学能力と、中国への並々ならぬ好奇心がある。
また、現地の情報を見聞きし、また現地の人と交流をして、ルポしていることがわかる。
多くの中国通が跋扈している日本だが、バランス良い見方をしている人は、供給面でも、需要面でも、ほとんどいない。その中で、著者は、割とバランスが良い見方をしている。
ただ、中国レポの難しい所は、ある一か所の現象を見て、中国を語ることはできないことだ。ある一部の現象をみて、全体を語ることができない。
一つの省で、日本と同程度の人口規模を抱える国だ、そもそも中国には、ある母数から「平均」を導き、それが重要だという概念が箕臼だ。著者も、それをよく知っているからだろう、取材テーマ―が、かなりバラバラだ。しかし、バランスがいい。
繁栄している影で、中国では多くの問題が噴出している。民主的には、問題が噴出してきた方がよい、なぜなら、問題がないと解決できないからだ。
中国が抱える問題は、中々、その大小関わらず、正確にはわからない。
だから、本当の所は、いったい何が起こっているのか、多くの人はわかっていない。
それは、日本で報道されるものならば、なおさらだ。
例えば、教育。過激な学歴競争で多くのモノが脱落する。
日本だと1800人に1人の学生は東大に入れるが、中国だと8500人に1人しか清華大か北京大には入れない。また近年は、良い大学を出ても簡単には就職は見つからない。
また、良い就職が見つかっても、組織では、成果を厳しく要求される。そういう現状に対して、今の所、若い人の反発や、改革が、大きなうねりとなって、行動としては、現れていない。制度や体制を批判することは、できない。
中国では、過激な競争で勝ってきた見返りがあまりに小さいと思う。
もうすでに、多くの中国の方が、努力と報酬がまるで見合っていないことを、知っている。しかし、豊富な社会資源がなければ、この現状から、脱出することはできない。
激烈な競争社会の中で、多くの中国の方は、もちろん疲れ、疑問に思っている。しかし、圧倒的多数の弱者が社会批判をすることはできない。現状ますます競争は苛烈になっている。競争に敗れた者は、「努力をしなかったからだ」という社会コンセンサスが、強力にあり、そういう者は、発言する資格もないし、場所もない。ネットは以前、そういう場だったが、取り締まりが厳しくなり、また、言っても変わらないことを、心の底から理解している。
中国が残酷な所は、「自分の代わりは、いくらでもいる」ことだろう、だから、如何に価値があるかが大事になり、自分に付加価値をつける行動をする。
1を10に言ったり、できないことも、できると言わなければ、いけないのは、何が本当や嘘かという基準ばかりではなく、その社会に背景がある。
経済規模や成長率は、ある程度、生産年齢人口やその増加率で決定されるが、
中国は、この二つが、莫大にいて、またこれから数十年に渡って労働者が増える。
これは、経済成長がこれからも続くことを意味するが、
それが、果たして、多くの中国の方に良いかという問題がある。
この著作では、中国深セン三和地区を中心にネットゲームにはまる若者に、
インタビューをしている章がある。中国のどの都市でも、こういう光景は見れる。
今の所は、そういう社会の底辺にいる若者がなれる就ける職業は少なくない。
成長と共に、莫大な関連産業や仕事がうまれているからだ。
そういう職業は、良い意味でも悪い意味でも「食っていける」。
また、政府や企業も失業率を気にするので、
ぎりぎり食っていける職業を生み出すことには余念がない。
「競争に負けたからから、ああなった」と、多くのモノは言う。
本人も、それを自覚している。
競争に勝った人と負けた人のコミュニケーションが、
中国には存在しない。
「話しを聞いてほしい、実は、、、、」と言っても、
誰も耳を貸さない。
耳を貸すのは、自分にとって、利益があるか、ないかだ、
他人に同情する余裕は、あまりない。
それよりも、家族と自分の利益を絶対優先で考える。
当たり前と言えば、当たり前な行動をしている。
一度、競争を降りたら、そこで人生がほぼ終わりなのが中国という社会だ。
ホッと一息できるのは、ある恵まれたごくごく一部の層だけだ。
中国では、ある一部の層と、その関係を持っている人が、
多くの資源、それは、政治、経済、教育、医療など、あらゆる分野を、
管理(実質は支配)している。ほとんどの者は、競争に絶対に参加しなくてはいけないが、
その競争に勝つことは、ほとんどできなく、脱落も許されていないのが、中国社会だ。
こんな過激な社会が日本の近くにある。
違って視点で見れば、多くの学びを得ることができる。
どの国でも生きるのは大変だが、現在、衰退していっている国に住んでいるのなら、
なおさら、中国という国や人に対して、偏った見方が生まれてしまうだろう。
しかし、中国の動向を正しく知ることやと中国人の生き方を交流を通して知ることは、
私たちに多くのことを気づかせてくれると感じる。その入門書として、本書をおススメしたい。
∂内容(「BOOK」データベースより)
ようこそ、ちょっと不思議で、心底怖い中国の旅へ。“アジアのシリコンバレー”深〓(せん)をさまようネトゲ廃人、広州に出現したアフリカ人村、内モンゴルの超弩級ゴーストタウン、謎のゆるキャラ勢揃いの共産党テーマパーク、さらには、日本や東南アジア、北米カナダまで。未知なる中国を探し求める著者は「さいはての地」で何を見たか?現代中国を炙り出す弾丸ルポルタージュ11連発! --このテキストは、paperback_shinsho版に関連付けられています。
∂著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
安田/峰俊
1982年、滋賀県生まれ。ルポライター。立命館大学人文科学研究所客員研究員。立命館大学文学部卒業後、広島大学大学院文学研究科修士課程修了(専攻は中国近現代史)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) --このテキストは、paperback_shinsho版に関連付けられています。
∈画像クリック🔁開けゴマ Open Sesami