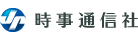【ニューヨーク時事】国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウオッチ(HRW)は14日、各国の人権状況に関する年次報告書を公表し、「日本の『人質』司法制度は容疑者を長期にわたり過酷な状況で拘束し、自白を強要している」と批判した。
アベ政治の主張する「自主憲法」というものは何か?。次の動画を見ればよくわかる。
『哲学のすすめ』(岩崎武雄著)の中にこんな一節がある。
【 たとえば、もしわれわれが、自分の基本的人権を主張し、「もしこの基本的人権を認めてくれなければ、おまえを殺してしまうぞ」といったとしたらどうでしょうか。それはいうまでもなく自己矛盾です。他人の生命を尊重することによってのみ、はじめて自分の基本的人権というものも生じてくるのだからです。しかしそれにもかかわらず、この種の考え方が個人的にも社会的にもしばしば行われているのではないでしょうか。少なくとも、自分の人権を守るためにはなにをしてもよいのだという考え方はよく行われているようです。】
岩崎武雄がいう自己矛盾も、基本的人権を否定すれば矛盾ではなくなる。権利とは強者が利益を得られる地位または資格と定義すれば良いだけだからである。
明治憲法では、実際に社会ダーウィニズムの思想から天賦人権を否定した。
カントは、理性的存在者としての人間は目的自体であり、いかなる場合にも、人間が目的自体であることを同時に考慮しないで、人間を手段としてのみ取り扱ってはならない、と主張したが、社会ダーウィニズムからだと、私自身の自己保存が目的の対象となるので人間が目的自体とならない、つまり基本的人権の否定に繋がるのである。
基本的人権を正当化する社会契約説(設立説)に対しては、契約という歴史的事実の不存在、「契約は守られなければならない」という前提の根拠、子孫拘束の根拠などに対し批判が向けられているので、他者(国民)の承認が重要になる社会契約説の根拠を前回のブログ記事で考えてみたらアクセスが激減した。まるで甘利氏のことを記事にした時みたいだ。(;゚д゚)
基本的人権は自然法の実定法化であり、ゆえに憲法は単なる法律ではない高次の法規範なのであるが、その基本的人権を否定する憲法を憲法と呼んで良いのだろうか?。基本的人権を否定することは悪法をも肯定することであり、悪法でも死を選ぶかそれとも服従を選ぶかを強要する国家は形式的法治国家と呼ぶべきものであり、実質的法治国家とは呼べない。※
アベ政治の改憲の目的は基本的人権を否定することにある。明治時代でも天賦人権論は自由民権運動の理論的支柱として機能したが、明治憲法により否定され、民衆の間にはほとんど定着できなかった…。現代日本においても稲田朋美のように「国民の生活が大事なんて政治はですね私は間違ってると思います」と基本的人権を否定する思想ばかりがテレビやネットで大々的に垂れ流され、基本的人権を肯定する思想は存在しないかのような見せ方をしているが、基本的人権を否定してそれに対応する義務が政治家には存在しないかのような欺瞞を暴力的に国民に押しつけて、国民をたいやきくんのような運命にしないでもらいたい。
P.S.積極的平和主義とは直接的暴力のみならずその原因となる間接的暴力(格差や貧困、差別など)を殺害された中村哲氏のように無くす行動つまり国民の生活を守ることをいうのであり、格差や貧困、差別などの間接的暴力を助長して、それに対する抵抗を直接的暴力で抑圧することではありません。
※cf.
日本の「人質司法」批判=ゴーン被告に「巨大圧力」―人権団体
HRWのロス代表は同日、ニューヨークの国連本部で記者会見し、保釈中に日本からレバノンに逃亡した日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告について「弁護するわけではない」と前置きしつつ、日本では容疑者の取り調べに弁護士が立ち会えず、被告は妻との接見も認められなかったと指摘。「日本の刑事司法制度が容疑者から自白を得るために課した巨大な圧力を物語っている」と述べた。
また、日本では容疑者の多くが自白を強要されているとして、「司法制度ではなく、自白(強要)制度だ」と非難した。