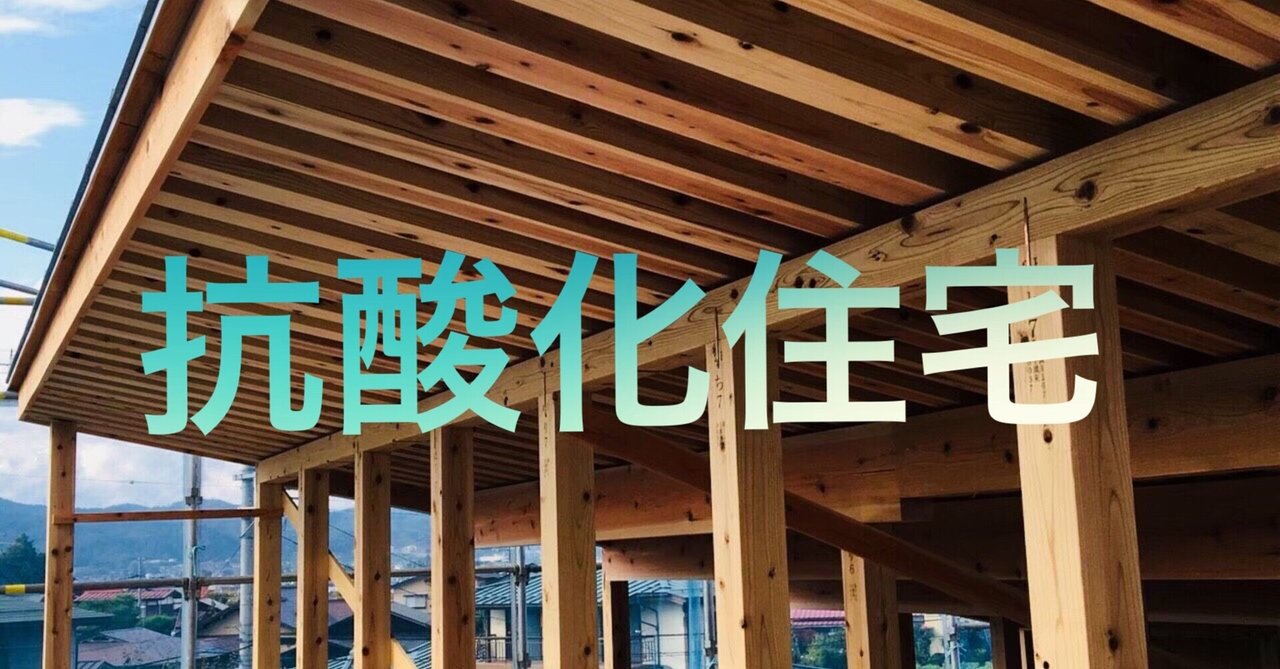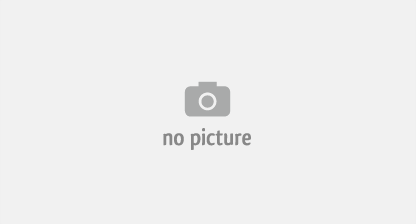建築の基礎知識を身につけるべく手に取った一冊。
さらっとしか読んでいないのですが……
私には難しすぎました。。
教養とするにはまだまだ及びません。。。
ですので、うすーい感想をお届けします!笑
▼ 『教養としての建築入門』をさらっと読んでみて
【坂牛卓(2023)『教養としての建築入門』、中公新書】
さらっと一周しか読んでいないのですが、印象に残った箇所をピックアップしてみます。
- 建築は、工学、美学、社会学などが織りなす、包括的な存在(まえがきより)
- 建築はキノコのようなもので、その土地の風土に根ざして生まれ、成長する(p.5)
- 建築は人が使うことを前提にした器(p.19)
- 単素材といえば、安藤忠雄の建築は典型(p.77)
- 建築の目的を遂行しようとすると一般的にはヒエラルキーが生まれる(p.132)
- 建築士の資格も「足の裏のご飯粒」と言われる。取らないと一人前と認められないが、取ったからといって誇れるものでもない。(pp.147-148)
ピックアップしてみて、「建築とは何か?」の答えを知りたがっていた自分に気づきました。。
理解がまだまだ足りませんが、答えの片鱗は見えてきたように思います。
建築はキノコ…この例えは私も使いたいですね。笑
#足の裏のご飯粒も
本書では、有名建築の紹介や設計のメカニズムにとどまらず、政治や経済とのかかわりまで網羅的に触れられています。
#建築が政治のプロパガンダと一体化
「人が見る建築」
「建築家が作る建築」
「社会に活きる建築」
の3つの側面から語られるのもおもしろいですね。
私は教育の分野から語ってみたいなと思いました、、
「参観者が観る教育」
「教師がつくる教育」
「社会に活きる教育」…
#教員免許も足の裏のご飯粒
マイホームは商品ではなく文化であるべきだと私は考えるのですが、筆者も同様のことを述べていたのは首がもげるほど共感したところです。
まさに建築は、「時間とともに人びとに愛され、その場所に欠かせない、文化的価値が醸造されるもの(p.220)」であって欲しいと思います。
【有料記事のお知らせ】
損しないマイホームの買い方について、約30,000文字で記事を書きました。マイホーム購入で損したくない方はどうぞ↓
【もっと詳しい健康と住まいのブログ】はコチラから↓