こんにちは!3Hメディソリューション株式会社 公式ブログ担当です!
今回も、みなさまの健康や医療に関する情報をお届けしてまいります。
さて、今回のテーマは多くの方にとって身近な問題である「生活習慣病」についてです。
日本人の死因の約半数を占める、がん・心臓病・脳卒中。これらは「生活習慣病」と呼ばれ、私たちの食生活や運動習慣、喫煙、飲酒といった日々の習慣が深く関わっています(遺伝的な要因なども影響します)。
生活習慣病の怖いところは、初期には自覚症状がほとんどないまま静かに進行し、気づいたときには深刻な状態になっているケースが多いことです。特にがんは、30年以上も日本人の死因第1位となっています。
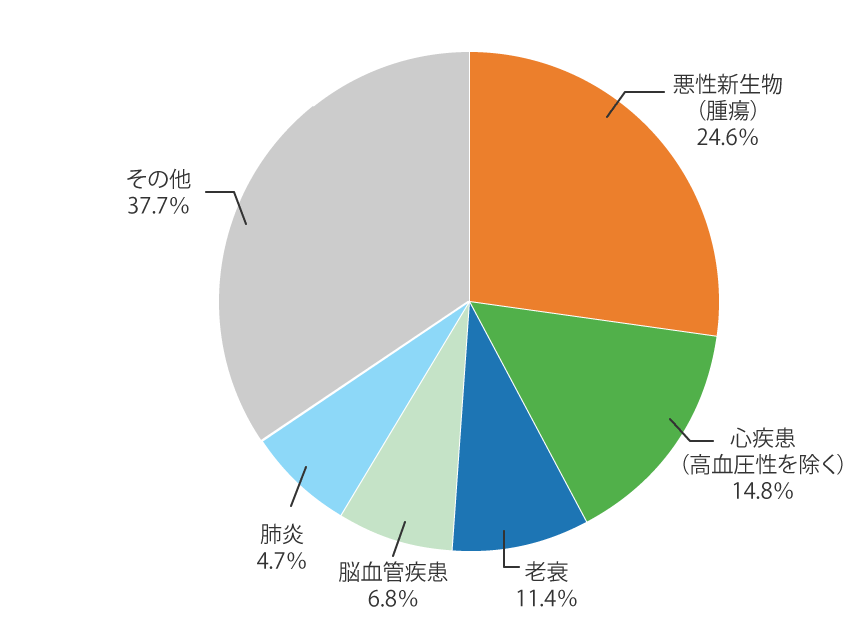
資料:厚生労働省「令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)」より政府広報室作成
また、心臓病や脳卒中の主な原因となる動脈硬化は、内臓脂肪型肥満に高血圧・高血糖・脂質異常症が組み合わさった「メタボリックシンドローム」の状態だと、急速に進行する危険性が高まります。40歳を過ぎると、メタボリックシンドロームやその予備群とされる方の割合は増加傾向にあります。
生活習慣病から身を守るカギは?
静かに進行する生活習慣病に対して、私たちができる最も重要な対策は「予防」と「早期発見」です。そのために不可欠なのが、定期的な健康診断やがん検診の受診です。
- 特定健診(メタボ健診)・特定保健指導
- 目的: 40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームのリスクを早期に発見し、生活習慣の改善をサポートします。
- メリット: 自身の健康状態を把握し、専門家から個別の改善アドバイス(保健指導)を受けられます。早期に生活習慣を見直すことで、病気の予防や健康状態の改善が期待できます。
「健康寿命」を延ばすために今日からできること
健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間「健康寿命」。これを延ばすには、日々の生活習慣の見直しが不可欠です。「1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後にクスリ」のポイントを、実践しやすい形で見ていきましょう。
【運動】まずは+10分、無理なく楽しく!
運動は特別なことである必要はありません。
- 目標: まずは「今より10分多く体を動かす」意識から。通勤で歩く距離を少し伸ばす、階段を使うなど、日常生活の中で活動量を増やしましょう。慣れてきたら、1日合計60分程度の活動が理想です。
- おすすめ: ウォーキング、軽いジョギング、サイクリングなどの有酸素運動や、自宅でできる軽い筋トレ・ストレッチが続けやすいでしょう。
- 継続のコツ: 家族や友人と一緒に、楽しみながら、体調に合わせて休みつつ、長く続けることが大切です。
【食事】バランスを意識し、"少し変える"習慣を
毎日の食事が体を作ります。完璧でなくてOK、少しずつ意識を変えていきましょう。
- 基本バランス: ごはん等の「主食」、肉・魚・大豆製品等の「主菜」、野菜・きのこ・海藻等の「副菜」を揃えることを意識しましょう。
- 野菜をプラス: いつもの食事にサラダや具だくさんスープなどを足して、野菜摂取量を増やしましょう。(1日350g目標)
- 塩分・糖分・脂質は控えめに: 漬物や加工食品、甘いお菓子やジュース、揚げ物や脂身の多い肉は摂りすぎに注意。出汁や香辛料を活用したり、良質な油(魚、オリーブオイル等)を選んだりする工夫を。
- 時間と量: 1日3食、なるべく規則正しく。よく噛んで腹八分目。夜遅い時間の食事は避けましょう。
【禁煙】サポートを活用し、健康な未来を
禁煙に「遅すぎる」ことはありません。病気リスク低減はもちろん、様々なメリットがあります。
- 禁煙サポート: 意志の力だけでなく、禁煙外来(保険適用の場合あり)や市販の禁煙補助薬(ニコチンパッチ等)を活用するのも有効です。薬剤師や医師に相談してみましょう。
- 周りの協力: 家族や職場に宣言し、応援してもらうことも力になります。
【薬】医師の指示を守り、自己判断しない
高血圧や糖尿病などで治療中の方は、処方された薬を正しく服用することが重要です。
- 生活習慣改善と併せて: 薬と生活改善は治療の両輪です。
- 自己判断はNG: 薬の量や服用を勝手に変えず、必ず医師に相談しましょう。
まとめ
「まだ元気だから大丈夫」と思わず、ご自身の健康状態を知るために、まずは定期的な健診・検診を受けてみませんか?そして、できることから少しずつ、健康的な生活習慣を始めてみましょう。
※本内容はがん情報サイト「オンコロ」をもとにAIが記事を作成しています。
出典元の記事は
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201402/1.htmlです。