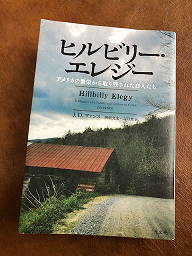1月20日、アメリカ大統領の就任式が行われ、バイデン新大統領がアメリカの新しいリーダーになった。トランプ前大統領は慣例を破り、式典の会場には姿を見せなかった。
「メキシコとの国境に壁を作る」に始まって、「支持者に対する連邦議会議事堂乱入の扇動(本人は否定)」まで、この4年間、トランプ前大統領は、文字通り、やりたい放題にやってきたように思う。そして、この間、私はずっと、「何故、この人が大統領に選ばれたのだろう」と疑問を持ち続けてきた。
答はいくつもあると思う。その一つを明らかにしてくれる映画が、『ヒルビリー・エレジー ー郷愁の哀歌ー』である。それは、この物語が、トランプに未来を託さざるを得なかった地域と、そこに暮らす人々の苦しみを描いているからである。
<ヒルビリーとは>
「ヒルビリー」。映画の内容に入る前に、まず、最近、時々耳にするようになったこの言葉を説明しようと思う。
映画には、J.D.ヴァンス『ヒルビリー・エレジー アメリカの繁栄から取り残された白人たち』という原作があって、この本の「はじめに」でヴァンスは自らについてこう書いている。
「私は白人にはちがいないが、自分がアメリカ北東部のいわゆる「WASP(ホワイト・アングロサクソン・プロテスタント)」に属する人間だと思ったことはない。そのかわりに、「スコッツ=アイリッシュ」の家系に属し、大学を卒業せずに労働者階層の一員として働く白人アメリカ人のひとりだと見なしている。
そうした人たちにとって、貧困は、代々伝わる伝統といえる。先祖は南部の奴隷経済時代に日雇い労働者として働き、その後はシェアクロッパー(物納小作人)、続いて炭鉱労働者になった。近年では、機械工や工場労働者として生計を立てている。
アメリカ社会では、彼らは「ヒルビリー(田舎者)」「レッドネック(首すじが赤く日焼けした労働者)」「ホワイト・トラッシュ(白いゴミ)」と呼ばれている。」
その住む場所は、南はアラバマ州やジョージア州から、北はオハイオ州やニューヨーク州の一部にかけてのアパラチア山脈周辺の広大な地域(グレーター・アパラチア)で、ヴァンスは「ケンタッキー州東部の丘陵地帯出身の私の家族は、自らを「ヒルビリー」と呼んでいる。」と書いている。
「ヒルビリー」の祖母と母、そして著者。3世代にわたる家族の愛憎を描いた映画が『ヒルビリー・エレジー ー郷愁の哀歌ー』である。
<あらすじ>
東部の名門、イェール大学のロースクールで学ぶ主人公のJ.D.(ガブリエル・バッソ)の携帯に姉のリンジー(ヘイリー・ベネット)から電話がかかて来た。「ママがヘロインの過剰摂取で入院した。帰ってきてほしい。」
電話を切ったJ.D.は、故郷のオハイオ州ミドルタウンに車を走らせ、母親を引き受けてくれる施設を姉と一緒に探すことになった。ミドルタウンでのJ.D.の一日を縦軸に、そこに少年時代の思い出を絡ませながら物語は進んでいく。
母親のベブ(エイミー・アダムス)は、高校時代の成績は優秀だったが経済的に恵まれていなかったため大学には行けず、看護師になって地元の病院で働いていた。両親の激しいいさかいを幼いころから見続けてきたこともあって精神的に不安定で、結婚と離婚を繰り返し、ドラッグも常用していた。
車を運転中に言い争いになり、息子から「ビッチ」と呼ばれたことに腹を立て、車から逃げるJ.D.を追いかけて危うく警察に捕まりそうになったり、ジャンキーであることを隠すために息子から尿をもらったり、患者に処方された薬を飲んでハイな気分になり、病院の中をローラースケートで走り回って解雇されたり。J.D.も、そんな母親から離れて暮らしたいと思うようになった。
少年時代のJ.D.を支えたのが、祖母のボニー(グレン・クローズ)だった。祖母は元々ケンタッキー州のジャクソンに住んでいたが、13歳の時に妊娠して、隣接するオハイオ州のミドルタウンに相手の男と逃げるように移ってきた。酔って帰ってきた夫にガソリンをかけて火をつけるような激しい気性の持ち主ではあるが、愛情豊かな女性で、孫のJ.D.とリンジーを心から愛していた。
夫に先立たれた後、ボニーはJ.D.を娘の元から引きとることになった。口やかましい祖母に反抗するJ.D.だったが、「自分には時間がない。家族を見るのはおまえだけなんだ。」と言われ、アルバイトで家計を助けながら勉強にも精を出すようになった。
祖母のおかげで立ち直ったJ.Dは軍を除隊した後、オハイオ州立大学を経てイェール大学のロースクール入学し、法律家を目指すことになった。キャンパスではウシャ(フリーダ・ピント)というガールフレンドもでき、未来への道がようやく開かれようとしていた。そんな矢先、リンジーからかかってきた電話が、母親がヘロインの過剰摂取で入院した、という知らせだった。
ようやく見つけた施設への入所を母親が嫌がったため、J.Dは母親をモーテルに連れていく。しかし、息子が食べるものを買いに行ったすきに再びヘロインを注射しようとし、それを見つけたJ.Dが母親から注射器を奪い取った。
J.Dは、翌日、就職試験の面接を受けることになっていたため、リンジーと交代してすぐに大学に戻らなければならなかった。身勝手で弱い母親にはじめは憤るが、やがて自分が守らなければ、という思いがこみ上げてくる。そんなJ.Dの気持ちが通じたのか、母親は穏やかな表情で息子を部屋から送り出した。ちょうどその時、リンジーが車で到着し、二人は母親への愛情とお互いへのいたわりの気持ちを確かめるように、しっかりと抱きしめあった。
最初にことわっておかなければいけないのは、私は10代のころから活字や映像・音楽を通してアメリカの政治や社会・文化に親しんできたが、けっしてアメリカ政治の専門家ではない、ということである。以下の文章も、アメリカを半世紀近くにわたってウォッチしてきた一人の素人の考えとして読んでいただけたら幸いである。
アメリカの地域の一つとして、「ラストベルト」という言葉を聞いた方も多いと思う。「Rust Belt」=「さび付いた一帯」といったような意味で、閉鎖された自動車工場や鉄工所などがさびた鉄骨をさらし、それに象徴されるかのように街全体もかつての活気を失った地域のことである。州をあげるとペンシルベニアやオハイオ、ミシガンなどで、『ヒルビリー・エレジー』の舞台となったケンタッキー州やオハイオ州を含むグレート・アパラチアと一部が重なっている。映画でも、工場の鉄骨がミドルタウンの衰退を象徴するかのように繰り返し登場していた。
アメリカには民主党と共和党の2大政党があって、トランプ以前は、民主党はブルーカラーの労働者のための政党、共和党はニューヨークのウォール街に代表されるようなホワイトカラーのための政党という側面が強かった。しかし、民主党が少数民族や若者向けの政策に力を入れるようになったため、ブルーカラーの多いヒルビリーたちは、しだいに民主党離れを起こし、一方で、共和党もホワイトカラーのための政党であり続けたため、彼らは、しだいに忘れられた存在になっていった。これに、鉄や石炭を使った重厚長大産業からIT産業へのアメリカ経済の転換が重なり、グレーター・アパラチア、とりわけラストベルトにある街は、どんどんとさびれていったのである。
「トランプ 5:2 ヒラリー」
これは2016年の大統領選挙のラストベルト各州での結果である。ヒラリー・クリントンは大都市ニューヨーク・シティとシカゴのあるニューヨーク州とイリノイ州では勝ったが、ペンシルベニア、オハイオ、ミシガン、インディアナ、ウィスコンシンの各州ではトランプが勝利した。映画のもう一つの舞台となったケンタッキー州でも、トランプがヒラリーを破った。民主党に裏切られ、共和党にも相手にされないヒルビリーたちに精力的に働きかけた結果であった。
トランプは、2016年の大統領選挙期間中、ラストベルトを繰り返し遊説に訪れ、「Make America Great Again=アメリカを再び偉大に」のスローガンのもと、ヒルビリーたちの心をつかむのに成功した。ヒルビリーの側にも、トランプを受け入れる土壌=メンタリティーがあったからだと思う。
ヒルビリーの気質をよく表しているのが、『ヒルビリー・エレジー』に登場する母親であろう。根は子供思いの愛すべき母親なのだが、幼いころからの家庭環境もあって自分の感情をコントロールすることができない。うまくいかないことがあると、その原因を他人のせいにして、あげくの果てはドラッグに逃げ込んでしまう、などなど。粗野と言われてもしょうがないような母親である。
粗野と言うと、トランプ前大統領も相当なものだと思う。前大統領は、一応、東部の名門大学を卒業した不動産王となっているが(一応と書いたのは、大学への入学疑惑や、実は借金まみれ、といった疑惑も取りざたされているため)、女性との性的関係について露骨に下品な言葉で語っている過去の会話の映像が公開されるなど、その素行は決して褒められたものではない。2016年の大統領選挙で、ヒルビリーたちはエリート臭のするヒラリーではなくトランプに、同質なものを感じ取ったのではないだろうか。
そのヒルビリーたちも、好き好んで粗野になったわけではない。産業構造の変化による地域の衰退とそこから生まれる貧困。それに有効な手を打つことができない政治家。こうした問題がヒルビリーたちの心をすさませ、共和党候補とはいえ、既存の政治家とは一線を画したトランプに自分たちの未来を託したのだと思う。あたかも救世主のように。
今のアメリカが抱える矛盾がラストベルトを生み出し、そこに暮らすヒルビリーたちが、トランプを大統領に選び、支えたのである。
※今回の選挙では、前回トランプが勝ったラストベルト5州のうち、ペンシルベニアなど3つの州でバイデンが勝利した。この結果、ラストベルト全体では、「トランプ 2:5 バイデン」となり、共和党と民主党の勝敗が前回から完全に逆転した。これが、バイデンを大統領に押し上げる大きな要因になった。ケンタッキー州は、前回に引き続き今回もトランプが勝利した。
<2人の女優の圧巻の演技>
映画を観る者に強烈な印象を与えるのが、母親役のエイミー・アダムスと祖母役のグレン・クローズの圧巻の演技である。
エイミー・アダムス
これまでに私が見た彼女の映画は、「人生の特等席」と「メッセージ」。「人生の特等席」では弁護士の役(父親のMLBの老スカウトマン役はクリント・イーストウッド)。「メッセージ」では言語学者の役を演じていたので、個人的には知的な職業を持つ女性の役が似合う女優というイメージが強かった。それが一転して、ヒルビリーの母親役である。激しい言葉や行動の裏側にある弱さ・脆さが、見る側にしっかりと伝わってくる優れた演技である。
グレン・クローズ
最初、映画を観た時、祖母のボニーを演じている女優が誰かわからかなかったが、グレン・クローズと知って、驚くと同時に納得もした。
彼女の演技で今でも鮮明に覚えているのは、『危険な情事』でマイケル・ダグラス演じる男にバスタブに沈められて死んだと思ったところ、再び起き上がって男を襲ったシーンである。これは本当に怖かった。その後も、『101』で101匹わんちゃんをつけ狙う、毛皮大好き女のクルエラを演じるなど、癖のある役をこなす演技派女優である。
彼女はアカデミー賞に7回もノミネートされているが、一度も受賞していない。今年のアカデミー賞のノミネートはまだ発表されていないが、『ヒルビリー・エレジー』の演技で、早くも助演女優賞の候補として名前があがっている。
<『華氏119』>
『ヒルビリー・エレジー』は、3世代にわたる家族の愛憎を物語の中心に据えているため、原作に比べると社会問題を正面から取り上げていない面がある。そうした点に不満を持つ方にぜひお勧めしたいのが、『ボウリング・フォー・コロンバイン』や『華氏911』で知られるマイケル・ムーア監督の『華氏119』である。
ムーア監督自身も、ラストベルトの一つであるミシガン州の出身で、何故、トランプ大統領が誕生したのかを、ラストベルトが抱える問題にも触れながら描いている。
ちなみに『華氏119』の119は、2016年にトランプが大統領選挙の勝利を宣言した11月9日のことを指している。
<バイデン新大統領のアメリカ>
それから4年余り。アメリカ国民は次の大統領にバイデンを選び、バイデン新大統領のアメリカがスタートした。
トランプ前大統領の4年間でアメリカはそれまで以上に社会が分断し、とりわけ熱烈な支持者たちは、前大統領がそうであったように、人々を敵と味方に分け、異なる意見の持ち主を徹底的に攻撃することでカタルシスを感じてきた。バイデン新大統領は、大統領就任演説の中で、「人々に団結を呼びかけ、この国を一つにすることに私の全霊を注ぐ」「私に投票しなかった人を含め、全ての国民のために戦う大統領になる」と述べて、国民の融和を強調した。
そのためにバイデン新大統領は何をしなければいけないのか。アメリカ再生のための重い課題として、新大統領は、『ヒルビリー・エレジー』が描いた社会や人々の苦しみに真正面から向き合い、これを解決する途を探さなければならないのである。
『ヒルビリー・エレジー ー郷愁の哀歌ー』
ロン・ハワード監督の2020年のアメリカ映画
ハワード監督は、2001年の『ビューティフル・マインド』でアカデミー監督賞を受賞。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
<参考までに>
J.D.ヴァンス『ヒルビリー・エレジー アメリカの繁栄から取り残された白人たち』(光文社)以外に私が読んだトランプ関連の本は以下の通りです。
・マイケル・ウォルフ『炎と怒り トランプ政権の内幕』 早川書房
・ボブ・ウッドワード『恐怖の男 トランプ政権の真実』 日本経済新聞出版社
・メアリー・トランプ『政界で最も危険な男 「トランプ家の暗部」を姪が告発』 小学館
・渡辺由佳里『トランプがはじめた21世紀の南北戦争』 晶文社
・金成隆一『ルポ トランプ王国 -もう一つのアメリカを行く 』 岩波新書
・吉見俊哉『トランプのアメリカに住む』 岩波新書
・渡辺 靖『白人ナショナリズム アメリカを揺るがす「文化的反動」』 中公新書
このうち一番のお勧めは『トランプがはじめた21世紀の南北戦争』です。渡辺さんは、2016年の大統領選挙で、トランプやヒラリー、それに民主党のもう一人の有力候補だったバーニー・サンダースの選挙キャンペーンを取材し、アメリカが抱える深刻な対立をとても分かりやすく説明してくれています。ちなみに彼女は、『ヒルビリー・エレジー アメリカの繁栄から取り残された白人たち』の巻末の解説も書かれています。
次は、今回とはがらり変わって『LA LA LAND ラ・ラ・ランド』について書いてみたいと思います。
ここ数年で見た映画の中では、最も好きな作品です。