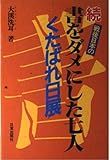お習字、音楽、お習字、音楽、憎悪する人間の悪口、音楽、スピリチュアルな事柄、音楽、お習字……
大変無礼ですが、これが拝金主義のなりの果てではないでしょうか。
なんだかこのリズムがパターン化されているような気がして、自身のことがつまらない、引き出しが少ない人間のようで苦笑して哀しみがこみ上げてきますがそれでもブログを続けて参ります。
さて、今日は日付けが既に変わりまして、お習字のことです。
2日前、追加でダメな手本を差し上げようと書いたものですが、案外気分良く書けたので忘備録として貼り付けておきたくなりましたので載せておきます。
昨日社内で出勤して直ぐに撮りました。
拙いながらも気分良く書けたものは、なにも恥じることはなく個人にとっての「蘭亭叙」になります(学生時分、先生がよく書けたものを『これはあんたの蘭亭じゃ』といっていたのが思い出されます。1回だけいわれただけですが)。ですから、自己満足ですが一応貼り付けておきました。
さて、次に気になった映像を紹介します。
村上三島先生門下の中で現在恐らく1番地位、名誉共におありではないかと思われる杭迫柏樹(くいせこはくじゅ)先生の「蘭亭叙」の臨書……。
すみません、少し正直違うような気がしました。違和感を感じました。
もっと線はふくよかであり、線の太い細いがあるような気がしますし、運筆も速くする部分があるのではないか、と八柱第1本を思い浮かべながら思いました。
杭迫先生の臨書された文字を見て、ああ蘭亭だ、という薫りがしませんでした。
ユーチューブのコメントに、有力な先生方の師風継承が、古典の解釈が歪められているとあり全く同感です。
同じくコメントには成瀬映山先生の文化庁の揮毫を見てショックを受けた、とありましたが、少し古典的な意匠を凝らして、それも青山杉雨先生の目を通して揮毫されたかのような感じがしますが果たして……。
大変無礼ですが、これが拝金主義のなりの果てではないでしょうか。
次に、手島右卿先生門下の仲川恭司先生の「鄭羲下碑」です。
当たり前ですが、手島先生と同じスタイルで臨書されています。贔屓しているわけではありませんが、鄭道昭の伸びやかな書が想起されるのは確かです。
毎日系の先生方がどう、讀賣系の先生方がどう、ということはありません。スタイルが各々あります。
その中で色々あるでしょう。複雑な事情が。
個人はこの大渓洗耳先生の意見に賛成します。以前拝借して読みましたが、胸がすく思いがいたしました。
書道界が全くの出来レースに近いことが横行していることを知り、無駄に真面目で不器用で孤独好きな個人には入ってはいけない世界だと思い知らされました。
ユーチューブで杭迫柏樹先生の「蘭亭叙」の臨書を見て、書をダメにした、といわれる弟子の先生方の作品を見てすみません、雨後の筍のような様相を感じてしまいました。
有名になる、書を書いて稼ぐということは……どういうことでしょうか。
安住した世界に入ると人間は努力を怠り、贅沢に奔り傲慢になってしまうのでしょうか。
そこで個人が立ち上がる! ということはしません。自身の腕の問題ですし、名前を売ろうとは全くもって考えられませんし、書道ブログにしようとは思いません。
側から色々見ているのがよいです……。