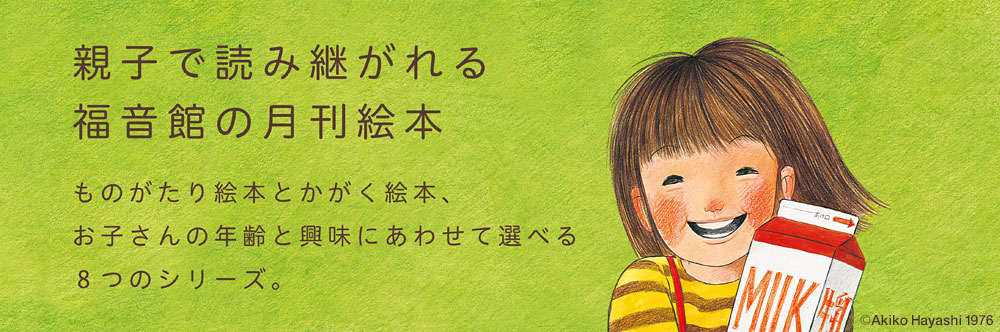足を運んで下さりありがとうございます
年長・年少・2歳の男の子三兄弟と共にやり抜く力を育てているmimisenseiです![]()
![]()
本日ご紹介しますのは、こちらの書籍
小3までに育てたい算数脳(2005年)
著者 高濱正伸
第1章
十歳で将来が決まってしまう⁉︎
第2章
小3までに育てたい「算数脳」
第3章
すべてを決める!
小3までの育て方・遊び方
著者 高濱正伸さんについて
***
この本は、算数・数学の「思考力」に焦点を当てた本です。
「補助線を引いたあとの、どんなに立派な解法を見せられても、納得できない。引いたあとの説明はできるが、それではほとんど価値がない。その一本が自力で思い浮かばないからこそ、困っている。ところが、補助線が思い浮かぶ秘訣を教えてくれる先生も本もないではないか」。
学生時代のそんな素朴な思いが、原点にあります。
とはじまります。
その、「超えられない壁」には2つの能力が関係してくる。
①「見える力」
=補助線が浮かぶ能力、空間認識力、試行錯誤力(脳の1つの処理能力)
●図形センス
●空間把握力
●試行錯誤力
●発見力 (p110)
②「詰める力」
●論理性
●要約力
●精読力
●意志力 (p110)
→悔し泣きするくらいら負けず嫌い。
「どうしても自分で解きたい、自分で考えたい」やり遂げる喜びを知っている(p.109)→GRIT?
***
「見える力」と「詰める力」は、
現場感覚では、小3までが勝負。
では、どのように過ごせばいいのか?
その答えは、
「家庭・遊び」の中にある。
外遊び
→夢中になって遊ぶ中で知性は育つ
イメージ力は外遊びでこそ伸びる
「=実体験」
五感を刺激する
異年齢で遊ぶ
危険を「本能」で察知する能力
家庭に関しては、親のあり方、親たちのNGワード行動など記載されています。
***
終わりの方では、
それぞれの力を伸ばせるゲームが具体的に記載されています。
ただ、1つ疑問が浮かびました。
百ます計算などに対して、知能数や集中力が上がったか、再現性のあるデータなのかわからないという記載があります。
計算は、中学2年生までに誰でもできるようになるものだと。
百ます計算は、中学生になっても四則演算ができない子がやればいいのでは?と述べられていました。
ということは、計算はやはり誰でもできるようになるわけではないのでは?
一方で、企業データを参考にしてはいるものの、「見える力」と「詰める力」が小3までに決まるというのは、現場感覚とのこと。この部分がエビデンスなどに基づいているとより説得力があったのかなぁ……。
先日ご紹介しましたこちらでは
外遊びや身体を動かすことを大切にすること、読み書き計算は一生モノの力だから低学年のうちからきちんと力をつけるべきだと述べられ、それぞれを大切にすべきだと。
| 東大ドクターが教える 塾に行かなくても勉強ができる子の習慣 1,404円 Amazon |
***
最後に、
〝1番大切なことは、主体性です。
自分でやりたいと思って自分でやってみて、我を忘れて熱中し、失敗したら自分で何故だろうと考え、自分で教訓を引き出し、成功したら間違いない自分の喜びとして満喫する。〟
と述べられています。
まさに、藤井聡太さんが歩んできた人生に通じるものがあるのでは?
と感じました。
かがくのとも こどものとも(福音館書店)定期購読してます♡
全ての学問の礎国語力育成に ブンブンどりむ
子どもの未来は「国語力」で決まる!
無料体験キットプレゼント中! ![]()
![]() ブンブンどりむの記事→★★★
ブンブンどりむの記事→★★★
![]() オススメのオンライン英会話
オススメのオンライン英会話
こども〜大人まで
3太郎の大好きな先生がいるよ