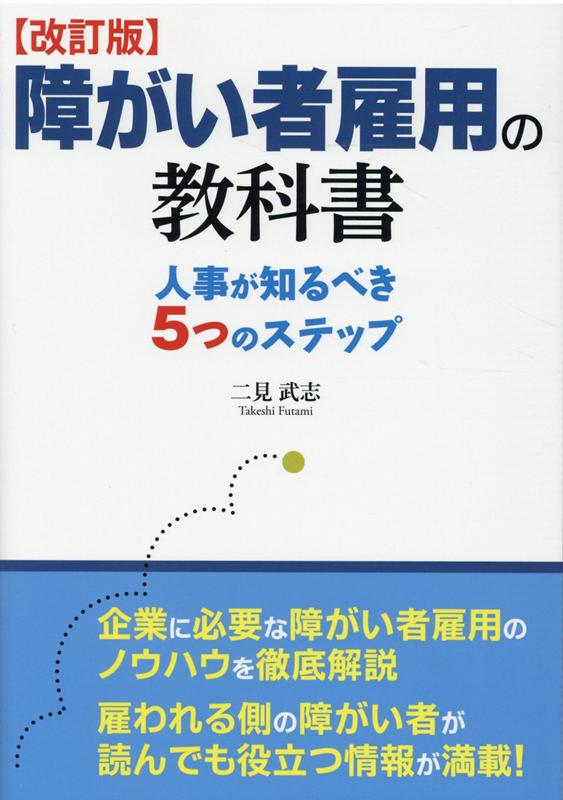精神障がい者雇用で求める人材と定着率について調べました!
今年の夏迄に、A型作業所か企業の障害者枠でのパートを目指しています。
「障かい者雇用」の本を読み学びました。
情報共有とし、列記させて頂きます。
是非、お付き合い下さい。
〈ご訪問いただきありがとうございます〉
35歳・うつ病・線維筋痛症の無職です。
180時間の残業、人間関係でうつ病を発症
精神科入院、休職しルート営業を退職
会社員退職→精神科デイケア卒業→地域活動支援センター(現在)で体調・体力をつけ、
就労継続支援A型へ向けての準備をします。
引用元:二見武志さんの本「障がい者雇用の教科書」内に記載がされておりました。
著者:二見武志
書名:障がい者雇用の教科書
発行所:ケイズプロダクション
出版年:2020年9月20日 改訂第1刷
一部引用し、抜粋「」内
【障がい者雇用の年齢別実態を見てみよう】
「●精神障がい者は30代後半~50代前半が約6割
精神障がいの発症年齢は10~30代が最も多く、精神障がい者全体の60%以上といわれています。
就業実態で見てみると40代が約3割と最も多いのが特徴です。
また、新規就職者数の伸び率が最も高いのも精神障がい者です。
筆者は、企業の人事担当者から「若くて電話応対とぽパソコンができる人の紹介をお願いします」などという具体的な人材についてのオーダーを受けることがあります。
そのような場合は「そんな人は、まずいません」と即答します。
企業が求める「即戦力=若くて仕事がバリバリできる人」というのは、とこの企業だって欲しいに決まっています。
バリバリ働ける障がい者は現在、引く手あまたです。
このような方は、簡単に就職が決まるどころか、いろいろな会社からすぐに声がかかる状況だということを心得ておいてください。」
●精神科の医師に聞いた!
以前、私は、精神科の主治医に、障害者雇用において「どんな人が求められますか?」と聞きました。
医師の回答
→「まず、毎日通勤出来る人。メンタル疾患の方は、体調に波があり、来てくれないと、仕事を任せられない。次に、印象が良い人を取る」ということでした。
●本書の求められる人材は?
「バリバリ働ける障がい者は現在、引く手あまた」ということ。
↓
私の解釈としては、妥協し最低限、毎日安定して通勤が必須と思います。
なぜ妥協かというと、
※そもそも、バリバリ働けたら精神疾患になっていません。無理して頑張らない方がいいですね😭
因み精神疾患になる要因について記載↓
●障害者の就職・転職サービスにおける求める人材は?
障害者 雇用・採用・求人のアットジーピーより提供↓「」内引用。一部抜粋。
精神障害者の選考で見るべきポイント4つ
ポイントを赤字にさせていただきました。
①自分の障害をよく理解しているか
「企業が精神障害のある方に求めるものとしては、職業能力に加えて、安定して働くことができるかどうかが重要となります。精神障害のある方が安定して働くためには、自分の障害について理解した上で、肯定的に受け入れて行動できる能力や態度を持っていることが必要です。」
→自身の障害の理解です。
企業からしたら、精神の障害枠にとって、自己理解は安定して毎日出勤する為に必要な事です。
▼メンタル不調防止・安定して働く為の対応策
〈私の場合〉
・土日の過活動。外出を抑える。
・ネガティブ思考なので、考えすぎない
・メンタル不調にならない様な環境で勤務する
(支援者との相性がいい。雰囲気の良い)
・勤務地が近い職場を選ぶ(通勤の負担減)
・労働時間が短い職場を選ぶ(週20時間勤務)
・ダブルタスクが苦手なので、シングルタスクの仕事を選ぶ。
・体調の相談が出来る人がいる職場を選ぶ。
・急な不調は、頓服を服用し乗り越える。
・精密な作業が苦手なので、避ける。
・パソコンの前で設計者のように何時間も席にいれないので、避ける。
・クリエイティブがない、ルーティンワークを選ぶ。
・人間関係の良い職場を選ぶ。
・ストレスになる仕事内容や職場を避ける。
②自分の障害を理解し、受容できているか
「うつ病や不安障害、気分障害をネガティブな感情や思考に陥りがちです。そのような状態になると、精神症状だけでなく、不眠や食欲不振などさまざまな身体症状も現れるため、働くことは困難になります。手帳を持つ精神障害者でも、心身の状態が安定している人のほうが継続して働けるケースが多いため、自分の障害を理解し、かつ受容できている人を選ぶと良いでしょう。」
→こちらも、自身の障害の理解です。
③他者とコミュニケーションがとれ、協力して仕事ができるか
「精神障害者が職場で安定的に働くには、周囲の理解や配慮が必要ですが、精神障害の症状は人それぞれ異なるため、周囲の人が完全に理解するのは非常に困難です。周囲に理解してもらうためには、まずは自分自身が障害について理解することが必要です。そして対処法を周囲に説明して、業務を遂行する上で必要な配慮を相談することが大切です。採用選考では、自身の障害について客観的に説明できるコミュニケーションスキルがあり、また周囲の人と協力して仕事ができそうかをチェックしましょう。」
→企業で働く「強調性」が必要です。
4、自分のスキルを理解し、自信を持っているか
「一般の選考でも重要となるのが、自己分析がしっかりとできていて、自身の長所や短所、得意なこと、スキルなどについて自己理解できていることです。これは精神障害のある方についても当てはまっていて、自分のスキルについて理解していない人は、入社しても十分に能力を発揮することができません。自身のスキルについて自信を持って業務を遂行できることが重要となります。」
→自分の長所や短所、得意なこと、スキルの明確化
〈私の場合〉
短所、
・早とちり。
・ダブルタスクが苦手。
長所、
・早とちり⇒行動力!
・企業経験!(言えるかわかりませんが)
①毎日安定して通勤できる人
②その人の印象(清潔感など)
③自分の障害について理解した上で、肯定的に受け入れて行動できる人
④心身の状態が安定している人
⑤自身の障害について客観的に説明できるコミュニケーションスキルがあり、また周囲の人と協力して仕事できる人
⑥自己分析がしっかりとできていて、自身の長所や短所、得意なこと、スキルなどについて自己理解できている人
●障がい別の勤続年数は?
本書より、
・身体障がい者10年2か月
・知的障がい者7年5か月
・発達障がい者3年4か月
・精神障がい者3年2か月
上記から、精神障害の平均勤続年数は
「3年2か月」
と1番、障害別の中で最も短いです…。
●離職率と仕事を継続する上で必要なことは?
株式会社エスプールプラス様より提供。
●就職1年後の定着率は?
↓

1年後の精神障害は定着率は、
勤続年数に比例し、一番低い
「49.3%」
半分は辞めてしまうのが現実!
離職の原因は↓
仕事を続けるために必要な事↓

〈仕事を続ける上で個人で出来る事は?〉
①調子が悪い時の意思表示。
②短時間労働の相談。
③体調管理。
※
わたしは、前職で耐えて、上司に言わずギブアップしました。
他人軸で生きてしまい、自分の事は後回し。
そこで「精神崩壊」。
メンタル疾患になってしまった方々は、自分優先で言うべき事は、言って「自己中」ぐらいがいいのかなと思います。我慢は続きません。
その上で結果が出ないのは仕方がないと思います。
求める人材像に「バリバリ働ける障がい者は現在、引く手あまた」という事は事実!
●以下を念頭に就活します!
①毎日安定して通勤出来るよう体力をつける
②その人の印象(清潔感をだす)
③自分の障害を理解する
④心身の状態を安定させる
⑤周囲の人と協力して仕事出来るよう心構え
⑥自身の長所や短所、得意、スキルを明確にする
⑦障害(体調)を相談できる人がいる職場を選ぶ
⑧短時間勤務からできる職場を選ぶ
⑨勤務地が近い職場を選ぶ。
⑩シングルタスクな仕事を選ぶ
⑪精密な作業が苦手なので避ける
⑫パソコンの前で設計者のように何時間も席にいれない為、身体を動かす仕事も選ぶ
⑬クリエイティブがない、ルーティンワークを選ぶ
⑭人間関係の良い職場を選ぶ
⑮ストレスになる仕事内容や職場を避ける
改めて、自分に無理のない働き方を
選択した方が良いと思いました。
わたしは現在、
「勤務地が近く」「利用料なし」「週20時間のA型作業所」で働ける所を検討しています。
※
今回「求める人材」と「定着率の低さ」がわかりました。
↓
精神疾患の定着率の低さから、ワガママなぐらいな、自己理解をして、出来ることや無理をしない範囲を目指す!
求める人材に無理に近づけても「根性」では続きません。
自分に合う自己理解をして、進めるしかないと思います。
今回、とても学びになりました。
そして、一度に鬱になり、精神疾患の再起は困難である事を示した現実も知れ、良い機会になりました。
注意していきたいと思います。
もしも、どなたかの参考になれましたら幸いです。