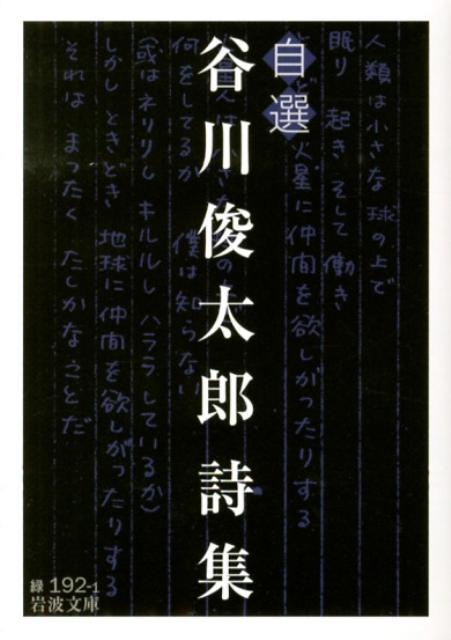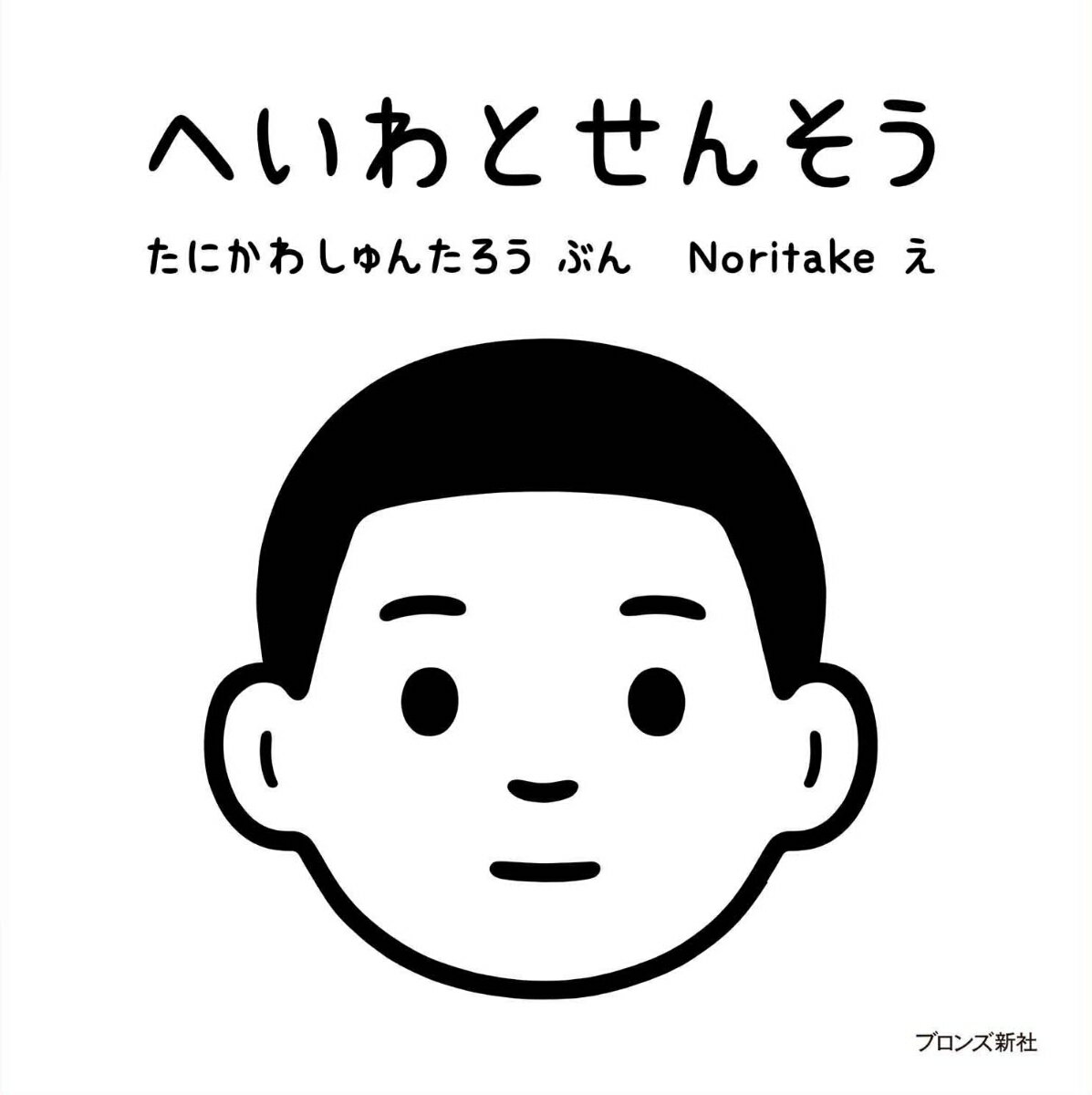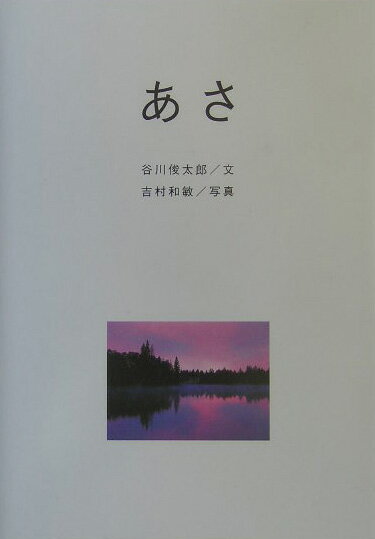おはようございます。いつもブログを読んでいただきありがとうございます😊
最近、谷川俊太郎さんの詩にどっぷりハマっています。先日、たまたま拝見したBS東京で放送された「あの本、読みました?詩人・谷川俊太郎特集!」という鈴木保奈美さんの番組で、俵万智さんや高橋源一郎さんが語る秘話を聞いて、あらためてその魅力に引き込まれてしまいました✨。
そこで今回は、お子さんもきっとご存知の「朝のリレー」という詩について、中学受験と絡めながら、そのすごさを考える記事を書いてみたいと思います。
「朝のリレー」 - 谷川俊太郎 -
カムチャツカの若者がきりんの夢を見ているとき
メキシコの娘は朝もやの中でバスを待っている
ニューヨークの少女がほほえみながら寝返りをうつとき
ローマの少年は柱頭を染める朝陽にウインクする
この地球ではいつもどこかで朝がはじまっている
ぼくらは朝をリレーするのだ
経度から経度へと
そうしていわば交替で地球を守る
眠る前のひととき耳をすますと
どこか遠くで目覚時計のベルが鳴っている
それはあなたの送った朝を
誰かがしっかりと受けとめた証拠なのだ
谷川俊太郎「朝のリレー」のここがすごい!
お子さんが「スイミー」と並んで知っているという方も多いかもしれませんね。この詩がなぜこんなにも心に響くのか、その魅力は大きく3つのポイントにあります。
1. 壮大なスケールと個人的な視点の融合
この詩は、地球儀を回すように、遠い国の「カムチャツカの若者」や「メキシコの娘」から始まります。世界のあちこちで繰り広げられる朝の情景を、次々と描いていきます。
ニューヨークの少女がほほえみながら寝返りをうつとき
ローマの少年は柱頭を染める朝陽にウインクする
といったように、具体的な情景が目に浮かぶようです。
そして、その光のバトンは「ぼくら」に渡されます。
この地球ではいつもどこかで朝がはじまっている
ぼくらは朝をリレーするのだ
という力強い言葉で、自分たちがこの大きな流れの一部であること、そしてそのバトンを受け取っていることの尊さを教えてくれます。
この詩のすごいところは、「地球」という壮大なスケールと、「朝」という個人的な日常を、いとも自然につなげてしまうところです。自分がこの広い世界の一部なんだ、と実感させてくれる不思議な力があります。
2. 五感に訴える描写の豊かさ
谷川さんは、難しい言葉や凝った比喩を使いません。しかし、「きりんの夢」「朝もや」「ほほえみ」「ウインク」といったシンプルな言葉が、読み手の頭の中に鮮やかな情景を思い浮かばせます。特別な装飾がなくても、世界中の人々の朝の温かさや息づかい、そして希望が伝わってくるのは、五感に訴える描写が的確だからです。
そして、詩の後半では聴覚にも訴えかけます。
眠る前のひととき耳をすますと
どこか遠くで目覚時計のベルが鳴っている
これは、遠い場所で誰かが朝を迎え、新しい一日を始める音。私たちもまた、そのバトンの一部なのだと感じさせてくれる、感動的な描写です。
3. 言葉のシンプルさと深いメッセージ
「朝のリレー」という言葉自体が、この詩の核心を突いています。太陽の光が東から西へバトンを渡していくように、世界中の人々が、それぞれの場所で朝を生きている。私たちは意識しなくても、皆が繋がっているという共生のメッセージが、平易な言葉で描かれているのです。
それはあなたの送った朝を
誰かがしっかりと受けとめた証拠なのだ
この一節は、私たち一人ひとりの「朝」が、実は誰かに届けられ、そして誰かの「朝」を受け取っているという、温かいメッセージを伝えています。私たちが日々を生きることが、地球という大きな共同体を守るリレーの一部なのだと感じさせてくれるのです。
受験生の「朝」も、大きなリレー
さて、この詩を中学受験に重ねて考えてみましょう。
お子さんが毎朝、机に向かうその「朝」も、まさに「朝のリレー」です。
- 眠い目をこすりながら、計算ドリルを開く時間。
- 苦手な社会の年号と格闘する時間。
それは、同じように頑張っている日本中の受験生たち、そしてかつて受験を経験したたくさんの大人たちと、見えないところで繋がっています。
この詩のように、お子さんたちの頑張りが、いつか世界へとつながる大きな夢へと変わっていく。この詩は、そんな未来への希望をそっと灯してくれます。
もしお子さんが勉強に疲れてしまったら、ぜひこの詩のことを話してあげてみてください。「君は一人じゃないんだよ」というメッセージが、きっと大きな力になるはずです✨。
最後までお読みいただきありがとうございました😊。
感想やご意見があれば、ぜひコメントで教えてくださいね!