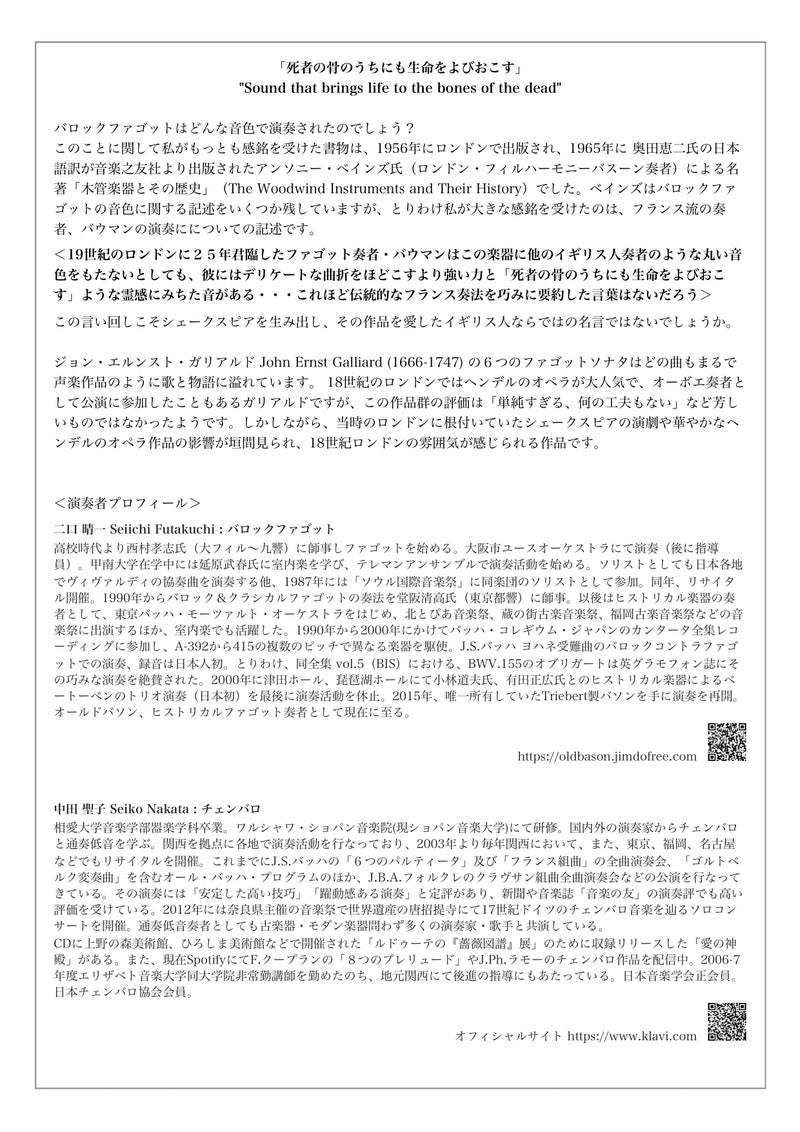バロックバスーンはどんな音色が良しとされたのだろう」と今でも自問自答しています。
昔はインターネットもないので、今のように文献も録音も気楽に検索して見聞きすることもできず、私がもっとも影響を受けたのは本でした。その本は、1956年にロンドンで出版され、1965年に 奥田恵二氏の日本語訳が音楽之友社より出版されたアンソニー・ベインズ氏(ロンドン・フィルハーモニーバスーン奏者)による名著「木管楽器とその歴史」(The Woodwind Instruments and Their History)でした。そのなかから18世紀のバスーンの音色に関する記述をいくつか紹介します。
(以下、転載)
・イギリス人たちが「馬の脚」と呼んだ古いバスーン(バロックバスーンのこと)は適当なリードを用いればたまらないほど甘美に響くのである。その音色は巧みに奏された近代フランスバスーンのそれに似ているともいえようが、しかしいくぶん音量が小さく、より安定し、引き締まり、どちらかというとチェロに似ている。旧式のオーボー同様、他のどの楽器ともよく混じり合うことはこの上ないが、一方、独奏楽器として好まれるに十分な重厚さも備えていた。
・18世紀中期を通じてのロンドン一流のバスーン奏者ミラー(Miller)は、「ヴォーホール(Vauxhall)などでのコンチェルトや、ヘンデルがオラトリオやコンチェルトの中で彼に割り当てたソロ・パートは人々の注意を呼び起こし、喜びを持って聴かれ、甘美な音色と端正な演奏ゆえにしかるべき喝采を博したのであった」といわれている。(バーニー・リースの百科事典より)。
・もうひとりここに名を挙げなければならないロンドンの奏者はホームズ(Holmes)である。彼の音色は「人声に非常に似ていた」といわれている。ハイドンの<シンフォニア・コンチェルタンテ>の初演をしたのもこのホームズで・・・
・もちろん下手なバスーン奏者も当時からいたもので、標準以下のバスーン奏者に当時あたえられたのは、「鼻づまり」だとか「山羊のようだ」とかいう言葉があった。これは、今日いう「がらがらした」とか「ベーコンを揚げているような音」だとかいう言葉に相当する。
アンソニー・ベインズはイギリス流・フランス流の奏法の違いについても丹念に文献をあたっており、次のような記述がみられました。
イギリス流について
・「強靭なリードを吹きこなす」ことを推奨(出典:Harmonicom 1830)
・外国人たち(フランス人のこと?)の「頼りない音色と意味のない演奏法」は七面鳥がその羽根で農家の中庭の地面を掃き歩いているようだ・・(出典:Harmonicom 1830)
フランス流
・イギリス人奏者たちの大まかなリードはタンギング(舌で音を発音させる技術)に特別の力を要求するために、
彼らは<ピアノ(小さな音・柔らかい音)>で演奏することがまったくできない・・・(出典:バール・1833年にパリで教則本を出版)
ベインズの著書の中でも、とりわけ私の心に残っていて今でも大好きな箇所は、フランス流のイギリス人奏者、バウマンの演奏にについての記述です
・19世紀のロンドンに25年君臨したバスーン奏者・バウマンはこの楽器に他のイギリス人奏者のような丸い音色をもたないとしても、彼にはデリケートな曲折をほどこすより強い力と「死者の骨のうちにも生命をよびおこす」ような霊感にみちた音がある・・・これほど伝統的なフランス奏法を巧みに要約した言葉はないだろう。(出典:不明)
この要約こそ、シェークスピアを生み出し、その作品を愛したイギリス人ならではの名言であると思います。
以下、コンサートのご案内です。
ジョン・エルンスト・ガリアルド John Ernst Galliard (1666-1747) の6つのファゴットソナタはどの曲もまるで声楽作品のように歌と物語に溢れています。 18世紀のロンドンではヘンデルのオペラが大人気で、オーボエ奏者として公演に参加したこともあるガリアルドですが、この作品群の評価は「単純すぎる、何の工夫もない」など芳しいものではなかったようです。しかしながら、当時のロンドンに根付いていたシェークスピアの演劇や華やかなヘンデルのオペラ作品の影響が垣間見られ、18世紀ロンドンの雰囲気が感じられる作品です。縁あって、18世紀のオリジナルのバロックファゴット(Prudent 1760?)が私の手元に居ます。この楽器を使ってのコンサートになる予定です。
ご予約はこちらから(お早めにどうぞ)