町奉行が任命される手順があります。
ちなみに人事異動というと我々ですと何処に異動になるにしても
辞令が出るのは普通だと思います。
ところが徳川幕府では、辞令など無いのです。
あくまでも将軍の言葉だけでした。
ちなみに人事の任免の際、「御用状」がきます。
「御用儀被為在候条、何日登城可有之」という御用召の紙が来ます。
もし、その紙の色が白であったら吉、鼠色であったら凶でした。
又、午前中のお召は吉、午後であったら凶であったという。
判りやすいですよね。
午後なら覚悟して心の準備が出来ます。
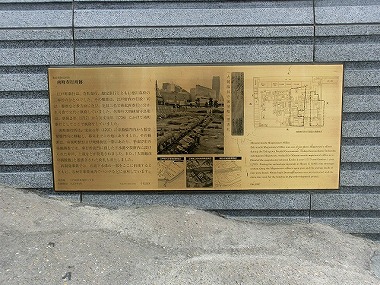
明治になって編纂された資料からかつて御側御用を務めた方が
町奉行を任命するにあたっての儀式を纏めたものがあるので
紹介します。
布衣(従6位相当)以上の役職任命は「御前御用」といわれた。
御座の間で将軍のお声掛けによって任命されるのです。
尚、6位相当と書きましたが、本来は官位は5位までしかありません。
幕府が作った官位ですが、旗本は、先ずは布衣になることを夢見て
頑張ったのです。
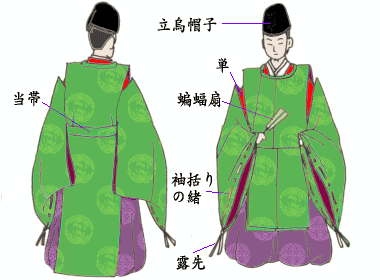
幕末の有能な官僚・川路聖謨も布衣に任命され、将軍家斉から
芝の浜離宮の釣り大会に招かれて、家斉からも声を掛けられ
感激し一層仕事に励もうと新たに決意した。
先ず先日に老中から登城すべき旨の御用紙(差し紙)が来る。
老中連署で「明日5つ半登城すべし」
早速、御受の返事をする使者を立てる。
登城、「御錠口」より入り、足袋を脱ぐ。
印籠・紙入れを預ける。
(貴人と逢う際は礼儀として、上記の品は持ち込まない。
鼻をかまない、火鉢に当らないが通常である)
御座の間にて待機、老中や若年寄などは3の間で座ってる。
時刻になると将軍が小姓を連れて出御、この時、警蹕の声
(シーシー)と云う声を出す。
次いで御用取次・小姓頭取・小納戸頭取・小姓らが着座
拝命者は、陶淵明の絵が描いてある杉戸を通り
御座の間の入側に着座。
月番老中が任命者の守名を将軍に披露。
将軍が「それへ」といい、入側から下段に入って好い、という意味
拝命者は、座したままでもじもじと体を動かす、
恐縮して体が動かないという仕草である
膝行といいます。膝だけ動かすのです。
将軍が「○○守町奉行を申し付ける
月番老中が代って応える
「結構に仰せ付けられ有り難ふぞんじます」
将軍「よふ勤めい」
老中「畏まり奉りました」
拝命者は下がる。
結局一言も無しである。
入側と呼ぶ縁側に入るだけで、下段の間にも入れない。
これは寺社奉行(大名)が拝命する時でも、半身を御座の間の
下段の間に差し向けるだという
町奉行ですと、従5位下朝散太夫です。
守名乗りが出来る官位です。
忠臣蔵でお馴染みの浅野内匠頭と同じで、小大名の官位官職です。
これは、内匠頭という官職を持つ従5位の位階の人という事です。
大名は大体、ここからスタートして行き、あとは、昇進することを
願います。
ちなみに、「頭」は寮の、「督」は兵衛府の、「正」は司の長官。
采女司(宮中で炊事を担当する采女を監督する役所)、
の長官が采女正となる。
これを見ても如何に、将軍との距離が遠いという事が分かります。
この遠さが将軍の尊厳を守るのです。
将軍の顔は近くとも御簾の陰にあるので見えるものではありません。
一門の一つであり幕末には政治職総裁を務め、参勤交代の
緩和という結果的には失敗であったことを行った福井藩主の
松平春獄は明治になっての回顧で述べている。
「将軍家へ御目見えの節は、尊顔を拝する等の事はこれなく、
御辞儀するばかり也。今の世にて考えれば、判りかたかるへし」
そして、福井藩に養子で赴く前、田安家に居た幼き頃
隠居し西の丸に居住してた祖父の家斉に対面した時の事を
述べている。
「公には最早隠居の身分故、目見の節は、よく予の顔を見て
辞儀すべしとのことを、側の者よりつたえたるものか、故に
一同有り難く御目見えの節、尊顔を拝しお辞儀せり」
つまり、御三家御三卿でさえも公式な将軍との御目見えの場合は
将軍の顔を見てはならず、将軍への直答すらも許されなかったのです。
しかし、この遠さを打ち破った人がいます。
勝海舟でした。
14代家茂の時ですが、話が遠いので家茂がもっと前へ、というので
遠慮なく前に出た。
後ほど、御用用人から勝が叱られますが、勝はそれに対して抗弁し
「近く進み出て国家のお大事を言上せんとするにこれを
制せられるは理由如何と」開き直っています。

