上口刑訴
問研刑訴
計6時間
今日は朝から学校で自習。
昼から法職講座・刑訴。
第1問は、新司法試験平成21年度の事案を圧縮したもの(百選35事件を参考にした事案)
捜索差押物件を写真撮影することの適法性を問う問題。
これは意表を突かれました。
捜索差押の場合の差押対象物件を写真撮影するということで混乱。
でも普通に写真撮影の強制処分性を確認して、令状が不要でもよいかを検討すればよかったんですね。
僕が混乱した原因の一つは、強制処分も「必要な処分」として行われるということを意識していなかったこと。
改めて考えれば当然ですね。
僕は、「必要な処分」として論じましたが(そういう学説もある)、判例は「捜索差押に付随する処分」として処理しています。
百選35事件の規範(地裁の規範)を覚えておこう。
第2問は、初回の接見指定の適法性と、それによって得られた自白調書の証拠能力について。
こちらはまぁまぁ書けた感じはしますが、条文をもっと意識すべきだと思いました。
古江本によると、
・39条3項本文「捜査のため必要があるとき」=接見指定の可否(接見指定の要件)
・39条3項但書「被疑者の防禦準備権の不当な制限」=指定内容の適否
と整理されるようです。
「取調べ中」ということから接見指定の要件が満たされ、指定可能となる。
「初回」ということから短時間でも即時に接見を認めるべきであった→接見を認めることができた→それをしなかった→不当な制限となり、違法。
それと、自白調書の証拠能力についてですが、僕は、先行手続が上記のとおり違法な手続なので、何のためらいもなく違法収集証拠排除法則を適用しました。
任意性説・違法収集証拠排除法則併用説に立てば当然認められる処理だとは思いますが、一応弁護士の先生に確認すると、併用説を知らなかったようでした。
学部授業で普通に「併用可能」と習ったので、当たり前のように違法収集証拠排除法則で書きましたが、まだそこまで当然に一般認識となっていないようですね。
(LS採点者や試験委員は当然知っているでしょうが)
併用説を採用するのであればその旨をきちんと書くべきでした。
購入しました。
- 行政法〈第3版〉/櫻井 敬子
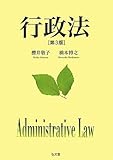
- ¥3,465
- Amazon.co.jp
これで一応7科目の基本書は揃った感じです。
(憲法にはまだ不安あり)
明日は一日中、明後日の憲法の試験勉強。
入試に直結する勉強はやりがいがある。