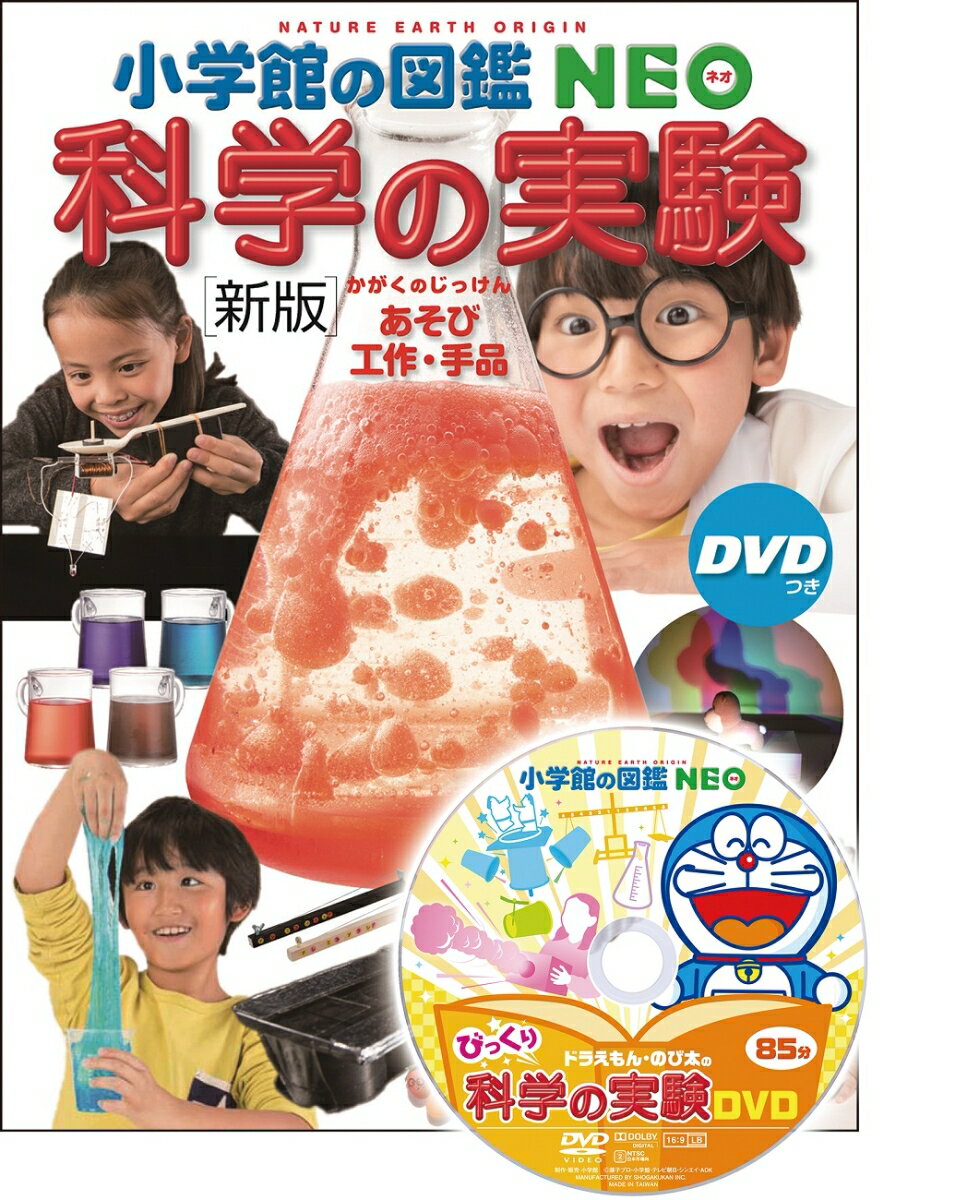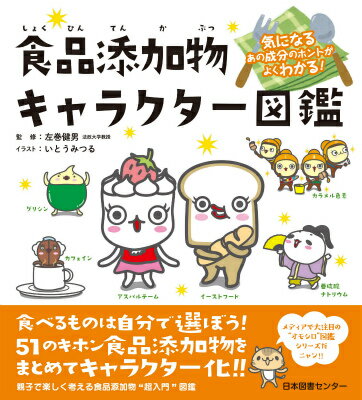少し前に、小田原にある鈴廣かまぼこの里に行きまして。

そこでかまぼこ手作り体験ができなかったのが残念で、お土産に買ったのがコチラです↓
材料は白身魚と塩、砂糖のみ。添加物は入っていません。
何の予定もない休日だったので、みんなでかまぼこを作ることにしました。
すり身パウダーを混ぜたあと、海のシリーズで形作り。クラゲ、ヒトデ、ペンギン、なぜかアンモナイトも。
フライパンに水を少しひき、その上にクッキングペーパーをしいてかまぼこを並べて、10分くらい蓋をして蒸したら完成。
水分飛ばして、焼き色もつけました!
魚の風味がシッカリ感じられるかまぼこの完成です。
料理を理科タイムに
せっかく子供と料理するなら、理科の知識をここで差し込んでおきたいところ。
かまぼこを蒸し焼きにしている間に、母からのクイズタイムです。
理科クイズ第1問 かまぼこが固まる理由は?
小1![]() 「ベーキングパウダー!」
「ベーキングパウダー!」
小3![]() 「グミと同じ!ゼラチン!」
「グミと同じ!ゼラチン!」
正解は〜
(子供に答えさせてる間に検索)
、、
、、
「魚のタンパク質が塩で溶けて、加熱で凝固するから!でしたー。ギョウコってのは、凝り固まるってことね。タンパク質は魚や肉に含まれる成分のことだよ。」
ゼラチンの素であるコラーゲンはタンパク質の一種なので、小3ムスメ![]() は正解に近かったですね。
は正解に近かったですね。
理科クイズ第2問 ものが燃えるのに必要な条件は?
昨年購入、いくつも実験しました!図解なので検索するより分かりやすいです。
なので、キャンプの焚火を思い出してもらいます。
「パパがさ、薪を組む時は空気の通り道を作った方がよく燃えるといってたよね」
「あと、焚火にうちわで風送ると、よく燃えるじゃん![]() 」
」
「…くうき?![]() 」
」
「だいたい正解!ものが燃えるには、空気中に含まれる酸素が必要なんだよ〜」
「図鑑で、燃やすモノと、酸素と、熱の3つが必要って書いてあったよ![]() 」
」
【追記】
タンパク質とゼラチンの気になる話
タンパク質が熱で固まる性質を持つなら、なぜタンパク質の一種であるゼラチンはなぜ熱で溶けるのか不思議じゃないですか?
ChatGPTに聞いたところ
ゼラチンは、コラーゲン(タンパク質)を加熱、分解したもので、構造が変化しているんだそう。
一般的なタンパク質は、加熱すると固くなるという非可逆性の変化が起きます。目玉焼きの白味が加熱で白く固まり、元には戻らないように。しかしゼラチンはすでにタンパク質とは構造が異なっており、加熱すると性質が絡み合う→冷えると解けて元に戻る、という可逆性の性質を持つ物質構造になっているという訳です。
今の子供たちに教えてもチンプンカンプンだろうから、母が気がついたこの疑問はまた次の機会にクイズにします![]()