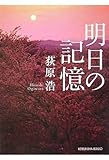光文社文庫の11月新刊。山本周五郎賞受賞作ということであるし、映画化されて話題になったことも記憶に新しい。そういう意味では、待望の文庫化と言うことができようか。
すでに世評を得た作品であり、自分のような者が苦言を呈するのはどうかと思うのだが、それでも述べておきたい。前回読んだ『メリーゴーランド 』でも感じたことだが、この作家の文章はやはり雑で稚拙だと思う。もしかしたら、文筆業には珍しく、ボキャブラリーが貧困なのではないかと疑ってしまう。テーマの立て方や、それを小説作品として具現化する方策には非凡なものを感じるだけに、文章の弱さが惜しまれてならない。重いテーマだから、平易な言葉を選んで軽い文章を志向した、という次元ではないと思うのだ。
ストーリーは、若年性アルツハイマーの進行を正面から描いていて、センセーショナルである。広告代理店営業部長の佐伯雅行は、不眠症に苦しみ、仕事上でもポカが続いて、精神科を受診したところ、アルツハイマーと診断される。彼はまだ50歳になったばかりの若さであった。記憶が消えてゆく恐怖に捉われながら、職場での彼は現在進行しているプロジェクトだけは成し遂げたいと思うし、家庭では、結婚を間近に控えた娘のために営業部長の立場で挙式を迎えたいと願い、趣味の作陶で若い夫婦に湯飲みを贈りたいと考える。彼は自分の罹病を否定するためにも、必死にメモを取って記憶を繋ぎとめ、正常を装おうとするが、病気は着実に進行し、ついには職場を追われ、最後には妻のことさえわからなくなってしまうのだ。この病気は、自分が自分でなくなってゆく恐怖に直面するわけで、例えば「癌と戦う」ということとも別種の悲惨さがあり、しかも誰もが発病する可能性を秘めているだけに、非常に身に詰まされる内容になっている。特に夫婦間には、この小説が終ってからもなお長い時間が続くことを思うと、暗澹としてくるのを禁じえない。著者は面白く読めるように工夫を凝らしているけれど、これは辛い小説である。
もう一つ苦言を添えるなら、この作品が佐伯雅行の「私」という独白で進行するのは不自然である。自分は基本的に一人の視点で語られる一人称の作品を愛するけれど、例えばハードボイルドなどで最後に「私」が死ぬケースがあり、「目の前が暗くなった」などと呟いて終ることには、違和感があった。死の実況中継をするような「私」の存在はありえないと思うのだ。同じように、記憶を喪失してゆき、日記さえまともに書けなくなる「私」が、最後まで普通に語り続けるこの作品も、どうにもしっくりとこないのである。
と、文句を並べてしまったが、注目作であることは認めざるを得ない。束の間の健康に感謝するためにも、一読の価値はあると思う。
2007年11月26日 読了