例の『1Q84』を読んでみました。純文学最速ミリオンセラー到達が話題になっている、村上春樹の新作です。
しかし、ぼくとしてはあまり好きになれませんでした。むろん、おもしろいところはあるのです。けれども意外性がない。かつて見た光景がそのまま展開されている。この小説を村上春樹の総決算として評価するひともいるようですが、それは裏返せば、想定の枠に収まった作品ということでもあります。
あえて斜に構えて分析すれば、おそらくはこの小説は、だからこそ売れているのでしょう。発売前の増刷が示しているように、『1Q84』のセールスを支えているのは内容を読んだ読者ではない。内容など関係なく購入する、かつての熱心な村上読者です。『1Q84』は、そのような読者の後ろ向きの期待にしっかり応えている。
そう考えると、この小説が、わざわざ1984年を舞台にした理由も見えてきます。
村上春樹はじつは還暦を迎えた老境の作家です。しかし今回の小説、主題も人物も、そんな年齢の作家とは思えないくらいに若々しい。それこそが村上の魅力と言われればそうなのですが、しかし、還暦を迎えてなお「自分探し」や「父との和解」に拘る作風はいささか不自然でもある。四半世紀前の東京を物語の舞台にしたのは、そんな不自然さを作家自身が自覚していたからかもしれません。
つまりは、この『1Q84』は、村上春樹という60歳の大作家が、まだ世界が1984年であるかのように、そして自分が35歳の新人であるかのように装って書いた、一種のコスプレ小説なのではないでしょうか。
むろん、小説の読み方はひとそれぞれです。『1Q84』が、今年の日本文学を代表する作品であることはまちがいない。興味のあるひとは、ぜひ手にとってみてください。
ところで、今回『1Q84』の話をしたのは、ぼくが文芸評論家だからでもあります。
多くの読者には意外かもしれませんが、村上春樹という作家は、じつは長いあいだ正当に評価されてきませんでした。たとえば彼は芥川賞を獲っていない。90年代に入っても、主流の批評家は村上の存在を無視しています。いまでもそのようなひとはいます。
これは必ずしも文壇の閉鎖性故とも言えません。村上春樹の文学は、そもそも日本近代文学の伝統のなかではかなり異質なのです。にもかかわらず、その村上こそが日本文学を支えてしまった。だから多くの文学者は、その逆説から目を逸らすことしかできなかったのです。
とはいえ、村上文学の評価が国外で高まり、毎年のようにノーベル賞候補と報じられるここ10年で、その風向きもずいぶん変わってきました。ぼく自身を含め、いま若手の批評家のあいだでは、村上春樹の正当な位置づけなくして日本文学の未来はない、という合意が(ようやく!)作られつつあります。『1Q84』は、そんな状況で出版された久しぶりの本格長編でした。
だからこそ、その作品が既視感しか与えなかったことに、ぼくは本当にがっかりしたのです。いまだからこそ、村上春樹には思う存分に新境地を拓いてほしかった。今回こそは、支持する批評家が大量に現れたはずなのです。
むろん、そんな批評の動向など、100万部の現実のまえではどうでもいい話でしょうが---。
週刊朝日2009年6月26日号より
動物化するポストモダン―オタクから見た日本社会 (講談社現代新書)/東 浩紀

¥735
Amazon.co.jp
ゲーム的リアリズムの誕生~動物化するポストモダン2 (講談社現代新書)/東 浩紀
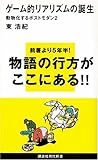
¥840
Amazon.co.jp
文学環境論集 東浩紀コレクションL/東 浩紀

¥2,730
Amazon.co.jp