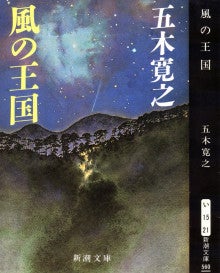かつては映画を観たり、本を読んだりした後に印象に残ったものがあると、簡単なメモを取っていた。それによると、 ジプシー(ロマ)に興味を持つようになったきっかけは、どうやら1969年の末に試写会で観たアレクサンドル・ペトロヴィッチ監督の映画「ジプシーの唄をきいた」(67年、ユーゴスラビア、カンヌ映画祭グランプリ受賞)がだったようだ。世間の偏見、差別に晒されて、安酒を煽りながら、あくまで自らの価値観に基づいて自由奔放に生き抜く根無し草のような逞しさに惹かれたのだと思う。
『ジプシーの唄をきいた』(67)
日本とは殆ど無関係なように思えるジプシーだが、意外に身近なところにジプシー文化は根を下ろしている。例えば、真偽のほどは判らないがタロット・カードはジプシーがヨーロッパ各地に広めたものと言われ、日本でもすでにお馴染みのカード。ちなみに、トランプはタロット・カードをよりシンプルに発展させたものだから、僕ら日本人はすでに子供の頃からジプシー文化と接点があったことになるのかも知れない。
それはともかく、ジプシー民族は一体どこからやって来たのだろうか?ヨーロッパで彼らがジプシーと呼ばれるようになったのは、当初はエジプト方面からやって来て、定住しない得たいの知れない民族と思われていたからで、エジプト人だと思われていたようだ。従って、ジプシーの語源はその“Egyptian”から来ている。が、元々の民族発祥の地はインドの北部辺りというから時代は全く異なるが、ケルトと共通しているというのも面白い。その後ヨーロッパやアジア各地に散らばったと見られている。で、彼らがヨーロッパに姿を現したのは15世紀頃のこと。定職に就かず、馬車などでの移動生活を続け、キリスト教徒でもなければ、言語(ロマ語)も違う彼らは、ヨーロッパ人の生活習慣や文化、宗教、価値観などで相容れなかったため、当初から異教徒として差別の対象になった。
そんな彼らジプシーの生業は、鍛冶、金属加工、木工細工などで、言わば技術集団。そしてもう一つの特徴て言えば、楽器類を常に携えて酒を呑んで歌ってと踊る、つまり大道芸などを披露して回る放浪芸集団としての一面も兼ね備えている。そんなこともあって、各地の村祭りや結婚式などに呼ばれて歓迎されたというから、差別される一方でご都合主義的に重宝がられていたことも窺える。
実は日本にもジプシーがいたと言うと驚く人も多いかも知れない。日本にかつて山窩(サンカ)と呼ばれる流浪の民がいて、日本のジプシーとも呼ばれているのだ。実際、一説にはジプシーの一部は日本に渡来して山窩(サンカ)になったという話もある。ジプシー系北方民族、タタール人が日本に渡って来たという話だが、確かにジプシーの生業と山窩の生業は一致するし、その一族だと言われる出雲阿国は芸能に秀でていて歌舞伎の原型を作ったとされる。それにタタール→タタラ→鍛冶、金属加工と考えると面白い。ちなみに歌舞伎のタタラを踏むという仕草は、鍛冶のタタラから来ている。それに間宮海峡も、かつてはタタール海峡と呼ばれていたことなどを考えると満更ウソでもないのでは…。さすれば、根なし草の“草”と呼ばれた忍者集団もその末裔なのでは、などと考えるとロマンが広がる。
『漂泊の民 山窩の謎』佐治芳彦
尚、山窩に関しては山窩文学の先駆者と言われる三角寛が知られているが、果たて山窩の文化を正しく伝えているかどうかについては個人的には少々疑問符が残る。
また彼らの魔女占いやシャーマニズムが、東北のイタコや口寄せ巫女、沖縄、奄美のノロやユタに通じるところがあるのも興味深いところ。
山窩一族のヒストリーを描いた五木寛之の『風の王国』
が、忘れてならないのはジプシー民族に常について回る迫害と差別の問題だろう。異教徒であったジプシーに対してヨーロッパ諸国は国外追放法政策を打ち出した為に、好むと好まざるとにかかわらず、結果的に流民化せざるを得なかったという歴史的経緯がある。元々土地を全ての人間の共有物と考えるジプシーと、土地の占有権を売買するヨーロッパ人との根本的な価値観の違いも大きかったに違いない。その違いは、まるで縄文的価値観と弥生的価値観の違いにも似ている辺りも面白いところではないだろうか。
ともあれ、ジプシーに対する迫害は近年になっても終息していない。例えば意外に知られていないのが、第二次世界大戦中にナチスによって虐殺されたのはユダヤ人だけではなく、標的にされたジプシーも50万人以上が虐殺されている。2000年にはスイスでジプシーの子供ばかり1000人(73年までに)が民族せん滅の目的で誘拐され、背後にスイス政府が関わっていたことが明るみに出て大問題に発展したこともある。そして昨年には何かと物議をかもすお騒がせなフランスのサルコジ大統領がジプシーの国外追放を命じて、反対運動が起こったばかり。残念ながらジプシー排斥の動きはいまだに現在進行形なのだ。
マールタ・シェベスチェーン&ムジカーシュ
で、ジプシー関連の音楽もまた千差万別で楽しい。何しろハンガリー、ルーマニア、ブルガリアの東欧、バルカン半島、、イタリア、フランス、スペインとヨーロッパ各国に跨っているのだから当然と言えば当然。
マールタ・シェベスチェーン&ムジカーシュ『ブルース・フォー・トランシルヴァニア』
ジプシー音楽に興味を持ったきっかけになったのは、ハンガリアン・トラッド・シンガーであるマールタ・シェベスチェーンのアルバムとの出逢いだった。ジプシー音楽と混ざり合い、影響し合いながら口承されてきたバルカン半島の伝承歌と出会って、すっかりハマッてしまった。多分最初に聴いたのは80S末頃だったように記憶しているが、マールタ・シェベスチェーン&ムジカーシュの『ブルース・フォー・トランシルヴァニア』か同じく『プリズナーズ・ソング』だったか。ちょっと鼻にかかっていてコブシを効かせた歌唱、それでいて母なる大地を思わせるようなディープな歌声が最高です。ディープ・フォレストの『ボエム』(95)にマルタの歌をフィーチャーした「マルタズ・ソング」が収録されて話題に、そして映画『イングリッシュ・ペイシェント』(96)の冒頭で流れる挿入歌も印象深い。それから、そうそう映画『おもひでぽろぽろ』の挿入歌も歌っている。(マールタとは来日時にインタビューしたので、行く行く紹介しようかと思ってます。魅力的な人でした。)
マールタ・シェベスチェーン&ムジカーシュ『プリズナーズ・ソング』
とは言え、トレンディーなワールド・ミュージック・ファンにはジプシー版ブエナヴィスタ・ソシャル・クラブとも言うべきタラフ・ドゥ・ハイドゥークスや、映画『炎のジプシーブラス 地図にない村から』に登場したジプシー・ブラスのファンファーレ・ チォカリーア、或いはちょっと下世話なジプシー・キングスなどの方が馴染み深いだろう。そうそう、ジプシーは差別用語として禁止され、ロマと呼ばなければならないと言うが、それでは自らジプシー・キングスと名乗っているバンドがいるのはどういうわけか?差別とは呼称などではなく、社会通念が育んで来た差別する心であって、それ以外の何物でもない。本当は呼称なんてものはあだ名(愛称)みたいなものだと思えば何の問題もない筈だ。というわけで、ここでは敢えてジプシーで通してますので、悪しからず。m(__)m
タラフ・ドゥ・ハイドゥークス 『Band Of Gypsies』
一方、映画ファンにはホアキン・コルテス主演の『ジターノ』(2000年、マヌエル・パラシオス監督)や『ジプシーのとき』(89年、エミール・クストリッツァ監督)『ラッチョ・ドローム』(93年、トニー・ガトリフ監督)、『ベンゴ』(2000年、トニー・ガトリフ監督)などが面白いかも。後者のサントラ盤の中ではインドからスペインのアンダルシアに定着するまでのジプシーの長い旅をテーマにした『ラッチョ・ドローム』は、ラジャスタンからスペインに至る各国のアーティストが収録されていて面白い。『ジターノ』の方はジプシー音楽のスピリット、その象徴としてのフラメンコを描いていて、トマティートと並ぶフラメンコ・ギターの第一人者、ビセンテ・アミーゴが参加している。ジプシーの血を引くトニー・ガトリフ監督が撮り、カンヌ国際映画祭のクロージングを飾った『トランシルヴァニア』(2006)も記憶に新しい。
『ラッチョ・ドローム』(93)
他にもジプシー・ジャズ・ギタリストの大御所、ジャンゴ・ラインハルトなども興味のある方は、一聴を!
『トランシルヴァニア』(2006)
ところで“ジプシー”というカクテルがあるそうな。ウオッカに薬草系リキュールのベネディクティンを加えてシェイクしたものだというが、是非とも呑んでみたいものだと思う。心当たりがある方、誰か誘って下さいまし。m(__)m