金の瞳のリゼ・ACT1 アーニーとセディ Part2
限定公開版をお読みの方も、続きはこちらから。
金の瞳のリゼ ACT1 アーニーとセディ Part2
翌朝。
いつもの時間にハウスメイドが朝食を届けに来ても、姉さんは自分の寝室から出てこなかった。
「おはようございます、ミスター・グレンフィールド。朝食のお飲物は、珈琲と紅茶のどちらになさいますか?」
つやつやのりんごのような頬をしたハウスメイドが運んできた真鍮のワゴンには、熱々のポリッジにポーチドエッグ、かりかりのベーコン、ソーセージ、かぶのポタージュスープ、ほうれん草のキッシュと、量も味もとても充実した朝食が載っている。焼きたてのパンにはバターとはちみつが添えてある。
この下宿の良いところは、第一に間借り人に対してよけいな詮索を一切しないこと、そして第二がこの食事だ。
「おはよう、メグ。そうだな、ぼくは珈琲をもらうよ」
「かしこまりました。それで、あのぅ……、もうお一方のミスター・グレンフィールドはまだおやすみでしょうか?」
「ああ、兄さんは……まだ寝てるんだ。その、ちょっと二日酔いでね」
――昨夜は、さすがにちょっと、やりすぎたかな。
だって姉さんがあんまり可愛く泣くから。
ぼくもつい抑えが効かなくなってしまって。はっと我に返った時には、姉さんは泣き濡れた頬を青ざめさせて、完全に意識を失っていた。
「まあ、珍しい。ミスター・アーノルドが二日酔いになるほどお酒を過ごされるなんて」
メグから見れば、ミスター・アーノルド・グレンフィールドは、酔っぱらって階段の下で寝こけていたり、若いメイドを卑猥なジョークでからかったり、すれ違いざまに彼女のお尻を撫でたりしない、まさに紳士の鑑だ。信じられないと思うのも無理はないだろう。
――言っておくが、ぼくだってメイドのお尻を触ったことなんかないよ! 深酒して階段を転げ落ちたことなら、二、三度あるけど。
「ここはもういいよ、メグ。兄さんの朝食は、ぼくが運ぶから」
「かしこまりました。では、失礼いたします」
軽く膝を曲げて可愛らしく一礼すると、メグはそそくさと部屋を出ていった。
貴婦人付きの小間使い(レディズ・メイド)と違って、彼女のような、中流家庭に雇われる雑働き女中(メイド・オブ・オールワークス)は、その名のとおり家の中のことを何でもかんでも引き受けなくてはならない。一分一秒だって手と足を休めているヒマはないのだ。
「さて、と。じゃあ、姉さんのご機嫌をうかがいに行こうかな」
こんがり焼けたキッシュを持って、ぼくは姉さんの寝室のドアをノックした。
「姉さん。――リゼ姉さん。もう起きてる?」
返事はない。
「姉さん、朝食だよ。ほら、姉さんの好きなほうれん草のキッシュもあるよ」
もう一度声をかけてから、ぼくはそうっとドアを開けた。
木目と落ち着いたローズグレーを基調にした寝室は、まだ窓に厚いカーテンが引かれ、かなり暗かった。
備え付けのベッドには、シーツに埋もれるようにして、くしゃくしゃに寝乱れたハニーブロンドが見える。
「まだ寝てるの? 姉さん」
近づいて優しく呼びかけると、姉さんは応えるようにゆっくりと寝返りをうった。
「おはよう、朝だよ。起きられる?」
「……セディ――」
シーツの波の合間から掠れた声がぼくを呼んだ。そして金色の瞳が、いささか焦点の合わないまま、ぼくを見上げる。
昨夜は、居間のソファーで意識を失った姉さんを、ぼくがこのベッドまで運んだ。本当ならそのまま同じベッドで眠って、もう一度愛し合いたかったんだけど。
「セディのばか」
枕から顔をあげようともせず、姉さんはひどく恨めしそうに言った。
「やだって、言ったのに……。もうやだ、やめろって、あんなに――」
うん。まあ……。それはぼくもちゃんと聞いたよ。
ぼくを睨む目が、うっすら涙ぐんでいる。
昨夜ぼくが着せた寝間着の襟元から覗く、姉さんの白い肌。そこには濃く薄く、いくつもの愛撫の痕が刻みつけられていた。ハイカラーのワイシャツとクラヴァットで隠れる位置ではあるものの、どんな行為の痕跡であるか、一目でわかる。
ああ、まったく。ぼくは最低の男だ。涙をこらえて薄紅く染まるその目元に、欲情してる。
「ごめん、姉さん。反省してる。今度はもっと優しくするから――」
泣き顔まで可愛い大切な恋人に、なだめるようにキスしようとすると。
「ばかやろッ! もう二度とするかッ!!」
身をかがめたぼくの顔面に、力いっぱい枕が叩きつけられた。
「おまえとはもう二度とキスもなんもしない! 出てけ、ばかっ!!」
枕やクッションが続けざまに飛んでくる。
「ご、ごめん、姉さん! ごめんってば!」
「うるさい! セディのばか、阿呆っ! 変態! ど助平!!」
姉さんは、ベッド回りにあるものを手当たり次第に投げつけてきた。
枕や室内スリッパよりずっと硬い、ヘアブラシや手鏡、革装幀の祈祷書なんかが飛んでくる前に、僕は這々の体で寝室を逃げ出した。
――やれやれ。姉さんのご機嫌はそうとう悪いらしい。
機嫌を直してもらうには、ほうれん草のキッシュ以上の贈り物が必要なようだ。
ぼくはひとり淋しく朝食を終えると、自分でワゴンを押して台所へ向かった。
「まあ、ミスター・セオドア。そんなことをなさらなくても、いつもどおり廊下に出しておいてくだされば、メグが片づけにまいりましたのに」
この下宿のキッチンを預かる家政婦兼料理人のハリエット・モリス夫人は、えくぼが魅力的な、たっぷりしたティーポットみたいに丸々としたご婦人だ。家主のオルソン夫人とは旧知の間柄だそうだ。
「いいんだよ、ミセス・モリス。実はあなたにお願いがあるんだ。また、りんごの甘煮を作ってくれないかな」
アップルパイの、パイ生地に詰める前のりんごの甘煮。特にモリス夫人が作るりんごの甘煮は、姉さんの一番の好物だ。
「メグから聞いてますよ。お兄さまが少しお加減を悪くされたようだとか。ええ、お待ちください。ちょうど昨日、パイを焼こうと思って買い込んでおいたんです」
モリス夫人は下宿人ひとりひとりの好みを正確に把握している。アーノルド・グレンフィールド氏が若い男性にしては珍しく、フルーツや甘いものが好きだということも。
「じゃあ、よろしく」
「あ、少しお待ちください、ミスター・セオドア」
台所を出ようとするぼくを、モリス夫人が呼び止めた。
「今、カモミールとローズマリーのお茶を用意します。このお茶で、お兄さまのお加減も良くなりますよ」
「……ありがとう」
カモミールとローズマリーってのはたしか、女性の冷え性や生理不順に効果があるハーブじゃなかったろうか。
やはり、若いハウスメイドはともかく、この下宿を切り盛りしているふたりの女性は、ぼくの兄アーノルド・グレンフィールドの正体に気づいているのかもしれない。
「ありがとう、ミセス・モリス。――世話をかけるね」
「どういたしまして。ですがそういう優しいお言葉は、私よりもどうぞ大切なお兄さまにおっしゃってあげてくださいまし」
モリス夫人は両手を腰に当て、ひどく怖い顔をしてぼくをじろりと睨み据えた。
「とかく殿方というものは、ご自分のパートナーの価値を軽んじがちです。一度、胸に手をあててよぉーくお考えになってごらんなさいまし。もし今、パートナーの方が忽然と消えてしまったら、自分ひとりだけで今までと同じ暮らしができるものかどうか。それをきちんとわきまえていたら、けして無体な真似はできないはずですよ」
「はい。……肝に銘じます」
世間の荒波を泳ぎ切ってきた女性の鋭い警告に、ぼくは唯々諾々とうなずくしかなかった。
第一章が終わったとこなので、ちょっと短いけど今回はここまで。続きはまた今度。
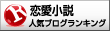
お気に召しましたら、ぽちっとクリックお願いいたします。
金の瞳のリゼ ACT1 アーニーとセディ Part2
翌朝。
いつもの時間にハウスメイドが朝食を届けに来ても、姉さんは自分の寝室から出てこなかった。
「おはようございます、ミスター・グレンフィールド。朝食のお飲物は、珈琲と紅茶のどちらになさいますか?」
つやつやのりんごのような頬をしたハウスメイドが運んできた真鍮のワゴンには、熱々のポリッジにポーチドエッグ、かりかりのベーコン、ソーセージ、かぶのポタージュスープ、ほうれん草のキッシュと、量も味もとても充実した朝食が載っている。焼きたてのパンにはバターとはちみつが添えてある。
この下宿の良いところは、第一に間借り人に対してよけいな詮索を一切しないこと、そして第二がこの食事だ。
「おはよう、メグ。そうだな、ぼくは珈琲をもらうよ」
「かしこまりました。それで、あのぅ……、もうお一方のミスター・グレンフィールドはまだおやすみでしょうか?」
「ああ、兄さんは……まだ寝てるんだ。その、ちょっと二日酔いでね」
――昨夜は、さすがにちょっと、やりすぎたかな。
だって姉さんがあんまり可愛く泣くから。
ぼくもつい抑えが効かなくなってしまって。はっと我に返った時には、姉さんは泣き濡れた頬を青ざめさせて、完全に意識を失っていた。
「まあ、珍しい。ミスター・アーノルドが二日酔いになるほどお酒を過ごされるなんて」
メグから見れば、ミスター・アーノルド・グレンフィールドは、酔っぱらって階段の下で寝こけていたり、若いメイドを卑猥なジョークでからかったり、すれ違いざまに彼女のお尻を撫でたりしない、まさに紳士の鑑だ。信じられないと思うのも無理はないだろう。
――言っておくが、ぼくだってメイドのお尻を触ったことなんかないよ! 深酒して階段を転げ落ちたことなら、二、三度あるけど。
「ここはもういいよ、メグ。兄さんの朝食は、ぼくが運ぶから」
「かしこまりました。では、失礼いたします」
軽く膝を曲げて可愛らしく一礼すると、メグはそそくさと部屋を出ていった。
貴婦人付きの小間使い(レディズ・メイド)と違って、彼女のような、中流家庭に雇われる雑働き女中(メイド・オブ・オールワークス)は、その名のとおり家の中のことを何でもかんでも引き受けなくてはならない。一分一秒だって手と足を休めているヒマはないのだ。
「さて、と。じゃあ、姉さんのご機嫌をうかがいに行こうかな」
こんがり焼けたキッシュを持って、ぼくは姉さんの寝室のドアをノックした。
「姉さん。――リゼ姉さん。もう起きてる?」
返事はない。
「姉さん、朝食だよ。ほら、姉さんの好きなほうれん草のキッシュもあるよ」
もう一度声をかけてから、ぼくはそうっとドアを開けた。
木目と落ち着いたローズグレーを基調にした寝室は、まだ窓に厚いカーテンが引かれ、かなり暗かった。
備え付けのベッドには、シーツに埋もれるようにして、くしゃくしゃに寝乱れたハニーブロンドが見える。
「まだ寝てるの? 姉さん」
近づいて優しく呼びかけると、姉さんは応えるようにゆっくりと寝返りをうった。
「おはよう、朝だよ。起きられる?」
「……セディ――」
シーツの波の合間から掠れた声がぼくを呼んだ。そして金色の瞳が、いささか焦点の合わないまま、ぼくを見上げる。
昨夜は、居間のソファーで意識を失った姉さんを、ぼくがこのベッドまで運んだ。本当ならそのまま同じベッドで眠って、もう一度愛し合いたかったんだけど。
「セディのばか」
枕から顔をあげようともせず、姉さんはひどく恨めしそうに言った。
「やだって、言ったのに……。もうやだ、やめろって、あんなに――」
うん。まあ……。それはぼくもちゃんと聞いたよ。
ぼくを睨む目が、うっすら涙ぐんでいる。
昨夜ぼくが着せた寝間着の襟元から覗く、姉さんの白い肌。そこには濃く薄く、いくつもの愛撫の痕が刻みつけられていた。ハイカラーのワイシャツとクラヴァットで隠れる位置ではあるものの、どんな行為の痕跡であるか、一目でわかる。
ああ、まったく。ぼくは最低の男だ。涙をこらえて薄紅く染まるその目元に、欲情してる。
「ごめん、姉さん。反省してる。今度はもっと優しくするから――」
泣き顔まで可愛い大切な恋人に、なだめるようにキスしようとすると。
「ばかやろッ! もう二度とするかッ!!」
身をかがめたぼくの顔面に、力いっぱい枕が叩きつけられた。
「おまえとはもう二度とキスもなんもしない! 出てけ、ばかっ!!」
枕やクッションが続けざまに飛んでくる。
「ご、ごめん、姉さん! ごめんってば!」
「うるさい! セディのばか、阿呆っ! 変態! ど助平!!」
姉さんは、ベッド回りにあるものを手当たり次第に投げつけてきた。
枕や室内スリッパよりずっと硬い、ヘアブラシや手鏡、革装幀の祈祷書なんかが飛んでくる前に、僕は這々の体で寝室を逃げ出した。
――やれやれ。姉さんのご機嫌はそうとう悪いらしい。
機嫌を直してもらうには、ほうれん草のキッシュ以上の贈り物が必要なようだ。
ぼくはひとり淋しく朝食を終えると、自分でワゴンを押して台所へ向かった。
「まあ、ミスター・セオドア。そんなことをなさらなくても、いつもどおり廊下に出しておいてくだされば、メグが片づけにまいりましたのに」
この下宿のキッチンを預かる家政婦兼料理人のハリエット・モリス夫人は、えくぼが魅力的な、たっぷりしたティーポットみたいに丸々としたご婦人だ。家主のオルソン夫人とは旧知の間柄だそうだ。
「いいんだよ、ミセス・モリス。実はあなたにお願いがあるんだ。また、りんごの甘煮を作ってくれないかな」
アップルパイの、パイ生地に詰める前のりんごの甘煮。特にモリス夫人が作るりんごの甘煮は、姉さんの一番の好物だ。
「メグから聞いてますよ。お兄さまが少しお加減を悪くされたようだとか。ええ、お待ちください。ちょうど昨日、パイを焼こうと思って買い込んでおいたんです」
モリス夫人は下宿人ひとりひとりの好みを正確に把握している。アーノルド・グレンフィールド氏が若い男性にしては珍しく、フルーツや甘いものが好きだということも。
「じゃあ、よろしく」
「あ、少しお待ちください、ミスター・セオドア」
台所を出ようとするぼくを、モリス夫人が呼び止めた。
「今、カモミールとローズマリーのお茶を用意します。このお茶で、お兄さまのお加減も良くなりますよ」
「……ありがとう」
カモミールとローズマリーってのはたしか、女性の冷え性や生理不順に効果があるハーブじゃなかったろうか。
やはり、若いハウスメイドはともかく、この下宿を切り盛りしているふたりの女性は、ぼくの兄アーノルド・グレンフィールドの正体に気づいているのかもしれない。
「ありがとう、ミセス・モリス。――世話をかけるね」
「どういたしまして。ですがそういう優しいお言葉は、私よりもどうぞ大切なお兄さまにおっしゃってあげてくださいまし」
モリス夫人は両手を腰に当て、ひどく怖い顔をしてぼくをじろりと睨み据えた。
「とかく殿方というものは、ご自分のパートナーの価値を軽んじがちです。一度、胸に手をあててよぉーくお考えになってごらんなさいまし。もし今、パートナーの方が忽然と消えてしまったら、自分ひとりだけで今までと同じ暮らしができるものかどうか。それをきちんとわきまえていたら、けして無体な真似はできないはずですよ」
「はい。……肝に銘じます」
世間の荒波を泳ぎ切ってきた女性の鋭い警告に、ぼくは唯々諾々とうなずくしかなかった。
第一章が終わったとこなので、ちょっと短いけど今回はここまで。続きはまた今度。
お気に召しましたら、ぽちっとクリックお願いいたします。