応援していただける方!
↓ のクリックをお願いします!
自然科学 ブログランキングへ
にほんブログ村
今日、初めてグランフロント大阪
を通過してきました
風景が全く変わっていて、唖然
そして、ものスゴい数の、人、人、人
場所によっては、左側通行の規制も
午後少し回っていましたが
レストランなどの外には順番待ちの列
落ち着くのはしばらく先になりそうです
前回の
「顕微鏡って、どこまで拡大できる?(1)」
では、
顕微鏡の性能は
小さい2点を区別できる分解能で表す
そして、
その分解能は波としての光の性質が
効いている
と書きました
読者の方から
「次はまだ? 早く読みたい。」
という、ありがたいコメントを
いただきましたので、
焦らさずに
今回はその先に進みましょう
結果的には
その分解能には光の波長で決まる
ということなのですが
そこにたどり着く前に
光が波だと
どんなことが起きるのか見ておきます
そもそも、波ですが
池に石を投げ込んだときにできる
波紋を思い浮かべてください

石が水に入った場所から
同心円上に波が広がります
2つの石を少し離して落とすと
それぞれの波紋で
山と山は強め合い
山と谷は打ち消し合う
という、干渉が起きます

光も波なので、
これと同じ現象が起きます
例えば、ヤングの実験

電気通信大学のサイトより
2つの光源から出た光は
干渉でスクリーンに縞が現れます
光も
山と山は強め合い
山と谷は打ち消し合います
山と谷が打ち消し合うと
光は消えます
この光が波であることによる干渉が、
レンズの分解能に大きく関係するのです
レンズで拡大できるのは下図の通りで
例えば、鉛筆の先端のから出た光が
レンズのいろいろな箇所を通過して
屈折を受けて進み、そのうち1点で
交わります
これを結像といって、
はっきり見える状態となります

東北大学多元物質科学研究所・石島秋彦先生のサイトより
上図では、比較的大きい物体を
見ていますが
無限に小さい点光源をレンズを通して
拡大すると、、、
1点に集まらないのです!
拡大してボヤけるからではありません
どういうことでしょうか?
点光源から出た光も
レンズのいろいろな箇所を通過します
レンズのどこを通過するかによって
結像までに光が進む距離も変わります
ここで、
先に書きました干渉が関係するのです
つまり、
光が進んだ距離の違いにより
スクリーン上では光の波の重なり具合で
ぼやけて映ってしまうのです

東北大学多元物質科学研究所・石島秋彦先生のサイトより
このぼやけてしまった真ん中の像を
Airy Disk(エアリー・ディスク)
といいます
で、分解能を考えるときには
どれくらい近い点光源を区別できるか
ということですので
2つの点光源を考えまして
それぞれの Airy Disk が
ギリギリ区別できる距離を
分解能とします
細かい計算はいいとして、、、
とりあえず、
分解能 δ は以下のようになります
δ=0.61 x λ/( n x sinθ)
ここで
λ は光の波長
n は屈折率
θ は点光源からレンズの端までの角度
大雑把にみて
0.61と n x sinθ は同程度のため
キャンセルするので
結局、分解能 δ は、
波長 λ 程度ということになるのです!
分解能 δ を小さくするには、、
sinθ を大きくする
つまり、
レンズを見る対象に近づける
もしくは、
λ を小さくする
つまり、
波長を短くする必要があります
ということで、
λ を小さくするために
光より小さい波長の電子線を使おう
というのが電子顕微鏡です
光学顕微鏡は、
光が波であるためにレンズを通すと
干渉が起きてしまい、
光の波長程度の大きさしか区別できない
というお話でした
(続く)
お読みいただきまして、ありがとうございました。
コメントもお待ちしています。お気軽にどうぞ!
私を応援していただける方は、すぐ下のリンクのクリック願います! いずれも、同時に自然科学系ブログのランキングが開いて、他のおもしろい科学系ブログにアクセスもできます。
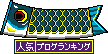
人気ブログランキングへ
にほんブログ村