アリスは友だちをつくった
- アリスは友だちをつくらない/グニラ・リン ペルソン

- ¥1,680
- Amazon.co.jp
本書の主人公アリスには親友がいました。
『赤毛のアン』のアンと同じ名前の、アンという少女がアリスの腹心の友でした。
ふたりは、いつも仲良く遊んでいたのですが、ある日、アンは交通事故で亡くなってしまいます。アンは死に、まるで鳥になって飛んで行ってしまったようなものでした。
不幸は重なるもので、今度は、アリスのお父さんの会社が破産。両親は船にのって、スウェーデン→オランダのアムステルダム→カナダ→アメリカ、という長い 船旅にでてしまいます。アリスはおばあちゃんの住むスウェーデンのストックホルムで、新しい学校に通うことになりました。(アストリッド・リンドグレーン の『名探偵カッレくん』と同じ舞台の物語ということになります。ちなみに、宮崎駿監督の『魔女の宅急便』の「コリコ」という街のモデルの一つでもあるよう です。『魔女の宅急便』って最初から最後まで通してちゃんと見たことないですけど)
アンとお揃いだった長い髪も、アンがいなくては意味がありません。
アリスは、髪を短く切りそろえ、決意をします。
「アンアリス、アンとアリス、アリスアン、アリスとアン。約束するわ、アン。わたし、友だちはつくらない。だから、どうかだれもわたしに近づいてきませんように」
アリスは、友だちをつくるまい、と転校先の学校でかたくなくに心を閉ざしてしまいます。自己紹介の場面でのアリスは、まるで『赤毛のアン』のアン・シャーリーのように、自分をSのつくアリスだと紹介します。
「わたしはアリスです」とアリスは言った。「Sのつくアリスです!」
(Eのつくアンかよ!! と思わずツッコミたくなりました……というかツッコミました)
そんなアリスの前に現れるのが、ジコルカという少年です。ジッゲと呼ばれるこの男の子は、ポーランド人の子供で、父親といっしょにトレーラーハウ スで寝起きしています。ジッゲはポーランド人であるため、スウェーデン語が流暢ではありません。このため、しばしば馬鹿にされる傾向にあるようです。ある とき、ジッゲは、ロッカーに盗んだものを隠しているのではないか、と泥棒の嫌疑をかけられます。しかし、そこに隠されていたものは、盗まれたものではな く、怪我をした小鳥でした。
アリスは、ジッゲに屋根裏の鍵を貸し、そこで小鳥を静養させることにします。これがきっかけとなって、ジッゲとアリスは友だちになっていきます。
やがて、クリスマスのコンサートの日がやってきました。アリスとジッゲは、ふたりで考えて、ローラースケートでダンスを踊ることにしました。
「アリス・チャーマーは小説家ではありません。それは黄色いパワーショベルです」
「そして、ぼくの名前はジコルカです。これはポーランド語で、意味は小さな鳥のことです」
ふたりは歌いながら、ローラースケートでステージの上を走ります。
「あなたには友だちがいる。それはわたしよ」
――と歌う、アリスとジッゲ。
そうです。
アリスには、友だちができたのです。
しかし、ジッゲは、父親の仕事の都合で街をでていってしまいます。
「きみはぼくのともだちだよ」 ジッゲ
――という手紙を残して。
そして、屋根裏部屋の鳥がついに回復し、飛び立つ日がやってきます。
「この鳥の名前はもうきめてあります。友だちのにおいがする鳥だから、友だちの名前をつけたいんです。ええ、鳥の名はアンアリスです。空へ行ってしまったのはアンだけれど、アンだけではさびしいから、わたしの名前もいっしょに」
鳥が飛びたち、アリスはハッと気がつきます。
気持ちが軽くなったような気がするのは、胸の中でこおりついていた涙がとけたせいかもしれない。
そして。
両親が帰ってきました。
また、アリスは転校することになりました。
……転校先の新しい学校へ向かうアリス。
「もう慣れちゃった」
アリスが、転校先の学校に遅刻して教室に入ると、
「アリスのスはSと書くんだよ」
と教室のどこかから声がかかります。
そこにいたのは……アリスの友だちジッゲでした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アン「友だちがいるって、いいわね」
ダイアナ「そうね」
アン「でも、アリスとジッゲは、いつまでも友だちのままでいられたのかしら? 生涯、友だち関係を維持することができたのかしら?」
ダイアナ「大人になって、友だちではいられなくなったかも知れない。そういうことは、ごく自然に考えられるとおもう」
ギルバート「僕とアンのように……? それともアンとダイアナのように……?」
アン「そうね。私とギルバートのように、恋人同士になったのなら、それはもう、友人関係とは違うわね。まして、結婚して、子供ができたとしたら。あるいは、私とダイアナのように、住む場所は違っても、心はつながった友だちのまま、生きていられたのかもしれないわ」
ダイアナ「……そうね。私とアンは、お互いを見つめ合うことはなくなってしまったけれど、それでも、お互いに、同じ方向を向いて生きているように感じるわ」
ギルバート「……なるほどね」
アン「ところで、ダイアナ。子供の頃の誓いだけれど」
ダイアナ「……?」
アン「あの、”太陽と月のあらん限り”ってところは、”太陽と月が失われようとも”に改めようかと思うのだけれど……」
ダイアナ「それはつまり、太陽(アン)が無(亡)くなっても、月(ダイアナ)が無(亡)くなっても、ふたりの友情はとこしえに続く、ということかしら」
アン「もちろん、そうよ」
ダイアナ「アン~!」
アン「ダイアナ~!」
ギルバート「じゃあ、アン。僕たちの誓いも、改めていいかな? あの”死が二人を別つまで”ってところを、是非、”死が二人を別っても”にさ!」
アン「却下よ!」
ダイアナ「却下ね!」
ギルバート「……な、何故!?」
「こんにちはアン」第4話「金色の泉」で使用された曲
- こんにちは アン オリジナルサウンドトラック1/TVサントラ
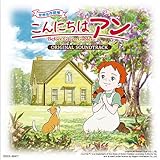
- ¥2,940
- Amazon.co.jp
- 「こんにちはアン」第4話「金色の泉」で
- 使用された曲リスト(使用曲を赤字で表示)
01. 世界名作劇場タイトル
02. ヒカリの種(TVサイズ)
03. サブタイトル
04. ノヴァスコシアの春
05. トーマス家のアン
06. 小さな瞳
07. 風を感じて
08. よかったね
09. こんにちは猫ちゃん
10. ロキンバー
11. 陽だまり
12. やさしい思い出
13. 小さな黄色い家
14. アン・シャーリー
15. 夏のきらめき
16. 朝のにぎわい
17. アンと子どもたち
18. 大さわぎ
19. 遊びの時間
20. エマーソン家
21. 秘密の部屋
22. 金色の泉
23. 想像する力
24. 秋のおとずれ
25. エリーザの恋
26. 夕映え
27. ひねくれもののミュゼット
28. 遠い調べ
29. バート
30. アンの哀しみ
31. さよならの時
32. メアリズビル
33. はじめての学校
34. よろこび
35. 月光のダンス
36. 雪景色
37. エッグマン
38. 心に翼あれば
39. クリスマス
40. 希望
41. おやすみアン
42. やったね♪マーチ(TVサイズ)
43. 予告編
注:他、詳細不明曲が1曲使用されています。
『こんにちはトリビ・アンの金色の泉』
BSフジ『We Can☆』のBGMには、『こんにちはアン』のサントラが使用されていた。2010年12月5日放送の番組では、7時35分頃『こんにちはアン』のサントラのトラック19「遊びの時間」が流された。
モンゴメリへの手紙
- 劇場版『赤毛のアン~グリーンゲーブルズへの道~』 [Blu-ray]/出演者不明

- ¥4,935
- Amazon.co.jp
「アンへの手紙」コンクール ですか。
締め切りはまだまだ先ですね。
とりあえず、下のパロディみたいなのは駄目だと思います。
さて。
今日はモンゴメリの誕生日ということで、モンゴメリへの手紙を書いてみました。
わが敬愛したてまつる師、ルーシー・モード・モンゴメリ様へ。
歓びの白い路や、きらめきの湖や、ボニーや、雪の女王のことで厚く御礼を申し上げます。
本当に感謝します。
お願いの方はあんまりたくさんあって全部言うと時間がかかるので、一番大事なもの一つだけにします。
どうか、私がプリンスエドワード島へ行けるようにしてください。お願いします。
あなたを尊敬するまぐS/Nねっとより。かしこ。
私は男なので、かしこと言うかわりに、以上といわなくてはならなかったかも知れません。
(なんのパロディかはお察しください。)
えーと、ブルーレイを買ったら、ついていたハガキにキリトリ線があってですね、それを切り取って保管しておくと、そのうち、なんかいいことがあるらしいですね。期待していますぜ。なにがあるのか解りませんが。
ところで、EDがアニメ本編とは違って、挿入歌のひとつが流れて終わってましたけれども、この劇場版で初めて”アン”に出会った人は、これを見て、続きが気になって、『赤毛のアン』を見たくなるのだろうかな? と思いました。思っただけです。余計なお世話きわまる心配とか懸念とかそういうものではありません。ただ思っただけです。しつこいな。
で、映像特典の高畑監督の「悪名高い」発言には思わず笑ってしまいました。きっと、本当に当時は大変だったんだろうなあ、と想像をめぐらせるばかりです。むろん、嗤ってはいけないのです。いろいろ参考になさった資料などもご紹介していらっしゃいましたが。いやあ、あきまへんなあ。右から左ですわ。どないしたらええんでっしゃろか。〉どうもせんでええわ!
あと、本当に最後に「おわり」って書くのは、時代を感じますです。
今日日、「おわり」って、あまりやらないんではないでしょうか。知りませんが。
赤毛のアンのアニメの魅力は、あらためて、”想像力”にあると感じました。
ここでいう”想像力”というのは、アンのめぐらす空想が、アニメーションとして動いている、ということについてです。きらめきの湖に波紋をたてて戯れる妖精とか、ああいうアニメならではの演出に、原作にはない魅力を感じました。
しかし、原作通り、と監督がいうのは、たぶん、こういった演出も含めて、高畑勲監督やスタッフが、アンを読んだときに感じたものそのものと想像しますが、つまるところ、どんな小説をアニメ化するにしても、原作通りにつくるというのは、それを読んだ読者の感じたままを具現化するのであって、原作通りではない、というのは、原作を読んだときに感じたことや想像したことではなく、別の書籍によって得た想像や知識をつぎたしているが故のオリジナル要素もとい非原作であろうと考えられます。それは、同じ作者の別作品からエピソードを流用するなども含まれるわけですが。まあ、そんなことはどうでもいいとして。ともかく、アンの”想像”がアニメーションとして動きまくるシーンというのが原作通りなのだとすれば、これはもう、読者であり表現者である監督&スタッフの皆様方が、アン・シャーリーもぞくぞくっとしてしまうであろう想像力の持ち主どもの結集であったことは、疑いの余地がないといえるわけですね。とまあ、そんなことは私が言うまでもないわけです。いまさら何をいっているんですかね、このブログは。
