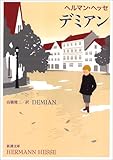津田沼で4時間ほど時間を潰さなければならない状況だったので
ヘッセの転機となった中編小説「デミアン」を一気に読みました。
主人公であるシンクレールの自己探求の物語。
第5章はまるで"ZERO" のようです。
自己発見、そして受容のプロセスにおいては、
師の存在や方法が必須だということでしょうか。
本の中に挟まれてあった紙切れ。デミアンからの返事。
鳥は卵の中からぬけ出ようと戦う。卵は世界だ。生まれようと欲するものは、一つの世界を破壊しなければならない。鳥は神に向かって飛ぶ。神の名はアプラクサスという。
P136
アプラクサスとは何でしょう?
われわれはこの名をたとえば、神的なものと悪魔的なものとを結合する象徴的な使命を持つ、一つの神性の名と考えることができる。(中略)さてアプラクサスは、神でも悪魔でもある神であった。
P139
シンクレールはアプラクサスを音楽の内側にも発見します。
町を歩いているとき、町はずれの小さな教会からオルガンの響いてくるのを2,3度聞いたことがあった。(中略)大きくはないが、いいオルガンだった。意力と粘りのある独特な極度に個性的な―祈りのように聞こえる表現を伴う、すばらしい演奏だった。(中略)私はテクニックという意味ではあまり音楽はわからないが、魂のこういう表現は子どものときから本能的に理解し、音楽的な要素を自己の内の自明な要素と感じていた。
音楽家はそれから現代のものもひいた。レーガーのものらしかった。(中略)バッハ以前の名匠や昔のイタリア人のものもまめにかなでられた。すべてが同じものを語っていた。このオルガン奏者が心にいだいていたもの、すなわち、あこがれ、世界の最も深い認識、世界への激しい告別、自己の暗い魂への熱烈な傾聴、献身の陶酔、驚異すべきものに対する深い好奇心などを、すべてが語っていた。
P146-147
シンクレールと音楽家ピストリウスの対話の中でのシンクレールの弁。
いや、ぼくは音楽を聞くのが好きです。もっともあなたのひくようなぜんぜん制限されない音楽だけです。人間が天国と地獄をゆすぶっているのが感ぜられるような音楽です。音楽は、いあtって道徳的でないから、ぼくにとって非常に好ましいのだと思うのです。ほかのものはすべて道徳的です。ぼくはそうでないものを求めているのです。ぼくは道徳的なもののためにいつも苦しむばかりでした。ぼくは自分の気持ちをよく言い表すことができません。―神と悪魔とを兼ねるような神がなければならないことをご存知ですか。そういう神があったということです。
P149-150
さらにピストリウスの弁。
ぼくたちは自分の人格の限界をいつもあまり狭く限り過ぎる。個人的に区別され異なっていると認めるものだけを、ぼくたちは常に自分の個人的存在の勘定に入れる。ところが、ぼくたちは、ぼくたちのだれもが、世界に存続するすべてのものから成り立っている。ぼくたちのからだが、魚まで、否、もっとさかのぼった所までの発展の系図を内に蔵しているように、ぼくたちは魂の中に、かつて人間の魂の中に生きたことのあるいっさいのものを持っているのだ。
P158
きみを飛ばせる飛躍は、だれでもが持っているわれわれ人類の大きな財産なのだ。それはあらゆる力の根とつながっている気持ちなのだが、いざとなると皆不安になるのだ。ひどく危険だからね!そこでたいていのものはいっそ飛ぶことを断念して、法規に従い歩道を歩くことにするのさ。
P160
自身の内側のプラスマイナスを認め、受け容れることは難しいことのようです。
ここでも「不安」という言葉があてられます。
ヘッセの転機となった中編小説「デミアン」を一気に読みました。
主人公であるシンクレールの自己探求の物語。
第5章はまるで"ZERO" のようです。
自己発見、そして受容のプロセスにおいては、
師の存在や方法が必須だということでしょうか。
本の中に挟まれてあった紙切れ。デミアンからの返事。
鳥は卵の中からぬけ出ようと戦う。卵は世界だ。生まれようと欲するものは、一つの世界を破壊しなければならない。鳥は神に向かって飛ぶ。神の名はアプラクサスという。
P136
アプラクサスとは何でしょう?
われわれはこの名をたとえば、神的なものと悪魔的なものとを結合する象徴的な使命を持つ、一つの神性の名と考えることができる。(中略)さてアプラクサスは、神でも悪魔でもある神であった。
P139
シンクレールはアプラクサスを音楽の内側にも発見します。
町を歩いているとき、町はずれの小さな教会からオルガンの響いてくるのを2,3度聞いたことがあった。(中略)大きくはないが、いいオルガンだった。意力と粘りのある独特な極度に個性的な―祈りのように聞こえる表現を伴う、すばらしい演奏だった。(中略)私はテクニックという意味ではあまり音楽はわからないが、魂のこういう表現は子どものときから本能的に理解し、音楽的な要素を自己の内の自明な要素と感じていた。
音楽家はそれから現代のものもひいた。レーガーのものらしかった。(中略)バッハ以前の名匠や昔のイタリア人のものもまめにかなでられた。すべてが同じものを語っていた。このオルガン奏者が心にいだいていたもの、すなわち、あこがれ、世界の最も深い認識、世界への激しい告別、自己の暗い魂への熱烈な傾聴、献身の陶酔、驚異すべきものに対する深い好奇心などを、すべてが語っていた。
P146-147
シンクレールと音楽家ピストリウスの対話の中でのシンクレールの弁。
いや、ぼくは音楽を聞くのが好きです。もっともあなたのひくようなぜんぜん制限されない音楽だけです。人間が天国と地獄をゆすぶっているのが感ぜられるような音楽です。音楽は、いあtって道徳的でないから、ぼくにとって非常に好ましいのだと思うのです。ほかのものはすべて道徳的です。ぼくはそうでないものを求めているのです。ぼくは道徳的なもののためにいつも苦しむばかりでした。ぼくは自分の気持ちをよく言い表すことができません。―神と悪魔とを兼ねるような神がなければならないことをご存知ですか。そういう神があったということです。
P149-150
さらにピストリウスの弁。
ぼくたちは自分の人格の限界をいつもあまり狭く限り過ぎる。個人的に区別され異なっていると認めるものだけを、ぼくたちは常に自分の個人的存在の勘定に入れる。ところが、ぼくたちは、ぼくたちのだれもが、世界に存続するすべてのものから成り立っている。ぼくたちのからだが、魚まで、否、もっとさかのぼった所までの発展の系図を内に蔵しているように、ぼくたちは魂の中に、かつて人間の魂の中に生きたことのあるいっさいのものを持っているのだ。
P158
きみを飛ばせる飛躍は、だれでもが持っているわれわれ人類の大きな財産なのだ。それはあらゆる力の根とつながっている気持ちなのだが、いざとなると皆不安になるのだ。ひどく危険だからね!そこでたいていのものはいっそ飛ぶことを断念して、法規に従い歩道を歩くことにするのさ。
P160
自身の内側のプラスマイナスを認め、受け容れることは難しいことのようです。
ここでも「不安」という言葉があてられます。