内容(「BOOK」データベースより)
山梨県で地元の有力者の一人娘が誘拐される事件が起こった。警察の指示に従った結果、身代金の受け渡しは失敗。少女は死体となって発見された!県警は、遺留品に付いていた指紋から、無実の青年を逮捕。執拗な揺さぶりで自白に追い込んでしまう。有罪は確定してしまうのか?そして真犯人は?現役の法律家が描く、スリリングな冤罪ドラマの傑作。
読み始めは・・・・・どうも文体が小説として面白みがないというか、無味乾燥な感じがしてどうなんだろうと思った。
「現役の法律家が書いた」っていうバイアスもあって、フィクションなのにノンフィクションを読んでいるような感じに捕らわれる。もっと言うなら、新人弁護士の研修の場で使われそうな、あるいは道徳の時間のテレビ番組みたいな、そんな教育的ドラマののスクリプトを読んでいるような感じ・・・。
けれど、途中からあまりの不条理さ、司法制度に潜む危うさに驚愕し、文体云々の問題はすっ飛んで、ぐんぐん引き込まれていく。
軽犯罪歴のあるチンピラがあれよあれよと言う間に殺人犯に仕立て上げられ、果ては死刑判決まで下る事態に陥る様は、読んでいて空恐ろしかった。何度も言うようだけど、これはフィクション。けれど、その中で行われる警察の尋問も、弁護士の仕事も、裁判での審理も、実際現代の日本で十分に起こりうるものなのだ。そのあたりの現実味が、「現役の法律家が書いた」という部分で、より一層恐ろしさを増す。
警察官、鑑識官、司法解剖医、弁護士、検察官、裁判官、そして被害者家族、加害者家族、容疑者自身・・・幾人もの立場の違う人間がこの事件に関わるが、彼らの誰に非があって冤罪事件は起こったのか。すべての者にあったとも言えるし、すべての者が悪意の元に行動したわけではないとも言える。「禍福はあざなえる縄の如し」という言葉を持って、作者が最終章にまとめた冤罪の起こる仕組みは、この小説を納得させるに足る説明だった。
冤罪は決して生み出してはいけない。けれど残念ながら起こりうる。制度上の問題が大きくあると思うが、結局は人の正義感が揺らぐことが一番危険なこと。裁判員制度が導入された時に、一般人の感覚を裁判に取り入れたいという趣旨があったと思うが、その意味・意義がこの小説を読んだことで本当によく理解できたと思う。すべての人にオススメしたい小説。
刑事事件に関わる上記の専門職の仕事や、容疑者逮捕後の事の流れをある程度の専門性を持ってかつ簡潔に知る事ができるという点でも読んで非常に価値のある本、と付け加えておく。
死亡推定時刻 (光文社文庫)/朔立木
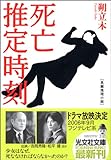
¥780
Amazon.co.jp
読了日 2010年2月26日
山梨県で地元の有力者の一人娘が誘拐される事件が起こった。警察の指示に従った結果、身代金の受け渡しは失敗。少女は死体となって発見された!県警は、遺留品に付いていた指紋から、無実の青年を逮捕。執拗な揺さぶりで自白に追い込んでしまう。有罪は確定してしまうのか?そして真犯人は?現役の法律家が描く、スリリングな冤罪ドラマの傑作。
読み始めは・・・・・どうも文体が小説として面白みがないというか、無味乾燥な感じがしてどうなんだろうと思った。
「現役の法律家が書いた」っていうバイアスもあって、フィクションなのにノンフィクションを読んでいるような感じに捕らわれる。もっと言うなら、新人弁護士の研修の場で使われそうな、あるいは道徳の時間のテレビ番組みたいな、そんな教育的ドラマののスクリプトを読んでいるような感じ・・・。
けれど、途中からあまりの不条理さ、司法制度に潜む危うさに驚愕し、文体云々の問題はすっ飛んで、ぐんぐん引き込まれていく。
軽犯罪歴のあるチンピラがあれよあれよと言う間に殺人犯に仕立て上げられ、果ては死刑判決まで下る事態に陥る様は、読んでいて空恐ろしかった。何度も言うようだけど、これはフィクション。けれど、その中で行われる警察の尋問も、弁護士の仕事も、裁判での審理も、実際現代の日本で十分に起こりうるものなのだ。そのあたりの現実味が、「現役の法律家が書いた」という部分で、より一層恐ろしさを増す。
警察官、鑑識官、司法解剖医、弁護士、検察官、裁判官、そして被害者家族、加害者家族、容疑者自身・・・幾人もの立場の違う人間がこの事件に関わるが、彼らの誰に非があって冤罪事件は起こったのか。すべての者にあったとも言えるし、すべての者が悪意の元に行動したわけではないとも言える。「禍福はあざなえる縄の如し」という言葉を持って、作者が最終章にまとめた冤罪の起こる仕組みは、この小説を納得させるに足る説明だった。
冤罪は決して生み出してはいけない。けれど残念ながら起こりうる。制度上の問題が大きくあると思うが、結局は人の正義感が揺らぐことが一番危険なこと。裁判員制度が導入された時に、一般人の感覚を裁判に取り入れたいという趣旨があったと思うが、その意味・意義がこの小説を読んだことで本当によく理解できたと思う。すべての人にオススメしたい小説。
刑事事件に関わる上記の専門職の仕事や、容疑者逮捕後の事の流れをある程度の専門性を持ってかつ簡潔に知る事ができるという点でも読んで非常に価値のある本、と付け加えておく。
死亡推定時刻 (光文社文庫)/朔立木
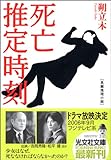
¥780
Amazon.co.jp
読了日 2010年2月26日