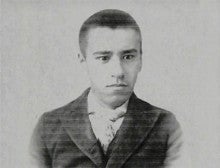2010 / 3 / 26 「僻地温泉」 について講義する山田べにこサン。
〓今年、3月26日の深夜、 TBS の
「新知識階級クマグス」
をネハンブツ (涅槃仏) よろしく寝っ転がってボーッと見ておりました。でね、思わぬキャラの出現に色めき立ちました。最後は正座して見ておりましたよ。
〓その出色のキャラこそ、今や、知るヒトぞ知る、はたまた、知らないヒトは “ナンじゃそりゃ” の
山田べにこ ![]()
さんですわいな。
![]()
![]()
![]()
〓「クマグス」 ってコトバに耳ナジミのないムキもござりましょう。“クマグス” というのは、日本の博物学の巨人 「南方熊楠」 (みなかた くまぐす) のことでありんす。
〓博物学 (はくぶつがく) natural history / historia nātūrālis というのは、近代までの学問のジャンルで、現在の 「生物学」 (動物学・植物学)、「鉱物学」、「地質学」 などをオールマイティにこなす学問でした。
〓学問のタテワリが進む以前の 「広汎な知識を必要とした学問」 でした。そういえば、「言語学」 linguistics もかつては 「博言学」 philology と呼ばれておりましたよ。
〓南方熊楠という名前はヘンテコですが本名です。和歌山の生まれなので、熊野本宮大社 (くまのほんぐうたいしゃ) の神木の楠 (くすのき) にちなんだ、と言います。
〓まさに幕末の幕末、明治が始まる前年の生まれで、昭和天皇と同じく “粘菌” (ねんきん) の研究で有名です。「粘菌」 というのは、みずから動き回る菌類で、
動物のようで動物でなく、植物のようで植物でない
それはナニかと尋ねたら、あ、ネンキン、あ、ネンキン、というフシギな生物です。
〓つまり、「クマグス」 という呼び名はですね、オタクという呼び名では片づけられないような
顕微鏡的に物事に凝るヒト
を指すらしいんすよ。
![]()
![]()
![]()
〓 3月26日の 「グマグス」 は、
僻地温泉のクマグス
でした。
〓つまり、気軽にクルマでヒョイと行けるような温泉ではなく、ササヤブを漕 (こ) いだり、滝や崖を登ったりして、ようやくたどり着けるような、秘湯とさえ呼ばれないような珍湯をたずね、ひとっ風呂あびてくるのが趣味というヒトなんすね。
〓 番組の MC は TBS の局アナにして、酒豪とのウワサを取り、番組ゲストの放つシモネタなんぞキントウンのごとくにあしらう 「竹内香苗」 (たけうちかなえ) アナウンサーでございますよ。
〓でね、番組のレギュラー出演者である V6 が、この 「山田べにこ」 さんにゲキハマリなわけです。「クイツイタ、クイツイタ、クイツイタ」。
【 山田べにこサン、登場 】
〓むむ~、アッシャあ、この僻地温泉のクマグスこと、
僻地温泉をもとめて海山をめぐる 「山田べにこ」 さん
にホレテしまったのですよ。ふだんは OL だそうで。現在28歳。二十歳のときから温泉巡りをやっているといい、いつも単独行だそうです。
いっしょに行ってくれるヒトがいないから
とのこと。
〓美人サンではないが、チャーミングであります。いかにも “山女” (やまおんな) という風貌でもありません。
〓登山をしないヒトにはピンと来ないであろうけれども、山には20代・30代の女性は絶えて居ない。アッシが25年前に山に登り始めたころからそうなんですね。まあ、オトコでも若いのは少ない。アッシらなんぞ、山小屋でオバサマたちに珍しがられて、オモチャにされたもんでした。
〓あるいは、このセツ、富士山や高尾山に登ったヒトは、山にも若い女性はいるよ、と言うかもしれない。しかし、それは、ひとり、最近の富士山と高尾山にかぎったことで、一時的な流行りでげすよ。一過性のブーム。他の山には、低山であろうと、高山であろうと、いないものはいない。
〓そして、たまに若い女性がいると、それは、アッシら登山仲間が名付けたところの
“ヤマオンナ”
なのです。つまり、単独行で、たくましく、日焼けして、体型と言えば 「アスリートタイプ」 で、オンナッケさらになし。
〓べにこサンは、山登りでなく、僻地温泉行 (コウ) が趣味なんですが、僻地温泉へのルートというのは、あきらかに、
フツーの登山道よりも 「さびれて、ササに覆われ、
迷いやすく、人跡絶え、薄気味悪く、歩きにくい」
にちがいないんですね。そういうルートをこういうオネエサンが歩いているのか、と思うと、ちょいと、ゾクゾクッとするわけですよ。
〓べにこサン、やっていることのスゴサに比べると、外見・容貌は、むしろ、マギャクのテンネン系。声はアニメ声で、じゃっかん、落ち着きがなく、ウッカリものです。
〓う~ん、いっしょに山に行くなら、こういうヒトと行きたいなぁ、と。 ![]()
![]()
![]()
![]()
〓番組では、スタジオに、温泉行の際の装備一式をならべて見せてくれたんですが、これがスゴイ。ただごとじゃない。
山歩きの装備一式 (ザックとか、そういうもの)
+
キャンプの装備一式 (炊事用の食器、火器、テント、寝袋など)
+
写真撮影の道具一式 (カメラ、三脚など)
+
風呂道具一式 (プラスチックおけ、簡易浴槽にする巨大なブルーシート)
+
クマ避けスプレー、クマ避け鈴、GPS受信機、ガスマスク、PH計など
〓ありえへん。まあ、行く先によって装備は選ぶとは思うけれども、これ、フルで背負ったら、極力、軽量化しても、60キロは超えると思う。米一俵の重さですよ。
![]()
![]()
![]()
〓「山田べにこ」 というのはペンネーム。実家のイヌの名が “べにこ” なんだそうです。このヒトの HP はココ。
http://www2.ocn.ne.jp/~veniko/index.html
〓 URL からすると、本来、「山田ヴェニコ」 なんだろうか。
【 山の中の地名はヘンなのが多い 】
〓ハナシは変わりますでゲスが、地名というのは妙なもので、人の住んでいない山の中にもあります。
〓樵 (きこり) が名付けたもの、猟師が名付けたもの、登山家が名付けたもの、あるいは、里の人たちが 「麓から見た姿」 で名付けたものなど、いろいろあります。
〓方言なのか、あるいは、単に符丁みたいなものなのか、はたまた、古語なのか、ときどき、奇妙な地名に出くわすことがあります。
〓たとえば、山では、
乗越 (ノッコシ)
という地名によく出会います。
〓山では、峠とか、尾根の鞍部 (アンブ=いちばん低い箇所) に 「○○のノッコシ」 とか、単に 「ノッコシ」 という地名が付いていることが多いのです。これは 「乗り越し」 の音便形です。
〓「乗り~」 で音便形を取るものには、日常語で、
乗っかる (←乗りかかる ?)
乗っ取る (←乗り取る)
などがありますが、古語・方言・専門用語には、「乗っ切る」、「乗っ込む/乗っ込み」、「乗っ付ける」、「乗っ伏せる」 (~ぷせる) などがあります。
〓現代標準語では、「乗り越す」、「乗り越し」 を 「のっこす」、「のっこし」 とは言いません。しかし、山の地名にはこれが残っているわけです。
〓今では、バスや電車で目的地を越えてしまうことを 「乗り越す」 と言いますが、これは明治時代後期からの用法で、本来の意味は、「物を乗り越える」、「乗り物 (駕籠・馬) で他者を追い越す」、「他者の地位・身分を追い越す」 という意味でした。
〓つまり、“峠を越える” というのは、「乗り越す」 のいちばん古い語義なんですね。江戸ッ子なんぞにとっては、峠を越えるなんて体験じたいが、日常、皆無なので、標準語には残らなかったんでしょう。普通の国語辞典には 「のっこし」 は出ていません。
〓逆に言うと、文語に残らず、地方の口語 (方言) にのみ残ったので、「乗り越し」 ではなく、「乗っ越し」 となるんでしょう。
![]()
![]()
![]()
〓尾根の鞍部を 「コル」 と呼ぶ場合もあります。「~のコル」 ってヤツ。たとえば、北アルプスには 「天狗のコル」 なんてところがあります。チョイと聞くとヘンな名前です。これは、登山家が名付けたもの。フランス語です。
〓つまり、地元の人たちが古くから歩いていた道筋につけられた名前が 「ノッコシ」 で、明治以降、登山というスポーツが日本に導入されてのち、登山コースにつけられた名前が 「コル」 となるんです。
〓これは、
col [ 'kɔl ] [ ' コる ] ビンのクビ、衣服の襟、物のくびれた部分、峠・鞍部。
というフランス語に由来します。つまり、“山の稜線のくびれ” という意味でしょう。
〓フランス語には、
cou [ 'ku ] [ ' クゥ ] 頸 (くび)。
という単語もあります。
〓どちらもラテン語の collum [ ' コッるム ] 「頸」 (くび) に由来するもので、フランス語における、その最初の用例は、
col [ ' コる ] 1080年初出
でした。
〓しかし、古フランス語には、当時、きわめて退化したとは言え、格変化が残っており、2格 (主格/斜格) と2数 (単数/複数) を区別しました。ゆえに、
cols [ ' コるス ] 「クビは」。単数主格
col [ ' コる ] 「クビを」。単数斜格
だったんです。
〓しかし、古フランス語の後期に、子音の前にある L が [ w ] に変化しました。同じような変化が、現代では、ブラジルポルトガル語やポーランド語で観察できます。あるいは、英語でもぞんざいな発音では feel, people といった単語の、いわゆる dark L [ ɫ ] が [ w ] 化します。「フィーオ」、「ピーポー」 ですね。
〓古フランス語でこうした変化が起こったため、単数主格が、
cous [ ' コウス ] 「クビは」
となりました。
〓古フランス語で格変化が消滅すると、通例は、斜格形が残りました。すなわち、 col が残るハズでした。しかし、この単語の場合は、
cols [ ' コるス ] → cous [ ' コウス ] → cou [ ' クゥ ] 「頸」 (くび)
col [ ' コる ] → col [ ' コる ] 「服の襟、ビンのクビ、物のくびれ」
というふうに “意味が分化した” んでゲス。
〓英語の collar 「襟」 (えり) は、ラテン語 collum の派生形 collāre [ コッ ' らーレ ] 「襟、首輪」 がフランス語を経由して入ったものです。
〓 collum [ ' コッるム ] から -āris で派生する形容詞が、
collāris, -is, -e [ コッ ' らーリス、~リス、~レ ] 「頸に関係する」
です。 -āris は、本来、 -ālis であり、英語の形容詞 final, national などに現れる -al と同じものですが、
語幹に l が含まれる場合に、異化 (いか) を起こして -āris となる
のです。「異化」 は先だって grammar と glamour でやりましたネ。
〓この形容詞の中性形が collare [ コッ ' らーレ ] “頸に関係するもの” です。
〓ただし、古フランス語 colier [ コり ' エル ] に対して、英語に入ったのは、英国の支配階級の使っていたフランス語、「アングロフレンチ」 の coler [ コ ' れル ] でした。中期英語では colēr [ ' コれール ]。異綴は coller, col(l)ar, culer。 現代英語の綴り collar はラテン語の原綴 collare を復元したものです。
【 「ニュウ」 の話 】
〓ヘンな山の地名のハナシをもう1つ。
〓八ヶ岳 (やつがたけ) を北上して行くと、南北の八ヶ岳を区切る麦草峠 (むぎくさとうげ) の手前に
ニュウ
という名前の岩があります。これは地図にも 「ニュウ」 と書いてある。たぶん、八ヶ岳を歩いた人なら、たいてい一度は、「ニュウ」 ってナンだろう? と思ったはずです。
岩がニュウっと突き出ているからか?
なんて考えたりします。
〓登山道を歩いていると、道案内の立て札に、
乳 (ニュウ)
と書いてあるので、たいていのヒトは、そうか、「オッパイ」 に似た岩ということか、とナットクしてしまいます。しかし、この岩、とくにオッパイに似ているわけではありません。
![]()
![]()
![]()
〓福井県に 「丹生」 (にゅう) という地名があります。これは、
【 丹 】 [ ニ ] “辰砂” (しんしゃ=硫化水銀 HgS から成る鉱物)
+
【 生 】 [ フ ] “ある種の植物・鉱物などを産する場所” を意味する接尾辞
↓
【 丹生 】 [ ニフ ] “辰砂の産地”
という地名です。
〓単純に、「芝の生えている場所」 が “芝生”。 12世紀から用例があります。
〓地名で言うと、川崎の “麻生” (あさお) は 「麻が生えている場所」。そして、この麻生には “柿生” (かきお)、「柿の生えている場所」 もあります。
〓「生」 (ふ) は接尾辞なので、 h 音が語中に立つことになります。日本語は、語頭以外の h 音が脱落したので、次のような変化が起こりました。
【 丹生 】 ニフ → ニウ → ニュー
【 瓜生 】 ウリフ → ウリウ → ウリュウ ※食用になる 「マクワウリ」 の生えている場所の意。地名・名字に多い。
【 麻生 】 アサフ → アサウ → アサオ ※川崎の地名の場合
→ アソー ※名字の場合
――――――――――――――――――――
【 芝生 】 シバフ → シバフ
〓“芝生” の場合も、「シバウ」 という発音を生じたようですが、けっきょく、残ったのは 「シバフ」 という音でした。合成語であることが意識される場合、あるいは、 h を落とすことで不都合が生じる、と感じられた場合は、日本語でも h 音が残りました。
【 ごはん 】 [ ご飯 」 「ご+はん」 とわかるので 「ごあん」 とはならない。
【 はは 】 [ 母 ] 江戸初期の 『日葡辞書』 には、 Fafa 「ファファ」、 Faua 「ファワ」 の両形がある。
歌舞伎が好きなヒトなら、「ハワサマ」 という発音をよく聞くだろう。
しかし、けっきょく、生き残ったのは 「ハハ」 (←ファファ) だった。
【 あふれる 】 [ 溢れる ] 「あうれる」 という発音は生じなかった。むしろ、 h を強化した 「あぶれる」 が生じ、別語として分岐した。
〓では、八ヶ岳の 「ニュウ」 は “丹生” と関係あるのか、というと、そうではありません。八ヶ岳のニュウで 「辰砂」 が採れた、などという記録はないようです。
![]()
![]()
![]()
〓実は、長野県の佐久 (さく) あたりの方言に面白いコトバがあるんすよ。
【 にゅう 】 刈り取った稲を円錐形に高く積み上げたもの。稲むら。
〓おそらく、「ニュウ」 というのは形から言ってもこれでしょう。
〓本来の語形は、
【 にほ 】 [ 堆 ]
と言います。
ニホ → ニオ (→ ニウ → ニュー)
という変化ですね。
〓「稲堆」 (いなにお)、「藁堆」 (わらにお) などとも言い、方言には、実に、さまざまな語形があります。
イナニエー 飛騨
イナニョ 富山県
ニエ 三重県志摩郡
ニオ 青森県津軽、岩手県上閉伊郡、新潟県、福井県、山梨県、長野県佐久、
岐阜県北飛騨、滋賀県甲賀郡、和歌山県東牟婁郡
ニオニオ 三重県一志郡
ニゴ 山梨県、長野県
ニゴボーズ 愛知県東加茂郡
ニュー 群馬県伊勢崎市・勢多郡、福井県、長野県佐久、静岡県賀茂郡、滋賀県
ニヨ 青森県南部、秋田県、新潟県中頸城郡、長野県佐久、和歌山県東牟婁郡
ニョー 山形県米沢市、富山県西礪波郡、福井県、山梨県、長野県、岐阜県吉城郡、静岡県
ニヨシ 山梨県中巨摩郡
ノ 千葉県印旛郡
ノー 茨城県、栃木県河内郡、千葉県、島根県鹿足郡、山口県玖珂郡
ノーグロ 山口県玖珂郡
ノーツンバ 茨城県稲敷郡
ノーボッチ 茨城県稲敷郡
ミョーブラ、ミョーツンブラ 静岡県富士郡
※「ミョー」 は 「ニョー」 の転訛。「ブラ」 は “稲叢” (いなむら) の “ムラ” の転訛
ワラニグ 飛騨
ワラニョ 岩手県
ワラニョー 静岡県
ワラネ 飛騨
ワラノー 茨城県
〓フダンならば、ヨーロッパの言語について説明するような 「多彩な音変化」 が見られます。たとえば、
ニホ → ニゴ、ニグ
というのは、「ニオ」 となってしまうと、聞き分けづらいコトバになってしまうことを恐れて、逆に、 h を脱落させずに g に強化したもの、でしょう。とてもオモシロイ例です。
〓また、静岡県富士郡に見える 「ミョー」 というのは、 n と m の交替です。これは、やはり、世界中の言語にときどき見えるもので、たとえば、ギリシャ語で、
Νικόλαος Nīkólāos [ ニー ' コらーオス ] 「ニーコラーオス」
というと、4世紀、小アジアの司教で、サンタクロースのモデルとなった人物の名前ですが、この名前はヨーロッパの諸言語でこんなふうに男子名として採用されています。
Nicholas [ ' ニクらス ] 英語 ※ -ch- は c と ch を混同したラテン語綴りに由来する
Nicolas [ ニコ ' ら ] フランス語
Николай Nikoláj [ ニカ ' らーイ ] ロシア語
――――――――――――――――――――
Mikołaj [ ミ ' コワイ ] ポーランド語
〓ご覧のとおり、ポーランド語で、 N → M という置き換えが起こっています。
〓また、関東各地に 「ニョー → ノー」 という変化が見えます。以前、何度か申し上げた 「直音化」 (ちょくおんか) ですね。主として、関東に見られる、というところが、とても興味深い。
〓八ヶ岳の 「ニュウ」 にいちばん近い大きな町は佐久です。甲州街道の側の 「茅野」 (ちの) や 「諏訪」 となると、山の反対側になってしまうんですね。
![]() 毎度おなじみ、「2」 に続きます。 ↓
毎度おなじみ、「2」 に続きます。 ↓