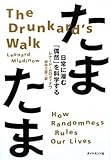信号が赤のときに、それを無視して車で突破するとどうなるか。容易にわかるように、かなり高い確率で事故を起こす。もし1回目で事故を起こさなくても、それを繰り返せば、いつかは事故を起こす。これは容易にわかる。
では、信号が黄色に変わったときに、スピードを出して車で突破するとどうなるか。赤信号を無視する場合ほどではないが、やはり事故を起こす確率は上がる。1回目、100回目、1000回目に事故を起こさなくても、1001回目に事故を起こすかもしれない。
以上、2つの場合は、事故を起こす確率が高いか低いかの違いで、本質は同じである。回数(確率の言葉で試行という)を繰り返せば、いつかは事故を起こす。これは、確率論の分野で大数の法則と呼ばれる法則による。
では、なぜ赤信号では止まるのに、黄色の信号ではスピードを上げて突破しようとするのだろうか(なお、どちらも違反である)。この疑問は、「少数の法則」と呼ばれる考え方で説明できる。
少数の法則とは、確率論の定理ではなく、マーフィーの法則のような警句である。数が大きくないのに大数の法則を使おうとする見当違いの行為を皮肉を込めて呼んだ言葉だ。(「たまたま」、レナード・ムロディナウ著、ダイヤモンド社、p.150)
黄色でスピードを出して、100回連続で事故を起こさなかったとする。そうすると、その運転手は、「黄色で突っ切っても事故は絶対に起きない」と確信してしまう。すなわち、100回の試行で、事故を起こす確率を0と判断してしまうのである。しかし、その確率が本当は0.1パーセントだった場合、100回連続で事故を起こさない確率はおよそ90パーセントであり、9割の人はその 0.1 パーセントという小さな確率を認識できない。しかし、1000回連続で事故を起こさない確率は、約37パーセントであり、それまでに6割の人は1回以上事故を起こす。
このようなことは、信号無視に限らず、いくらでもある。スピードオーバー、無理な追い越し、歩いている時の信号無視、自転車の片手走行など、これまでの人生で一度も事故を起こさなかったからといって、事故を起こす確率が0になっているわけではないのである。無謀な運転でこれまで事故を起こさなかったからといって、そのドライバーの腕が良いわけでもない。ただ単に、運がよかっただけである。
交通ルールを守るのは、そのような少数の法則による誤解から身を守るためである。単に違反切符を切られないようにするためではない。
たまたま―日常に潜む「偶然」を科学する