RepeCa〜連続復習 Repeat Card〜 (暗記カードに復習機能をプラスしたアプリ)
今回は、”私が京都大学に合格した時に行っていた方法” を公開してしまいます。
上のアプリはここで紹介するアナログな復習管理方法をデジタルに置き換えたものです。
****************************
(以下、過去記事を含みます。)
大学受験に苦戦した私が、実際に行って効果があった復習管理の方法を公開します。
(※ 復習の方法の "一例" としてご覧下さい。)
下の写真です。
以前の記事:「なぜ復習を4回に分け、連日こなすと続くのか?」 で紹介したように、達成度を4段階に分けて、ある期間、なるべく連日、連続して復習をしています。厳密には4日連続ではないですが、復習管理をしている画像です。上の画像の鉛筆書きの部分です。これは、物理の標準的なレベルの問題集で、復習システムを使った問題集管理を行っています。
画像では、一日目は10月8日に学習したけれど、あまりにテキトーだったので、3日後の10月11日にきちんとやり直し、そこで達成度1を付けています。翌日、達成度2の復習を行い、一日空いたので、10月14日にも達成度2の復習を行い、15日にようやく達成度3を付けています。最後の復習から数ヶ月おいて大学入試(二次試験)直前の2月10日に、総復習を兼ねて見直しの復習をしています。画像中には書かれていませんが、これが4段階目です。
本来は総復習を行うより前に4段階まで達成しておき、スピード化までしておくのが理想ですが、継続することを重視するため、このように大雑把です。
****************************
連続復習をすると効果は絶大でした。
画像は物理の標準レベル問題集ですが、みっちり復習することで、東大物理の応用問題も解けるようになりました。(※ 別に演習も必要です。演習もこの復習で意識して記憶に残しました。)
復習すると記憶の再現スピードと共に正確さも上昇するので、応用するときの知識や応用するときの時間的・心理的余裕も増大します。それまでの「一夜漬け」とは全く比にならない記憶力、応用力が付きました。これまで「やりっぱなし」で失っていた記憶を、強固な記憶として試験本番までストックすることができたのです。直前の総復習でも、これ以外に4段階まで達成した "復習ストック" を含めて短時間で見直すことにより、さらなる得点力の増強が実現し、自信を持って本番に臨めました。
問題集の余白に日付と達成度をチェックしておくだけで、4段階の復習を適用し、連日行うことで記憶に残す "復習システム" が出来上がります。最も記憶に残る方法で、負荷を分散し、やる気が持続し、継続できる "仕組み"を作るのです。
「大雑把」でも、「テキトー」でも構いません。復習しないと残りません。大雑把でもテキトーでも「繰り返し」は効きます。
大雑把ではありますが、いや、大雑把であるからこそ続けられる、そんな例として上の画像を紹介しました。
(※ きちんと4日連続で一通りの復習を終えている記録もあります。)
このような(別の方法でも構いませんが)復習チェックを習慣にしておくと、復習の計画をその都度特別に考える必要はなくなり、ただ日付と達成度をメモしておくだけで済みます。
****************************
使用した問題集:
注:旧版 名問の森物理 (電磁気・熱・原子) (河合塾SERIES)/河合出版
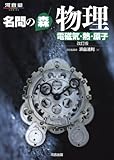 ¥1,050 Amazon.co.jp
¥1,050 Amazon.co.jp
新版:名問の森物理 波動2・電磁気・原子 (河合塾シリーズ)
 ¥1,100 Amazon.co.jp
¥1,100 Amazon.co.jp
****************************
ちなみに、達成度の数字の上にある「カ」というのは、学習の「形態」のメモです。
すべての問題を解き直すのに、紙と鉛筆ですべてを「書き直し」していると、膨大な時間と労力を消費し、他の勉強ができなくなります。何より、めんどくさいし、退屈だし、疲れます…。
そこで、暗記カードの様に、問題を読んだら答えを見ずに、"頭の中で "解法を順序立てて再現します。なるべく丁寧さを心がけます。手を動かしたりしてイメージすることもあるでしょう。人間は、書かなくても視覚イメージがある程度できるし、黙っていても頭の中で音声を再生することができます。そしてそのスピードはリアルよりも速いし、疲れも少ないです。
これを利用します。
この復習の方法が、暗記カードで学習しているときに近いので、"カード型" と(私なりに勝手に)名付け、その頭文字であるカタカナの「カ」をとってメモしていました。時間がある時や、正確にチェックしたい時は「書く」復習をするので、ひらがなの「か」をメモしていました。
後から復習記録を振り返ると、きちんと「書いて」復習したのか、頭の中で「カード型復習」をしたのか一目瞭然です。それに応じて以後の学習の方法や強度を対応させることができます。
…私はめんどくさがりなので、カタカナの「カ」ばかり並んでいますが…
**************************
ともあれ、復習のシステムに記憶の管理を任せ、一回一回の学習は「カ」で済むようなラクなものにして、達成感の脳内物質で気分を上昇させながら、ゲームのように楽しく勉強を続けることができます。この復習管理法により、記憶の管理と気分の上昇、やる気の持続が可能になります。"トータル" で負荷と時間を削減し、"トータル" で記憶の質を向上し、続けるための気分の上昇も見込める方法です。
"根性” では記憶に残らないから、復習に分散させる。
効率を上げるため、復習システムに任せる。
自分は今やることだけ、やればよい。続ければ良い。
…このように考えると、長期戦の試験勉強では気が楽になり継続しやすくなります。
(※ 達成度や、難易度はぜひ自分用にカスタマイズして下さい。)
**************************************
新アプリ「RepeCa〜連続復習 Repeat Card〜」が「復習管理ノート」の後継アプリとして公開されました。
上記のアナログな復習方法をデジタルに埋め込んだアプリの第二弾です。
暗記カードに復習機能をプラスしたアプリです。
カメラで暗記カードを素早く作り、4日連続+1ヶ月後の復習をします。
復習予定は自動作成・自動更新。
全体の成果をグラフでひと目で確認できます。
※暗記カード5枚分は無料。
















