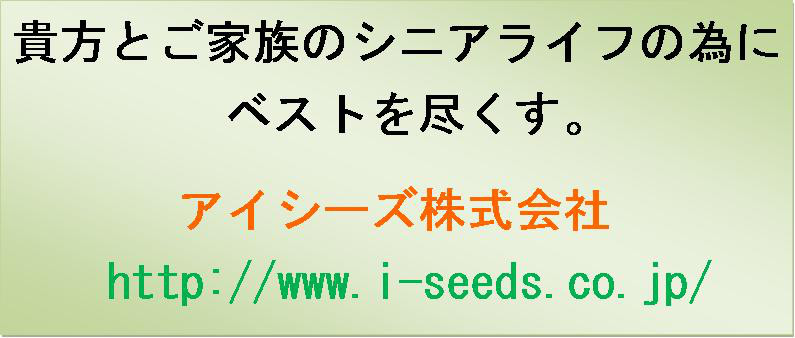以下、CB news 様より引用させていただきました。
ありがとうございます。
生活保護の7000人弱が高齢者向け未届け施設に―厚労省
厚生労働省は10月20日、社会福祉法などの法的な位置付けのない未届け施設に入所する生活保護受給者のうち、「要介護の高齢者を対象とした施設」や「高専賃(有料老人ホームは除く)」への入所者が6879人に上ったとの調査結果を発表した。
厚労省は今年1月、都道府県や指定都市などに対して調査を指示し、各自治体が1月1日時点の施設数や入所者の数を調べた。厚労省はこの結果を集計した4月に中間報告を行っており、同日までに重複して数えられている人の名寄せを行うなどの精査を行った結果を公表した。
調査によると、老人福祉法や社会福祉法になどに法的な位置づけのない未届け施設に入所する生活保護受給者は、全国で1万2587人(4月の報告では1万 4268人)に上った。このうち、要介護高齢者を対象とした施設への入所者は4339人、高専賃(有料老人ホームは除く)への入所者は2540人だった。 施設の数はそれぞれ、582施設、243施設だった。
また、生活保護費を支給している自治体がある都道府県以外の施設に入所している人は、全国で572人だった。このうち、東京都内の自治体から都外の施設に入所している人が517人に上り、全体の9割を占めた。
生活保護をめぐっては、厚労省が10月7日に、昨年度の「社会福祉行政業務報告の結果の概況」の中で、昨年度1か月平均の受給者が159万2620人に上るとの結果を発表している。
厚生労働省の管轄による建築物及び介護サービスの監査対象
と、ならない未届け施設・・・
なぜ存在するのか?
それは、「需要」が有るからである。
そして、この場合の「需要」とは、
対象者及び支援者が限りなく困窮した末の
「避難」 「救済」 の場所である。
さて、ここでのポイント。
「無届け」 と 「未届け」
大切な、人の命と生活を守るサービスを提供する以上、
今後も含めた施設運営方針の定まらぬ前者は、
正義であるとは言い難い。
一方、後者の中にも極めてグレーな施設が存在するが、
スプリンクラー設置や外部介護サービスの連携を充足させ
将来、有料老人ホーム申請への転換を具体的に見据えている施設も
少なくはない。
現状では 「未届け」 の施設が、今後どのように進化していくのかを
希望を持って 「見届け」 たいものである。
ありがとうございます。
生活保護の7000人弱が高齢者向け未届け施設に―厚労省
厚生労働省は10月20日、社会福祉法などの法的な位置付けのない未届け施設に入所する生活保護受給者のうち、「要介護の高齢者を対象とした施設」や「高専賃(有料老人ホームは除く)」への入所者が6879人に上ったとの調査結果を発表した。
厚労省は今年1月、都道府県や指定都市などに対して調査を指示し、各自治体が1月1日時点の施設数や入所者の数を調べた。厚労省はこの結果を集計した4月に中間報告を行っており、同日までに重複して数えられている人の名寄せを行うなどの精査を行った結果を公表した。
調査によると、老人福祉法や社会福祉法になどに法的な位置づけのない未届け施設に入所する生活保護受給者は、全国で1万2587人(4月の報告では1万 4268人)に上った。このうち、要介護高齢者を対象とした施設への入所者は4339人、高専賃(有料老人ホームは除く)への入所者は2540人だった。 施設の数はそれぞれ、582施設、243施設だった。
また、生活保護費を支給している自治体がある都道府県以外の施設に入所している人は、全国で572人だった。このうち、東京都内の自治体から都外の施設に入所している人が517人に上り、全体の9割を占めた。
生活保護をめぐっては、厚労省が10月7日に、昨年度の「社会福祉行政業務報告の結果の概況」の中で、昨年度1か月平均の受給者が159万2620人に上るとの結果を発表している。
厚生労働省の管轄による建築物及び介護サービスの監査対象
と、ならない未届け施設・・・
なぜ存在するのか?
それは、「需要」が有るからである。
そして、この場合の「需要」とは、
対象者及び支援者が限りなく困窮した末の
「避難」 「救済」 の場所である。
さて、ここでのポイント。
「無届け」 と 「未届け」
大切な、人の命と生活を守るサービスを提供する以上、
今後も含めた施設運営方針の定まらぬ前者は、
正義であるとは言い難い。
一方、後者の中にも極めてグレーな施設が存在するが、
スプリンクラー設置や外部介護サービスの連携を充足させ
将来、有料老人ホーム申請への転換を具体的に見据えている施設も
少なくはない。
現状では 「未届け」 の施設が、今後どのように進化していくのかを
希望を持って 「見届け」 たいものである。