(26) ジェルジ・リゲティ(1926-2006):無伴奏ヴィオラ・ソナタ(1991/94)(増補)
第二次世界大戦後の前衛音楽を担ったピエール・ブーレーズ、カール・ハインツ・シュトックハウゼン、ルチアーノ・ベリオらヨーロッパの主流に対して、1960年代、ヨーロッパの周縁から刺激を加えてきたひとりが、ハンガリーのジェルジ・リゲティである。リゲティというと一定音域を音でべったりと埋め尽くすトーン・クラスターがトレードマークだったが、晩年には民謡への参照を強めた。無伴奏ヴィオラ・ソナタはこの時期のものでヴァイオリン協奏曲やピアノのための練習曲第2巻、ナンセンス・マドリガルと語法上の共通性を持つ。
ヴィオラという楽器について、「木と大地とタンニン酸を思い出させる」C線しか好きではなかったリゲティだったが、1990年にタベア・ツィンマーマンの演奏を聴いてひどく魅了された。「きめが粗く、目覚ましいが、常に優しい」G線のよさにも開眼したのだという。1991年、ウニフェルザル出版の社長アルフレート・シュレーの90歳祝いのために、アーディッティ弦楽四重奏団あるいはそのメンバーの演奏する小品が何人もの作曲家に委嘱され、1枚のCDが作られたが、この時、リゲティはヴィオラ・ソロのための《ループ》という曲を書く。これは当時アーディッティ弦楽四重奏団のヴィオラ奏者だったガース・ノックスが初演した。翌年、彼の教師だったシャーンドル・ヴェレシュの追悼に《ファスカール》が書かれる。1994年に至り、ここにさらに4曲が書き足されて、6楽章の無伴奏ヴィオラ・ソナタが完成し、タベアに献呈され彼女が初演した。
一番テンポの速いノックス盤が20分弱、遅いタメスティット盤が23分ほど。ゆっくりした楽章と早い楽章が交互に配置されている。性格的小品の寄せ集めのようでありながら、リゲティの個性に染め上げられて一貫性がある。技巧的には難しいが、音楽の作りは単純と作曲者は述べるが、そこにはリゲティ一流のパラドックスが仕掛けられている。
第1楽章〈ホラ・ルンガ〉は「ゆっくりした舞曲」の意。これはC線のみで弾かれる。最初はC線の普通の音域で民謡風の旋律が歌われる。明白な引用ではないものの、ルーマニアのカルパティア山脈北方の民謡の性格を持ったものだという。ゆっくりとした定型的な旋律素材がつなぎ合わされていくもの。しかし最初の数音ですでに微分音程のずれがあって、とても奇妙である。もっともこれは民謡自体が西洋的な平均率に則っていないことを反映しているのだろう。リゲティはヴィオラのC線のさらに下にF線があるものと想定し、そのF線の第5、第7、第11倍音が作る、平均率とずれた音程を使用しているのだという。この架空の民謡の旋律はしまいにはC線のハーモニクスまで使って非常に高い音程まで登っていく。最後はまるで極限的な音程。第2楽章〈ループ〉は奇妙なスイング感を持った早い楽章。タメスティットはジャズの精神を持って演奏すべきという。基本的なテンポは変わらないので、どんどんテンポが上がっていくかのごとく感じられるように書かれた騙し絵のような曲。第3楽章〈ファスカール〉。これはハンガリー語で「ねじれ」とか「よじれ」の意。おかしな転調がずっと続くということからだろうか。「人が泣き出しそうになった時に鼻に感じる痛いようなねじれたような感覚」と作曲者は説明している。第4楽章〈プレスト・コン・ソルディーノ〉はその名の通り、弱音器をつけた速い楽章だが、アクセントの位置が目覚ましく変化して眩暈を起こすような音楽となる。第5楽章〈ラメント〉は、終始ダブルストップで奏され、その旋律はバルカン半島、象牙海岸、メラネシアなどの影響を受けているという。第6楽章〈半音階的シャコンヌ〉。リゲティはこの曲でバッハへの言及は一切ないと述べ、シャコンヌの用語にしてもその原義「低音のオスティナート音列を伴う、強くアクセントのつけられた三拍子の、荒々しく、喜びに満ちあふれた舞曲」に過ぎないとするが、やはりシャコンヌとくると無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番を連想せざるを得ないだろう。聴くだに怖気を振るうようなとんでもない重音の連続。そこにバルトーク風の(ということはハンガリー民謡風の)旋律が印象的に登場する。
録音はすでに6種もある。
初演者ツィンマーマンの演奏はソニーのリゲティ・エディションの第7巻に収録。初演者としてひとつのスタンダードを築いているといえるだろう。
リゲティ・エディション7 室内楽作品集/オムニバス(クラシック)
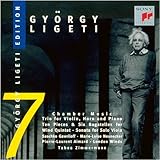
Amazon.co.jp
「ループ」の初演者ノックスの演奏はこの曲の民謡的な要素からはむしろ離れて、現代音楽としてびしびしと弾ききっているという感じ。〈プレスト・コン・ソルディーノ〉の仮借ないテンポなど大した迫力。
Works for Solo Viola/Gyorgy Ligeti
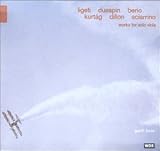
Amazon.co.jp
デヴュー盤でこの曲をとりあげたローレンス・パワーは優れた技巧できっちりと弾いているが、欲を言えばちょっと生真面目にすぎる。どこかあっさりしているのがこの人の持ち味ともいえるのだが。
Viola Works/Gyorgy Ligeti

Amazon.co.jp
今井信子の演奏は「ヴィオラ・スペース・ジャパン10周年記念」盤に収録。さすがに風格のある演奏。
Viola Space/George Benjamin
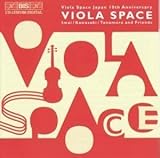
Amazon.co.jp
師タベア・ツィンマーマンの路線の延長に、まるで一編の民謡集のように弾ききったタメスティット盤。たぶん「ホラ・ルンガ」はこんな風にゆっくりとダラダラと歌われる民謡なのだろう。曲と戯れているようなところが魅力。
J.S.バッハ:無伴奏パルテ/アーティスト不明
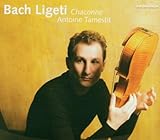
Amazon.co.jp
HMV ONLINE

ジュヌヴィエーヴ・ストロッセはテンポ的にはタメスティットに近いが、きちっとまじめに弾いている感じなのは種々の現代音楽のアンサンブルに参加している人だけのことはあるというところか。
Works for Solo Viola/Strosser
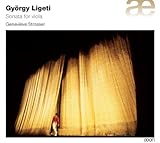
Amazon.co.jp
第二次世界大戦後の前衛音楽を担ったピエール・ブーレーズ、カール・ハインツ・シュトックハウゼン、ルチアーノ・ベリオらヨーロッパの主流に対して、1960年代、ヨーロッパの周縁から刺激を加えてきたひとりが、ハンガリーのジェルジ・リゲティである。リゲティというと一定音域を音でべったりと埋め尽くすトーン・クラスターがトレードマークだったが、晩年には民謡への参照を強めた。無伴奏ヴィオラ・ソナタはこの時期のものでヴァイオリン協奏曲やピアノのための練習曲第2巻、ナンセンス・マドリガルと語法上の共通性を持つ。
ヴィオラという楽器について、「木と大地とタンニン酸を思い出させる」C線しか好きではなかったリゲティだったが、1990年にタベア・ツィンマーマンの演奏を聴いてひどく魅了された。「きめが粗く、目覚ましいが、常に優しい」G線のよさにも開眼したのだという。1991年、ウニフェルザル出版の社長アルフレート・シュレーの90歳祝いのために、アーディッティ弦楽四重奏団あるいはそのメンバーの演奏する小品が何人もの作曲家に委嘱され、1枚のCDが作られたが、この時、リゲティはヴィオラ・ソロのための《ループ》という曲を書く。これは当時アーディッティ弦楽四重奏団のヴィオラ奏者だったガース・ノックスが初演した。翌年、彼の教師だったシャーンドル・ヴェレシュの追悼に《ファスカール》が書かれる。1994年に至り、ここにさらに4曲が書き足されて、6楽章の無伴奏ヴィオラ・ソナタが完成し、タベアに献呈され彼女が初演した。
一番テンポの速いノックス盤が20分弱、遅いタメスティット盤が23分ほど。ゆっくりした楽章と早い楽章が交互に配置されている。性格的小品の寄せ集めのようでありながら、リゲティの個性に染め上げられて一貫性がある。技巧的には難しいが、音楽の作りは単純と作曲者は述べるが、そこにはリゲティ一流のパラドックスが仕掛けられている。
第1楽章〈ホラ・ルンガ〉は「ゆっくりした舞曲」の意。これはC線のみで弾かれる。最初はC線の普通の音域で民謡風の旋律が歌われる。明白な引用ではないものの、ルーマニアのカルパティア山脈北方の民謡の性格を持ったものだという。ゆっくりとした定型的な旋律素材がつなぎ合わされていくもの。しかし最初の数音ですでに微分音程のずれがあって、とても奇妙である。もっともこれは民謡自体が西洋的な平均率に則っていないことを反映しているのだろう。リゲティはヴィオラのC線のさらに下にF線があるものと想定し、そのF線の第5、第7、第11倍音が作る、平均率とずれた音程を使用しているのだという。この架空の民謡の旋律はしまいにはC線のハーモニクスまで使って非常に高い音程まで登っていく。最後はまるで極限的な音程。第2楽章〈ループ〉は奇妙なスイング感を持った早い楽章。タメスティットはジャズの精神を持って演奏すべきという。基本的なテンポは変わらないので、どんどんテンポが上がっていくかのごとく感じられるように書かれた騙し絵のような曲。第3楽章〈ファスカール〉。これはハンガリー語で「ねじれ」とか「よじれ」の意。おかしな転調がずっと続くということからだろうか。「人が泣き出しそうになった時に鼻に感じる痛いようなねじれたような感覚」と作曲者は説明している。第4楽章〈プレスト・コン・ソルディーノ〉はその名の通り、弱音器をつけた速い楽章だが、アクセントの位置が目覚ましく変化して眩暈を起こすような音楽となる。第5楽章〈ラメント〉は、終始ダブルストップで奏され、その旋律はバルカン半島、象牙海岸、メラネシアなどの影響を受けているという。第6楽章〈半音階的シャコンヌ〉。リゲティはこの曲でバッハへの言及は一切ないと述べ、シャコンヌの用語にしてもその原義「低音のオスティナート音列を伴う、強くアクセントのつけられた三拍子の、荒々しく、喜びに満ちあふれた舞曲」に過ぎないとするが、やはりシャコンヌとくると無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番を連想せざるを得ないだろう。聴くだに怖気を振るうようなとんでもない重音の連続。そこにバルトーク風の(ということはハンガリー民謡風の)旋律が印象的に登場する。
録音はすでに6種もある。
初演者ツィンマーマンの演奏はソニーのリゲティ・エディションの第7巻に収録。初演者としてひとつのスタンダードを築いているといえるだろう。
リゲティ・エディション7 室内楽作品集/オムニバス(クラシック)
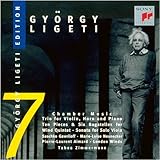
Amazon.co.jp
「ループ」の初演者ノックスの演奏はこの曲の民謡的な要素からはむしろ離れて、現代音楽としてびしびしと弾ききっているという感じ。〈プレスト・コン・ソルディーノ〉の仮借ないテンポなど大した迫力。
Works for Solo Viola/Gyorgy Ligeti
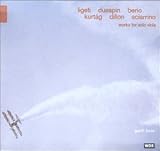
Amazon.co.jp
デヴュー盤でこの曲をとりあげたローレンス・パワーは優れた技巧できっちりと弾いているが、欲を言えばちょっと生真面目にすぎる。どこかあっさりしているのがこの人の持ち味ともいえるのだが。
Viola Works/Gyorgy Ligeti

Amazon.co.jp
今井信子の演奏は「ヴィオラ・スペース・ジャパン10周年記念」盤に収録。さすがに風格のある演奏。
Viola Space/George Benjamin
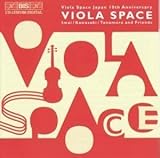
Amazon.co.jp
師タベア・ツィンマーマンの路線の延長に、まるで一編の民謡集のように弾ききったタメスティット盤。たぶん「ホラ・ルンガ」はこんな風にゆっくりとダラダラと歌われる民謡なのだろう。曲と戯れているようなところが魅力。
J.S.バッハ:無伴奏パルテ/アーティスト不明
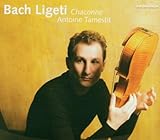
Amazon.co.jp
HMV ONLINE
ジュヌヴィエーヴ・ストロッセはテンポ的にはタメスティットに近いが、きちっとまじめに弾いている感じなのは種々の現代音楽のアンサンブルに参加している人だけのことはあるというところか。
Works for Solo Viola/Strosser
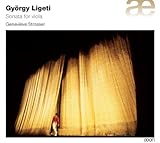
Amazon.co.jp