(3)ゲオルク・フィリップ・テレマン(1681-1767):ヴィオラ協奏曲ト長調TWV 51:G9
史上初のヴィオラ協奏曲はテレマンのものらしい。正式にはヴィオラ・ダ・ブラッチョのための協奏曲と記されているようだ。ヴィオラ・ダ・ガンバ=足のヴィオラに対する、腕のヴィオラという意味だが、ガンバなどのヴィオール族からヴァイオリン族に主流が変遷していく時期の過渡的な呼称と考えていいのだろう。恐らく最初は、ヴィオール族に対するヴァイオリン族の総称として用いられ、やがて現在のヴィオラに相当するものに意味が限局していったのではないだろうか。J. S. バッハのブランデンブルク協奏曲第6番のヴィオラもヴィオラ・ダ・ブラッチョになっている。このブラッチョが、現在もドイツ語のヴィオラを示すブラッチェという言葉として残っているのは周知の通り。
彼の時代、ローカルな作曲家だったJ. S. バッハに比べて、テレマンはヨーロッパ中に知られたスター作曲家だった。管弦楽組曲だけで100曲を超え、受難曲も四十何曲。現在でもその作品の整理は行き届いていないありさまなのだそうだ。私など、短調のバッハはちょっと重たすぎるので、長調のテレマンを聴くのはとても楽しい。最近はテレマン作品目録TWVの番号で整理されている。ヴァイオリン協奏曲をはじめ、協奏曲も数多あるが、ヴィオラ協奏曲はこれ一曲しか残っていない。残っていないのか、一曲しか作曲されなかったのか、私にはわからない。ヴィオラ協奏曲はTWVで、ソロ協奏曲を示す51番中の、ト長調の9個目の曲G9と分類されている。
もっとも、別に2つのヴィオラのための協奏曲というのはあるけれど。これも実は2つのヴィオレッタのための協奏曲、とある。ヴィオレッタって何だ? 椿姫ではないと思うが、小ぶりのヴィオラという意味だろうか。いずれにせよ、現在はヴィオラで演奏される。後述のベルリン・バロック・ゾリステン盤、ムジカ・アンティ・ケルン盤にはこの曲も収録されている。
1712~21年のハンブルク時代に作曲されたと推定されている。いわゆるソナタ・ダ・キエザ(教会ソナタ)様式の緩急緩急の4楽章。どういう状況で作曲され、誰が弾いたのかといった情報はどのCDを見ても載っていないのでわかっていないのだろう。
ディスクは結構あるけれど、12分ほどの曲なので、テレマン作品集か、ヴィオラ協奏曲集にこっそり収録されている。
Recorder Suite / Viola Concerto / Tafelmusik/Georg Philipp Telemann
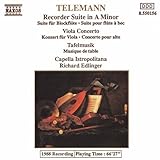
Amazon.co.jp
昔懐かしい分厚い弦楽合奏で荘重にやったものならNaxosのカペラ・イストポリターナ盤。ソロはラディスラフ・キセラクという人が重厚に弾いている。ほとんど即興的な装飾を加えず弾いているのは今となっては貴重かも知れない。
String Concertos/Georg Philipp Telemann
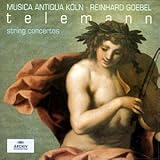
Amazon.co.jp
しかし、やはりこの時代の作品ならオリジナル楽器の演奏が聴きたい。ドイツ・バロックなら、ムジカ・アンティカ・ケルンでしょう。弦3-3-2-2-1にチェンバロ、テオルボという編成。テオルボがはいると古雅な味わいが増していい。第1楽章ラルゴからしてフレージングが短くて度肝を抜かれる。フローリアン・ドイターのヴィオラはくすんだ渋い音だが、1650年のフランドルの作者不明の楽器を使用とのこと。譜面通りははじめばかりで、即興的変奏を加えていく。第2楽章アレグロは軽快な上行音型がテヌートでまたびっくり。第3楽章アンダンテは超高速で終わってしまう。しかし、歩くくらいの速度アンダンテなら、これが正解。まあ、いささか早足だが。終楽章はプレストだから歯切れのいい速度と切れ味で。

jpc
最近、若手ヴィオラ奏者がこの曲を入れている。
ニルス・メンケマイアーはポツダム室内アカデミーと。オリジナル楽器ではないようだが、短い音価の扱いなど近年の古楽演奏の影響下にある。ソロも装飾をふんだんに加えている。何より躍動的な味わいが快い。オケのメンバーが明記されていないので編成はよくわからないが、聴いたところでは少人数の合奏で、各パートソロではないようだ。通奏低音はチェンバロもテオルボも入っていていい味わいを醸す。
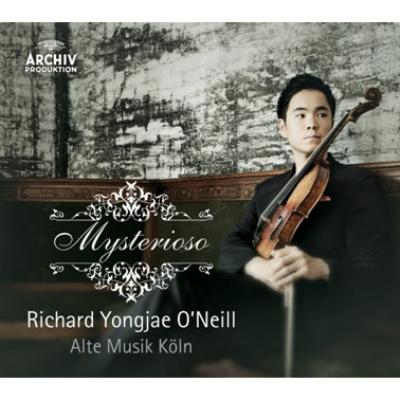
HMV ONLINE
もう一人は、リチャード・ヨンジェ・オニール。オリジナル楽器のアルテ・ムジーク・ケルンとやっている。こちらは各パートひとり。念を押すような拍節感がとりわけ緩序楽章でいささかもたれるが、古楽器仕様の音色の魅力がある。オニールの装飾はちょっと違和感を感ずるときがある。通奏低音はチェンバロ。
Concertos & Unknown Works/Georg Philipp Telemann
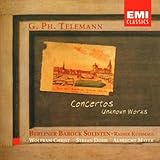
Amazon.co.jp
ベルリン・フィルの元ソロ奏者の演奏が2つ。
ヴォルフラム・クリスト=ベルリン・バロック・ゾリステン盤。ベルリン・バロック・ゾリステンはベルリン・フィルの首席奏者を中心に結成された、ミニ・ベルリン・フィル。とはいえ現在のベルリン・フィルはカラヤン時代のような低音に基盤をおいた重いオケではない。弦は2-2-1-1-1という編成でメリハリのきいたアンサンブルをしている。クリストの楽器はヴィオーム製。
クリストにはベルリン・フィルハーモニー・ゾリステンとの来日時に東芝EMIが録音した盤もある。
Music for Viola & Orchestra/Telemann
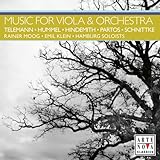
Amazon.co.jp
ライナー・モーク=ハンブルク・ゾリステン盤。同じくベルリン・フィルといっても、モークの音はもっと恰幅が広く野太いのが魅力。モークは飯田裕氏製作の楽器を使ったCDがあるが、この録音でもそうなのかは不明。
Suzuki Viola School, Viola: Viola Part (Suzuki .../Shinichi Suzuki

Amazon.co.jp
この曲、New York Viola Societyのカタログでは30種ほどの録音が挙げられているが、ソリスト級のヴィオリストの録音は多くはない。やはり易しいからだろうか。Suzuki Viola School Vol.4にも収録されているお稽古曲。
史上初のヴィオラ協奏曲はテレマンのものらしい。正式にはヴィオラ・ダ・ブラッチョのための協奏曲と記されているようだ。ヴィオラ・ダ・ガンバ=足のヴィオラに対する、腕のヴィオラという意味だが、ガンバなどのヴィオール族からヴァイオリン族に主流が変遷していく時期の過渡的な呼称と考えていいのだろう。恐らく最初は、ヴィオール族に対するヴァイオリン族の総称として用いられ、やがて現在のヴィオラに相当するものに意味が限局していったのではないだろうか。J. S. バッハのブランデンブルク協奏曲第6番のヴィオラもヴィオラ・ダ・ブラッチョになっている。このブラッチョが、現在もドイツ語のヴィオラを示すブラッチェという言葉として残っているのは周知の通り。
彼の時代、ローカルな作曲家だったJ. S. バッハに比べて、テレマンはヨーロッパ中に知られたスター作曲家だった。管弦楽組曲だけで100曲を超え、受難曲も四十何曲。現在でもその作品の整理は行き届いていないありさまなのだそうだ。私など、短調のバッハはちょっと重たすぎるので、長調のテレマンを聴くのはとても楽しい。最近はテレマン作品目録TWVの番号で整理されている。ヴァイオリン協奏曲をはじめ、協奏曲も数多あるが、ヴィオラ協奏曲はこれ一曲しか残っていない。残っていないのか、一曲しか作曲されなかったのか、私にはわからない。ヴィオラ協奏曲はTWVで、ソロ協奏曲を示す51番中の、ト長調の9個目の曲G9と分類されている。
もっとも、別に2つのヴィオラのための協奏曲というのはあるけれど。これも実は2つのヴィオレッタのための協奏曲、とある。ヴィオレッタって何だ? 椿姫ではないと思うが、小ぶりのヴィオラという意味だろうか。いずれにせよ、現在はヴィオラで演奏される。後述のベルリン・バロック・ゾリステン盤、ムジカ・アンティ・ケルン盤にはこの曲も収録されている。
1712~21年のハンブルク時代に作曲されたと推定されている。いわゆるソナタ・ダ・キエザ(教会ソナタ)様式の緩急緩急の4楽章。どういう状況で作曲され、誰が弾いたのかといった情報はどのCDを見ても載っていないのでわかっていないのだろう。
ディスクは結構あるけれど、12分ほどの曲なので、テレマン作品集か、ヴィオラ協奏曲集にこっそり収録されている。
Recorder Suite / Viola Concerto / Tafelmusik/Georg Philipp Telemann
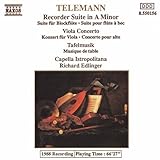
Amazon.co.jp
昔懐かしい分厚い弦楽合奏で荘重にやったものならNaxosのカペラ・イストポリターナ盤。ソロはラディスラフ・キセラクという人が重厚に弾いている。ほとんど即興的な装飾を加えず弾いているのは今となっては貴重かも知れない。
String Concertos/Georg Philipp Telemann
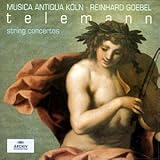
Amazon.co.jp
しかし、やはりこの時代の作品ならオリジナル楽器の演奏が聴きたい。ドイツ・バロックなら、ムジカ・アンティカ・ケルンでしょう。弦3-3-2-2-1にチェンバロ、テオルボという編成。テオルボがはいると古雅な味わいが増していい。第1楽章ラルゴからしてフレージングが短くて度肝を抜かれる。フローリアン・ドイターのヴィオラはくすんだ渋い音だが、1650年のフランドルの作者不明の楽器を使用とのこと。譜面通りははじめばかりで、即興的変奏を加えていく。第2楽章アレグロは軽快な上行音型がテヌートでまたびっくり。第3楽章アンダンテは超高速で終わってしまう。しかし、歩くくらいの速度アンダンテなら、これが正解。まあ、いささか早足だが。終楽章はプレストだから歯切れのいい速度と切れ味で。

jpc
最近、若手ヴィオラ奏者がこの曲を入れている。
ニルス・メンケマイアーはポツダム室内アカデミーと。オリジナル楽器ではないようだが、短い音価の扱いなど近年の古楽演奏の影響下にある。ソロも装飾をふんだんに加えている。何より躍動的な味わいが快い。オケのメンバーが明記されていないので編成はよくわからないが、聴いたところでは少人数の合奏で、各パートソロではないようだ。通奏低音はチェンバロもテオルボも入っていていい味わいを醸す。
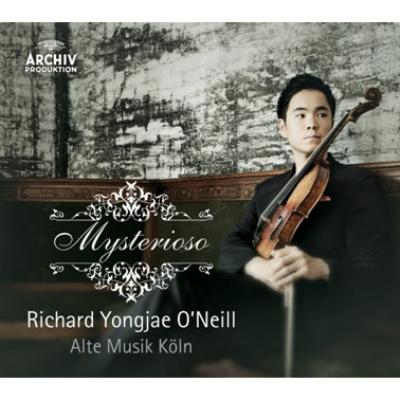
HMV ONLINE
もう一人は、リチャード・ヨンジェ・オニール。オリジナル楽器のアルテ・ムジーク・ケルンとやっている。こちらは各パートひとり。念を押すような拍節感がとりわけ緩序楽章でいささかもたれるが、古楽器仕様の音色の魅力がある。オニールの装飾はちょっと違和感を感ずるときがある。通奏低音はチェンバロ。
Concertos & Unknown Works/Georg Philipp Telemann
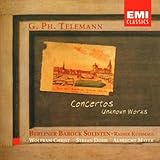
Amazon.co.jp
ベルリン・フィルの元ソロ奏者の演奏が2つ。
ヴォルフラム・クリスト=ベルリン・バロック・ゾリステン盤。ベルリン・バロック・ゾリステンはベルリン・フィルの首席奏者を中心に結成された、ミニ・ベルリン・フィル。とはいえ現在のベルリン・フィルはカラヤン時代のような低音に基盤をおいた重いオケではない。弦は2-2-1-1-1という編成でメリハリのきいたアンサンブルをしている。クリストの楽器はヴィオーム製。
クリストにはベルリン・フィルハーモニー・ゾリステンとの来日時に東芝EMIが録音した盤もある。
Music for Viola & Orchestra/Telemann
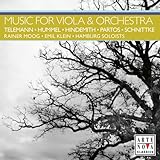
Amazon.co.jp
ライナー・モーク=ハンブルク・ゾリステン盤。同じくベルリン・フィルといっても、モークの音はもっと恰幅が広く野太いのが魅力。モークは飯田裕氏製作の楽器を使ったCDがあるが、この録音でもそうなのかは不明。
Suzuki Viola School, Viola: Viola Part (Suzuki .../Shinichi Suzuki

Amazon.co.jp
この曲、New York Viola Societyのカタログでは30種ほどの録音が挙げられているが、ソリスト級のヴィオリストの録音は多くはない。やはり易しいからだろうか。Suzuki Viola School Vol.4にも収録されているお稽古曲。