(2)ダリウス・ミヨー(1892-1974):ヴィオラ協奏曲第1番(1929)
ヴィオラは地味だし、多くの作曲家がピアノだのヴァイオリンだのの協奏曲をさんざん作ってから、ヴィオラの曲に取りかかるので、晩年の作品で、しかもエレジー的なものが目につく。バルトークのコンチェルトとショスタコーヴィチのソナタは文字通り白鳥の歌だし、ブリトゥンの《ラクリメ》だって、死の前年の作品でしかも「涙の日」だ。武満徹の《鳥が庭に降りてくる》も最後の作品のひとつじゃなかったか。いや、ヴィオラ用にだって陽気な曲はあるんだよって、ミヨーに登場願うわけ。
ミヨーは多作家だ。演奏する曲に困ったら、ミヨーかマルティヌーの作品表を眺めればいいというジョークがあるが、ヴィオラのレパートリーもしっかりある。ヴィオラ協奏曲「第1番」と題された曲を持っているのは、近年では、サリー・ビーミッシュ、ウィリアム・トーマス・マッキンリー、ペール・ヘンリク・ノルドグレンなどがいるけれど、バロックや古典期の作曲家や、あるいはヒンデミットなど複数曲ヴィオラ協奏曲を書いた人はいても、通常、番号は振られていない。ミヨーには番号つきのヴィオラ協奏曲が2曲ある。さらに、四季の名のついたコンチェルティーノ連作中の《夏》がヴィオラ用だ。
しかし、ミヨーは多作家ながら、録音は限られた曲以外は少なく、ヴィオラ協奏曲もその録音は第1番と夏のコンチェルティーノがあるだけのようだ。なぜ第2番が録音されないのかは不明。六人組の中で、オネゲルが私にとって非常に近しい作曲家だったのに対して、ミヨーはどうも苦手だった。明るすぎて閉口してしまうのだ。まあ、最近は交響曲の録音など今まで無視されてきたものも出てきて、そうしたものを聴いてはいるとむかし思っていたよりも作風の広い人だとわかってきた。でも、南仏出身のこの人は基本的に明るいのである。アンニュイはあってもメランコリーにはならない。そのミヨーのヴィオラ協奏曲は痛快の一言に尽きる。ヴィオラ音楽だって、見事に明るく、「ヴィオラは悲しみの楽器だ」とかいった観念とは縁がないのだ。こうまでヴィオラを明るい世界に出してくれたミヨーに乾杯! そうそう、ミヨーの自伝は『幸せだった私の一生』とかいうのだが、実にミヨーらしい。
この曲はヒンデミットのために1929年に通常の編成のオーケストラのために書かれ、ピエール・モントゥー指揮のコンセルトヘボウ管弦楽団により初演された。初演の後、室内管弦楽団とも演奏できるようにとのヒンデミットの示唆により、翌年、ヴィオラ独奏と15楽器のための版が作られた。下記のCDは双方ともこの第2版による。曲は12~14分ほどだが、しっかり4楽章もある。重音のヴィオラにクラリネットがまとわりついて、ちょっとストラヴィンスキーの《兵士の物語》みたいに始まるが、ヴィオラはヒンデミット風、伴奏はミヨー風という感じ。ヒンデミットの「室内音楽」に影響を受けているのかも知れない。翳りを帯びた第2楽章(《イタリアのハロルド》風のアルペッジョも出てくる)や淡い色彩の第3楽章は「明るい」では片づけられないが、終楽章は見事にお祭り騒ぎで終わってくれる。
CDは作曲者指揮、ベルリン・フィルの主席を務めたウルリヒ・コッホによる盤しかないと思っていたが、New York Viola SocietyによるとJulia Rebecca AdlerによるAudite盤があったらしい。そして最近、スサーネ・ヴァン・エルスのヴィオラ、ラインベルト・デ・レーウ指揮シェーンベルク・アンサンブルの盤が出た。
Darius Milhaud: Viola Concerto No. 1; Quatre Visages

Amazon.co.jp
Milhaud : 6 Little Symphonies,others
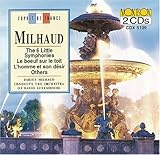
Amazon.co.jp
ヴィオラは地味だし、多くの作曲家がピアノだのヴァイオリンだのの協奏曲をさんざん作ってから、ヴィオラの曲に取りかかるので、晩年の作品で、しかもエレジー的なものが目につく。バルトークのコンチェルトとショスタコーヴィチのソナタは文字通り白鳥の歌だし、ブリトゥンの《ラクリメ》だって、死の前年の作品でしかも「涙の日」だ。武満徹の《鳥が庭に降りてくる》も最後の作品のひとつじゃなかったか。いや、ヴィオラ用にだって陽気な曲はあるんだよって、ミヨーに登場願うわけ。
ミヨーは多作家だ。演奏する曲に困ったら、ミヨーかマルティヌーの作品表を眺めればいいというジョークがあるが、ヴィオラのレパートリーもしっかりある。ヴィオラ協奏曲「第1番」と題された曲を持っているのは、近年では、サリー・ビーミッシュ、ウィリアム・トーマス・マッキンリー、ペール・ヘンリク・ノルドグレンなどがいるけれど、バロックや古典期の作曲家や、あるいはヒンデミットなど複数曲ヴィオラ協奏曲を書いた人はいても、通常、番号は振られていない。ミヨーには番号つきのヴィオラ協奏曲が2曲ある。さらに、四季の名のついたコンチェルティーノ連作中の《夏》がヴィオラ用だ。
しかし、ミヨーは多作家ながら、録音は限られた曲以外は少なく、ヴィオラ協奏曲もその録音は第1番と夏のコンチェルティーノがあるだけのようだ。なぜ第2番が録音されないのかは不明。六人組の中で、オネゲルが私にとって非常に近しい作曲家だったのに対して、ミヨーはどうも苦手だった。明るすぎて閉口してしまうのだ。まあ、最近は交響曲の録音など今まで無視されてきたものも出てきて、そうしたものを聴いてはいるとむかし思っていたよりも作風の広い人だとわかってきた。でも、南仏出身のこの人は基本的に明るいのである。アンニュイはあってもメランコリーにはならない。そのミヨーのヴィオラ協奏曲は痛快の一言に尽きる。ヴィオラ音楽だって、見事に明るく、「ヴィオラは悲しみの楽器だ」とかいった観念とは縁がないのだ。こうまでヴィオラを明るい世界に出してくれたミヨーに乾杯! そうそう、ミヨーの自伝は『幸せだった私の一生』とかいうのだが、実にミヨーらしい。
この曲はヒンデミットのために1929年に通常の編成のオーケストラのために書かれ、ピエール・モントゥー指揮のコンセルトヘボウ管弦楽団により初演された。初演の後、室内管弦楽団とも演奏できるようにとのヒンデミットの示唆により、翌年、ヴィオラ独奏と15楽器のための版が作られた。下記のCDは双方ともこの第2版による。曲は12~14分ほどだが、しっかり4楽章もある。重音のヴィオラにクラリネットがまとわりついて、ちょっとストラヴィンスキーの《兵士の物語》みたいに始まるが、ヴィオラはヒンデミット風、伴奏はミヨー風という感じ。ヒンデミットの「室内音楽」に影響を受けているのかも知れない。翳りを帯びた第2楽章(《イタリアのハロルド》風のアルペッジョも出てくる)や淡い色彩の第3楽章は「明るい」では片づけられないが、終楽章は見事にお祭り騒ぎで終わってくれる。
CDは作曲者指揮、ベルリン・フィルの主席を務めたウルリヒ・コッホによる盤しかないと思っていたが、New York Viola SocietyによるとJulia Rebecca AdlerによるAudite盤があったらしい。そして最近、スサーネ・ヴァン・エルスのヴィオラ、ラインベルト・デ・レーウ指揮シェーンベルク・アンサンブルの盤が出た。
Darius Milhaud: Viola Concerto No. 1; Quatre Visages

Amazon.co.jp
Milhaud : 6 Little Symphonies,others
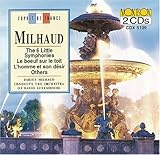
Amazon.co.jp