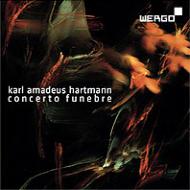(23) カール・アマデウス・ハルトマン(1905-1963):ヴィオラにピアノを伴う管楽器・打楽器伴奏の協奏曲(1954/56)
カール・アマデウス・ハルトマンは今でこそメジャー・レーベル(EMI)から交響曲全集 が出ているが、かつて私はハルトマンを聴くのに大変苦労した。そんな昔話。
が出ているが、かつて私はハルトマンを聴くのに大変苦労した。そんな昔話。
かつてお茶の水にレアものばかりを専門としたクラシックのレコード店があって、その店がレコード雑誌にハルトマン交響曲全集のレコードの広告を出した。当時、交響曲あさりをしてた私は、気になってハルトマンて誰だと調べたところ、新ヴィーン楽派とストラヴィンスキイのバーバリズムを融合させた作風とかいう記述を見て、俄然、聴きたくなってしまった。しかし、その店に行った時には既に遅し、ハルトマン交響曲全集は売り切れていた。地団駄踏む思いである。どうせ1セットくらいの在庫だったのだろう。これは他でもない、Wergoのクーベリックもいくつか指揮しているバイエルン放送響の演奏であり、いまやCD化されている。それから半年だか1年だかしてそのLPボックスセットをようやく手に入れたのだが、内容はちょっと予想とは違っていた。ストラヴィンスキイのバーバリズムがちゃぶ台ひっくり返して暴れるようなものなら、ハルトマンのバーバリズムはちゃぶ台を端から破砕していくようなものだ。いや、ちょっとそういう暴れ方はないんじゃないかと鼻白んだ。その真価がわかってきたのはCD化されて買い直してからだったかも。
ハルトマンもその後、だいぶ一般化した。とりわけ《葬送協奏曲》は20世紀のヴァイオリン協奏曲の中でも好んで演奏されるものに仲間入りしたといっていいだろう。1939年、ナチス政権下に書かれ、〈反ファシズム〉とも副題されるこの曲は、しかし、それこそハルトマンの真骨頂ではない。彼はナチス政権下で「国内亡命」、沈黙を決め込んでいたが、作品は書き続けていた。戦後、それらの作品を改作し、交響曲第6番までを発表する。第7番と第8番は戦後に新たに書かれたものである。これらの作品は徹底した推敲と容赦ない苛烈な表現が、一見した古典的形式の中に詰め込まれている。
戦後のハルトマンは何といっても8曲の交響曲が代表作であるが、最近になって、初期の作品にも注目が向けられるようになってきた。無伴奏ヴァイオリン・ソナタと組曲 (各2曲:1927)、5つの小オペラ連作《蝋人形展示室》
(各2曲:1927)、5つの小オペラ連作《蝋人形展示室》 (1929/30)、オペラ《シンプリツィウス
(1929/30)、オペラ《シンプリツィウス ・シンプリツィシムス
・シンプリツィシムス 》(1934/35; rev.56/57)、室内協奏曲
》(1934/35; rev.56/57)、室内協奏曲 (1930/35)、あるいは戦後の交響曲の改作元となった《シンフォニア・トラジカ》
(1930/35)、あるいは戦後の交響曲の改作元となった《シンフォニア・トラジカ》 (1940; rev.1943)などである。
(1940; rev.1943)などである。
ところがどっこい、ハルトマンのディスコグラフィーはむしろ交響曲以外の戦後作品の録音が遅れてしまい、ピアノと管楽器・打楽器のための協奏曲(1953)はクーベリック盤 がようやく出て、下記Wergo盤に新録が収録。そして、このヴィオラ協奏曲も最近になって登場したわけだ。ヴァイオリン協奏曲の方はいくつも録音されているのに酷いじゃないか。
がようやく出て、下記Wergo盤に新録が収録。そして、このヴィオラ協奏曲も最近になって登場したわけだ。ヴァイオリン協奏曲の方はいくつも録音されているのに酷いじゃないか。
下記のCapricio盤のCDジャケットには英題で「Concerto for Viola and Piano」と大書されている。ヴィオラとピアノのための協奏曲である。ところが、ドイツ語の原題は「Konzert für Bratche mit Klavier, begreitet von Bläsern und Schlagzeig」なので、ちょっとニュアンスが違う。CDではドイツ語もKonzert für Bratche und Klavier...になっているが、これはハルトマン自身の命名とは違う。修飾語があとからズラズラ並んでいる様を生かして訳すと「ヴィオラ協奏曲(ピアノ付き、管楽器・打楽器伴奏)」という感じか。あくまでヴィオラのための協奏曲でピアノが付随し、伴奏は管楽器と打楽器なのである。その証拠に、第1楽章「ロンド」冒頭、まずはヴィオラの長々とした無伴奏で多声的なソロが続く。管楽器の吹奏が少しずつはいってきて、ピアノの登場は伴奏の一員という扱い。
なぜ、そんなことをくだくだ述べるのかというと、このヴィオラ名曲100選には、いくつか選定基準を考えていて、協奏曲はソロ協奏曲しか扱わないつもりなのだ。つまり二重奏協奏曲は排除。というのも、モーツァルトの協奏交響曲は名曲だけれども、ヴィオラの名曲にこれを挙げるのはどうにも癪じゃないか。モーツァルトより劣るかも知れないが、ヴィオラの独奏協奏曲は沢山あるのだから。しかし、なぜハルトマンは取り上げるの、という言い訳が上記なのだが、他の選定基準には「好きな作曲家はできるだけ取り上げたい」もあるのだよ。
さて第1楽章。「ロンド」と題されているが、なぜか前半遅い音楽、後半速い音楽。後半はハルトマン流怒濤のアレグロ。留まるところなく無窮動的なヴィオラとオケが突き進む。ヒンデミットのヴィオラ協奏曲、なかんずく室内音楽第5番を思い起こすが、この無窮動的な旋律、ヒンデミットのようだけれど、よく聴くとハルトマンの交響曲のアレグロの節回しなのだ。管楽器はオーボエとホルンを欠き、CD解説によると柔らかい音色を敢えて避けているのだという。第2楽章「メロディ」ではピアノは導入部だけで、あとはお休み、ヴィオラ・ソロを管打楽器が伴奏し続ける。中間部でテンポが速くなる、緩序楽章とスケルツォを融合したような形。第3楽章「ロンド・ヴァリエ」は今度は三拍子系の無窮動的音楽。無調でよくここまで高揚し続けられると感心して聴く約25~27分。
このヴィオラ協奏曲はプリムローズのために書かれたが、病気のため初演は他人の手に委ねるを得なかった。
最初に出たのがCapriccio盤。演奏はタチャーナ・マスレンコのヴィオラ、フランク-インモ・ツィヒナーのピアノ、マレク・ヤノフスキ指揮ベルリン放送交響楽団団員。この初録音は恐らく放送録音で、第1楽章だけがRCAの「Music in Deutschland 1950-2000」に収録されていて、臍を噛んでいた。
HMV ONLINE
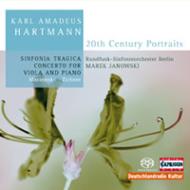

もうひとつリリースされたのが、Wergo盤。ディートリヒのヴァイオリン協奏曲でソロをとっていた、エリザベート・クフェラートのヴィオラ(彼女はヴァイオリンとともにヴィオラも弾く。現在はバンベルク交響楽団のコンサートミストレス)、ポール・グッドウィン指揮カイザースラウテルン南西ドイツ放送交響楽団。グッドウィンはバロック・オーボエ奏者でホグウッドの後任として古楽アカデミーの指揮者をしていたが、最近はオペラの指揮に力を入れているとのこと。しかしなぜここでハルトマンなんか振っているのか不明。オケは2007年にザールブリュッケン放送交響楽団と合併して、ドイツ放送フィルハーモニーとなる、あの楽団である。
HMV ONLINE
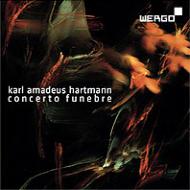

カール・アマデウス・ハルトマンは今でこそメジャー・レーベル(EMI)から交響曲全集
かつてお茶の水にレアものばかりを専門としたクラシックのレコード店があって、その店がレコード雑誌にハルトマン交響曲全集のレコードの広告を出した。当時、交響曲あさりをしてた私は、気になってハルトマンて誰だと調べたところ、新ヴィーン楽派とストラヴィンスキイのバーバリズムを融合させた作風とかいう記述を見て、俄然、聴きたくなってしまった。しかし、その店に行った時には既に遅し、ハルトマン交響曲全集は売り切れていた。地団駄踏む思いである。どうせ1セットくらいの在庫だったのだろう。これは他でもない、Wergoのクーベリックもいくつか指揮しているバイエルン放送響の演奏であり、いまやCD化されている。それから半年だか1年だかしてそのLPボックスセットをようやく手に入れたのだが、内容はちょっと予想とは違っていた。ストラヴィンスキイのバーバリズムがちゃぶ台ひっくり返して暴れるようなものなら、ハルトマンのバーバリズムはちゃぶ台を端から破砕していくようなものだ。いや、ちょっとそういう暴れ方はないんじゃないかと鼻白んだ。その真価がわかってきたのはCD化されて買い直してからだったかも。
ハルトマンもその後、だいぶ一般化した。とりわけ《葬送協奏曲》は20世紀のヴァイオリン協奏曲の中でも好んで演奏されるものに仲間入りしたといっていいだろう。1939年、ナチス政権下に書かれ、〈反ファシズム〉とも副題されるこの曲は、しかし、それこそハルトマンの真骨頂ではない。彼はナチス政権下で「国内亡命」、沈黙を決め込んでいたが、作品は書き続けていた。戦後、それらの作品を改作し、交響曲第6番までを発表する。第7番と第8番は戦後に新たに書かれたものである。これらの作品は徹底した推敲と容赦ない苛烈な表現が、一見した古典的形式の中に詰め込まれている。
戦後のハルトマンは何といっても8曲の交響曲が代表作であるが、最近になって、初期の作品にも注目が向けられるようになってきた。無伴奏ヴァイオリン・ソナタと組曲
ところがどっこい、ハルトマンのディスコグラフィーはむしろ交響曲以外の戦後作品の録音が遅れてしまい、ピアノと管楽器・打楽器のための協奏曲(1953)はクーベリック盤
下記のCapricio盤のCDジャケットには英題で「Concerto for Viola and Piano」と大書されている。ヴィオラとピアノのための協奏曲である。ところが、ドイツ語の原題は「Konzert für Bratche mit Klavier, begreitet von Bläsern und Schlagzeig」なので、ちょっとニュアンスが違う。CDではドイツ語もKonzert für Bratche und Klavier...になっているが、これはハルトマン自身の命名とは違う。修飾語があとからズラズラ並んでいる様を生かして訳すと「ヴィオラ協奏曲(ピアノ付き、管楽器・打楽器伴奏)」という感じか。あくまでヴィオラのための協奏曲でピアノが付随し、伴奏は管楽器と打楽器なのである。その証拠に、第1楽章「ロンド」冒頭、まずはヴィオラの長々とした無伴奏で多声的なソロが続く。管楽器の吹奏が少しずつはいってきて、ピアノの登場は伴奏の一員という扱い。
なぜ、そんなことをくだくだ述べるのかというと、このヴィオラ名曲100選には、いくつか選定基準を考えていて、協奏曲はソロ協奏曲しか扱わないつもりなのだ。つまり二重奏協奏曲は排除。というのも、モーツァルトの協奏交響曲は名曲だけれども、ヴィオラの名曲にこれを挙げるのはどうにも癪じゃないか。モーツァルトより劣るかも知れないが、ヴィオラの独奏協奏曲は沢山あるのだから。しかし、なぜハルトマンは取り上げるの、という言い訳が上記なのだが、他の選定基準には「好きな作曲家はできるだけ取り上げたい」もあるのだよ。
さて第1楽章。「ロンド」と題されているが、なぜか前半遅い音楽、後半速い音楽。後半はハルトマン流怒濤のアレグロ。留まるところなく無窮動的なヴィオラとオケが突き進む。ヒンデミットのヴィオラ協奏曲、なかんずく室内音楽第5番を思い起こすが、この無窮動的な旋律、ヒンデミットのようだけれど、よく聴くとハルトマンの交響曲のアレグロの節回しなのだ。管楽器はオーボエとホルンを欠き、CD解説によると柔らかい音色を敢えて避けているのだという。第2楽章「メロディ」ではピアノは導入部だけで、あとはお休み、ヴィオラ・ソロを管打楽器が伴奏し続ける。中間部でテンポが速くなる、緩序楽章とスケルツォを融合したような形。第3楽章「ロンド・ヴァリエ」は今度は三拍子系の無窮動的音楽。無調でよくここまで高揚し続けられると感心して聴く約25~27分。
このヴィオラ協奏曲はプリムローズのために書かれたが、病気のため初演は他人の手に委ねるを得なかった。
最初に出たのがCapriccio盤。演奏はタチャーナ・マスレンコのヴィオラ、フランク-インモ・ツィヒナーのピアノ、マレク・ヤノフスキ指揮ベルリン放送交響楽団団員。この初録音は恐らく放送録音で、第1楽章だけがRCAの「Music in Deutschland 1950-2000」に収録されていて、臍を噛んでいた。
HMV ONLINE
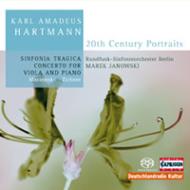
もうひとつリリースされたのが、Wergo盤。ディートリヒのヴァイオリン協奏曲でソロをとっていた、エリザベート・クフェラートのヴィオラ(彼女はヴァイオリンとともにヴィオラも弾く。現在はバンベルク交響楽団のコンサートミストレス)、ポール・グッドウィン指揮カイザースラウテルン南西ドイツ放送交響楽団。グッドウィンはバロック・オーボエ奏者でホグウッドの後任として古楽アカデミーの指揮者をしていたが、最近はオペラの指揮に力を入れているとのこと。しかしなぜここでハルトマンなんか振っているのか不明。オケは2007年にザールブリュッケン放送交響楽団と合併して、ドイツ放送フィルハーモニーとなる、あの楽団である。
HMV ONLINE