(62) エディソン・デニーソフ(1929-96):パウル・クレーの3つの絵─ヴィオラとアンサンブルのための(1985)
発明王に因んで命名された子が作曲家になるとは両親も予想できなかったに違いない。
デニーソフはソヴィエト・ロシアで西側の前衛的な語法を身につけた作曲家として1960年代初めから西欧で知られていた。1970年代後半になって、シュニトケやグバイドゥーリナが紹介されるまで、西側に知られたほとんど唯一のソヴィエトの前衛作曲家だった。ピエール・ブーレーズの《マルトー・サン・メートル》に影響を受けた1964年の《インカの太陽》が出世作。この頃は旋律線に微分音が豊富に仕掛けられていたが、1980年代頃から、半音階だけで似たような効果を醸しだし、かなりロマンティックな表情もみせるようになった。しかし彼はフランス音楽から影響を受けた作曲家で、硬質で色彩的なオーケストレーションはロシア人離れしている。
ヴィオラ音楽は1980年代に集中して書かれており、《パウル・クレーの3つの絵》のほかにも、ヴィオラとチェンバロと弦楽のための《室内音楽》(1982)、2つのヴィオラとチェンバロと弦楽のための協奏曲(1984)、ヴィオラとピアノのための《バッハのコラール「もう十分です」の主題による変奏曲》(1984、ヴィオラとアンサンブルのための版が1986)、ヴィオラ協奏曲(1986)がある。
本当なら演奏時間35~40分かかる大作ヴィオラ協奏曲を取り上げるところだろうが、FMでバシュメトが弾いた演奏を聴いたことはあるものの、ディスクがない。ヴィオラをアルトサクソフォンに置き換えた版はBISに録音があるのだが。終楽章は延々と15分ほど続くシューベルトの主題による変奏曲。この部分はたぶんチェロとピアノのための《シューベルトの主題による変奏曲》に転用されている。ディスクもないし、いささか冗長という気もするので、却下。
《バッハのコラール「もう十分です」の主題による変奏曲》はアルバン・ベルクのヴァイオリン協奏曲に引用されている有名な旋律による変奏曲だが、ベルクへのオマージュ作品という感が強く、それなら、デニーソフ色がもっとよく出ている《パウル・クレーの3つの絵》がいいのではと思った次第。
正確にはヴィオラ、オーボエ、ホルン、ピアノ、ヴィブラフォン、コントラバスのための《パウル・クレーの3つの絵》であるが、明らかにヴィオラがソロだし、ヴィオリストのイゴール・ボグスラフスキイのために書かれている。
各楽章はパウル・クレーの絵画の題名が付けられている。
第1楽章:秋風のディアナ

ヴィブラフォンの硬質な響きの中をヴィオラとコントラバス、そしてピアノが少しずつずれながら崩壊していくような半音階的な走句を奏で出すと、いかにもデニーソフ的な音響空間が拓かれる。そして半音階をたっぷりとまずしたヴィオラの旋律。ここでは以上の4楽器のみの合奏。9分ほど。
第2楽章:セネシオ

ヴィオラ・ソロ曲。重音を多用した多声的独奏曲。重音トレモロ、重音の一人二声合奏、左手のピツィカート、5分ほどのカデンツァである。
第3楽章:階段の上の子供

アンサンブルには管楽器が加わり、ぐっと厚みを増す。トリルで装飾された走句で各楽器が走り回る。約9分。
さて、困ったことに録音は2種あるもいずれも廃盤。だいたい、1996年に亡くなってからというもの、デニーソフの録音は少ない。聴きやすい類の現代音楽だと思うのだけれど。
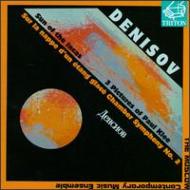

上記はモスクワ現代音楽アンサンブル版。ヴィオリストの名前も明記されていない怪しい盤。上述のように廃盤だが、金に糸目を付けぬなら、Amazonマーケットプレイスで購入するという手もある。
もうひとつは初演者ボグスラフスキイのヴィオラ、ボリショイ劇場ソリスト・アンサンブル盤。こちらも中古が手にはいるかも。
新録を待ちたいといいたいところだが、管楽器のためのソナタなどが折々に録音されるだけで、デニーソフ作品集を出そうというレコード会社がいまや乏しいので、期待薄かもと悲観的になってしまう今日この頃。
発明王に因んで命名された子が作曲家になるとは両親も予想できなかったに違いない。
デニーソフはソヴィエト・ロシアで西側の前衛的な語法を身につけた作曲家として1960年代初めから西欧で知られていた。1970年代後半になって、シュニトケやグバイドゥーリナが紹介されるまで、西側に知られたほとんど唯一のソヴィエトの前衛作曲家だった。ピエール・ブーレーズの《マルトー・サン・メートル》に影響を受けた1964年の《インカの太陽》が出世作。この頃は旋律線に微分音が豊富に仕掛けられていたが、1980年代頃から、半音階だけで似たような効果を醸しだし、かなりロマンティックな表情もみせるようになった。しかし彼はフランス音楽から影響を受けた作曲家で、硬質で色彩的なオーケストレーションはロシア人離れしている。
ヴィオラ音楽は1980年代に集中して書かれており、《パウル・クレーの3つの絵》のほかにも、ヴィオラとチェンバロと弦楽のための《室内音楽》(1982)、2つのヴィオラとチェンバロと弦楽のための協奏曲(1984)、ヴィオラとピアノのための《バッハのコラール「もう十分です」の主題による変奏曲》(1984、ヴィオラとアンサンブルのための版が1986)、ヴィオラ協奏曲(1986)がある。
本当なら演奏時間35~40分かかる大作ヴィオラ協奏曲を取り上げるところだろうが、FMでバシュメトが弾いた演奏を聴いたことはあるものの、ディスクがない。ヴィオラをアルトサクソフォンに置き換えた版はBISに録音があるのだが。終楽章は延々と15分ほど続くシューベルトの主題による変奏曲。この部分はたぶんチェロとピアノのための《シューベルトの主題による変奏曲》に転用されている。ディスクもないし、いささか冗長という気もするので、却下。
《バッハのコラール「もう十分です」の主題による変奏曲》はアルバン・ベルクのヴァイオリン協奏曲に引用されている有名な旋律による変奏曲だが、ベルクへのオマージュ作品という感が強く、それなら、デニーソフ色がもっとよく出ている《パウル・クレーの3つの絵》がいいのではと思った次第。
正確にはヴィオラ、オーボエ、ホルン、ピアノ、ヴィブラフォン、コントラバスのための《パウル・クレーの3つの絵》であるが、明らかにヴィオラがソロだし、ヴィオリストのイゴール・ボグスラフスキイのために書かれている。
各楽章はパウル・クレーの絵画の題名が付けられている。
第1楽章:秋風のディアナ

ヴィブラフォンの硬質な響きの中をヴィオラとコントラバス、そしてピアノが少しずつずれながら崩壊していくような半音階的な走句を奏で出すと、いかにもデニーソフ的な音響空間が拓かれる。そして半音階をたっぷりとまずしたヴィオラの旋律。ここでは以上の4楽器のみの合奏。9分ほど。
第2楽章:セネシオ

ヴィオラ・ソロ曲。重音を多用した多声的独奏曲。重音トレモロ、重音の一人二声合奏、左手のピツィカート、5分ほどのカデンツァである。
第3楽章:階段の上の子供

アンサンブルには管楽器が加わり、ぐっと厚みを増す。トリルで装飾された走句で各楽器が走り回る。約9分。
さて、困ったことに録音は2種あるもいずれも廃盤。だいたい、1996年に亡くなってからというもの、デニーソフの録音は少ない。聴きやすい類の現代音楽だと思うのだけれど。
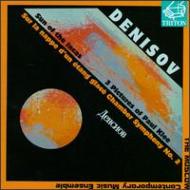
上記はモスクワ現代音楽アンサンブル版。ヴィオリストの名前も明記されていない怪しい盤。上述のように廃盤だが、金に糸目を付けぬなら、Amazonマーケットプレイスで購入するという手もある。
もうひとつは初演者ボグスラフスキイのヴィオラ、ボリショイ劇場ソリスト・アンサンブル盤。こちらも中古が手にはいるかも。
新録を待ちたいといいたいところだが、管楽器のためのソナタなどが折々に録音されるだけで、デニーソフ作品集を出そうというレコード会社がいまや乏しいので、期待薄かもと悲観的になってしまう今日この頃。