(49) ヘンク・バディンフス(1907-1987):ヴィオラ協奏曲(1965)
オランダの作曲家、ヘンク・バディンフスはオランダ人の両親のもと、当時はオランダ領だったジャワに生まれたが、幼い頃に孤児となり、オランダに戻って里親のもとで育つ。工科大学に入って地質学を学び、1931年に優秀な成績で卒業し、しばらく地史学者・古生物学者の助手として働いた。その一方で作曲家になりたい思いは断ちがたく、音楽は独習した。アムステルダム音楽院で教えていたベラルーシの著名なヴァイオリニストのアドヴァイスを受けるが、きちんと給料がもらえる職業を選ぶようにいわれる。作曲界の大御所ヴィレム・ペイペルに個人的に教えを請うが、最初の時ペイペルはバディンフスがすでにあらゆる作曲の知識を持っていることを知る。
1935年からは、オランダ各地の音楽院で教職に就く。ナチスの影響下にあった1942年、ハーグの音楽院の学長職に、前任のユダヤ人教授を追い落とすように就いたことから、オランダではナチ協力者として戦後もひどく評判が悪かったらしい。ただし、この件について本人は、そのような時代に学長の席を空席にしてはいけないので一時的なこととして責任を果たしたのだと説明しているという。今日になるまでバディンフスの音楽があまり演奏されてこなかったのはオランダ国内のそうした状況もあるようだ。
バディンフスはミヨー、オネゲル、ヒンデミット、バルトークに影響を受けているという。六音音階、八音音階(長二度と短二度の交代)を用い、別種の調性を試みた。6つのオペラ、15曲の交響曲、24曲の独奏協奏曲などを作曲し、電子音楽にも取り組んだ。
ヴィオラ協奏曲は1965年作なので比較的後期の曲である。成立の由来等はCD解説にも書かれておらず、よくわからない。
独奏と弦楽合奏のためにスコアリングされている。急緩急の3楽章、約20分。
第1楽章はクアジ・レントの序奏で弦楽の不気味なトレモロをヴィオラのモノローグが縫っていく。突如アレグロの主部にはいると、ヒンデミットもかくやという激しいソロ、最後はグリッサンドで降下して、静かなパートにはいるが、メリスマを伴ったヴィオラ・ソロにグリッサンドの弦楽合奏、怪しくも緊張感の漂う音響空間が開かれる。そして再び怒濤のアレグロ。
第2楽章アダージョは沈潜した雰囲気がオネゲルを思わせる。ちょっとエキゾチックな雰囲気を醸すターンのある旋律。やがてソロも重音を駆使して音楽の密度は高まっていく。
第3楽章アレグロ・モルトは三拍子の舞曲調、ひたすら弾き続けるヴィオラ。弦楽器がいかにパーカッシヴになれるかといった音楽である。
演奏はヴァン・ビーク指揮オーヴェルニュ管弦楽団。ソロはこのオケのソロ・ヴァイオリン奏者にして、ロンドン響のコンマス(最近のLSO Liveのメンバー表には載っていないので退団したか)、ゴルダン・ニコリッチ。彼はユリア・フィッシャーのモーツァルト協奏交響曲でもヴィオラを弾いている。
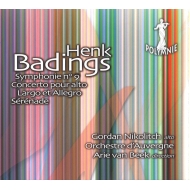

HMV ONLINE
オランダの作曲家、ヘンク・バディンフスはオランダ人の両親のもと、当時はオランダ領だったジャワに生まれたが、幼い頃に孤児となり、オランダに戻って里親のもとで育つ。工科大学に入って地質学を学び、1931年に優秀な成績で卒業し、しばらく地史学者・古生物学者の助手として働いた。その一方で作曲家になりたい思いは断ちがたく、音楽は独習した。アムステルダム音楽院で教えていたベラルーシの著名なヴァイオリニストのアドヴァイスを受けるが、きちんと給料がもらえる職業を選ぶようにいわれる。作曲界の大御所ヴィレム・ペイペルに個人的に教えを請うが、最初の時ペイペルはバディンフスがすでにあらゆる作曲の知識を持っていることを知る。
1935年からは、オランダ各地の音楽院で教職に就く。ナチスの影響下にあった1942年、ハーグの音楽院の学長職に、前任のユダヤ人教授を追い落とすように就いたことから、オランダではナチ協力者として戦後もひどく評判が悪かったらしい。ただし、この件について本人は、そのような時代に学長の席を空席にしてはいけないので一時的なこととして責任を果たしたのだと説明しているという。今日になるまでバディンフスの音楽があまり演奏されてこなかったのはオランダ国内のそうした状況もあるようだ。
バディンフスはミヨー、オネゲル、ヒンデミット、バルトークに影響を受けているという。六音音階、八音音階(長二度と短二度の交代)を用い、別種の調性を試みた。6つのオペラ、15曲の交響曲、24曲の独奏協奏曲などを作曲し、電子音楽にも取り組んだ。
ヴィオラ協奏曲は1965年作なので比較的後期の曲である。成立の由来等はCD解説にも書かれておらず、よくわからない。
独奏と弦楽合奏のためにスコアリングされている。急緩急の3楽章、約20分。
第1楽章はクアジ・レントの序奏で弦楽の不気味なトレモロをヴィオラのモノローグが縫っていく。突如アレグロの主部にはいると、ヒンデミットもかくやという激しいソロ、最後はグリッサンドで降下して、静かなパートにはいるが、メリスマを伴ったヴィオラ・ソロにグリッサンドの弦楽合奏、怪しくも緊張感の漂う音響空間が開かれる。そして再び怒濤のアレグロ。
第2楽章アダージョは沈潜した雰囲気がオネゲルを思わせる。ちょっとエキゾチックな雰囲気を醸すターンのある旋律。やがてソロも重音を駆使して音楽の密度は高まっていく。
第3楽章アレグロ・モルトは三拍子の舞曲調、ひたすら弾き続けるヴィオラ。弦楽器がいかにパーカッシヴになれるかといった音楽である。
演奏はヴァン・ビーク指揮オーヴェルニュ管弦楽団。ソロはこのオケのソロ・ヴァイオリン奏者にして、ロンドン響のコンマス(最近のLSO Liveのメンバー表には載っていないので退団したか)、ゴルダン・ニコリッチ。彼はユリア・フィッシャーのモーツァルト協奏交響曲でもヴィオラを弾いている。
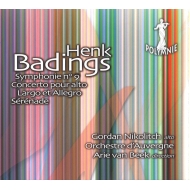
HMV ONLINE