(27) アルチュール・オネゲル(1892-1955):ヴィオラ・ソナタ(1920)
オネゲルといえば、やはり「パシフィック231」が有名か。あとは5つの交響曲。
室内楽はあまり知られていないが、Timpaniレーベルに4枚組の室内楽曲全集があって、意外なようだが、弦楽器関係では、弦楽四重奏3曲、ヴァイオリン・ソナタ3曲、ヴィオラ・ソナタ、チェロ・ソナタ、2つのヴァイオリンとピアノのソナティネ、ヴァイオリンとチェロのソナティネ、無伴奏ヴァイオリン・ソナタなどがある。が、多くは若書き。ヴァイオリン・ソナタを仕上げて、1920年にヴィオラ・ソナタ、チェロ・ソナタ、2つのヴァイオリンとピアノのソナティネが書かれている。そのあと数年内に「ダヴィデ王」や「パシフィック231」が書かれて一躍名を轟かすのだ。交響曲を書き出すのは1940年代になってからである。
ヴィオラ・ソナタはモーリス・ヴィユーのために書かれた。どういう経緯でヴィオラのソナタなどに手を染めたのか、わたしの見た限りでは明記されているものはなかった。
三楽章制で15分ほどの作品である。第1楽章はアンダンテとヴィヴァーチェの交代。冒頭の跳躍の多いピアノからして、無調的で、時代の空気を写している感じだが、あまりオネゲルらしくないのが第一印象。しかし、聴き込んでいくと、沈んだ面持ちの中の真摯な祈りのようなものが感じられてきて、第3交響曲「典礼風」の第1楽章が連想されてきた。第2楽章アレグレット・モデラートは苦悩を噛み締めつつ慰めを求める歌になる。しかし、中間部で突如ピアノに春のような明るい旋律が登場し、ヴィオラと対位法を奏でていく。ここのぱっとした輝きは非常に印象的だ。そしてまた苦みを含んだ歌になる。終楽章アレグロ・ノン・トロッポは前向きな音楽だが、悲しみを乗り越えて進んでいこうとするような決然とした表情がある。
ちょっと取っつきは悪いが、聴き込むと毅然とした美しさのある曲である。
いわゆるフランス6人組に数えられるオネゲルだが、実はスイス人。ジュネーヴ生まれだから、フランス語圏スイスの出ではあるが、その作風は典型的なフランス風とは一線を画す。演奏上では、単純化するならフランス風とドイツ風の間で様々な表現があり得る。
前述のオネゲル室内楽全集ではクセルブXeurebのヴィオラで収録されている。これはフランス的な粋がある演奏だと思う。
Chamber Music (Box)/Honegger
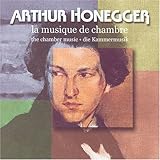
Amazon.co.jp
旧東ドイツのマンフレート・シューマン(なんて立派な名前だろう)の演奏は、オネゲルのベートーヴェン的な真摯さを捉えた演奏。私はこちらの方が好き。ただし、それは好みの問題で優劣ではない。
このほかに私が持っているのはオネゲル生誕100年にリリースされたPragaのシュペリーナ盤のみである。ニュー・ヨーク・ヴィオラ協会のディスコグラフィーを見ると、11種の録音があるが、古い録音が多い。最近は流行らない曲なのだろうか。
Music for Viola & Piano/Shostakovich
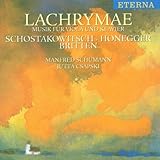
Amazon.co.jp
オネゲルといえば、やはり「パシフィック231」が有名か。あとは5つの交響曲。
室内楽はあまり知られていないが、Timpaniレーベルに4枚組の室内楽曲全集があって、意外なようだが、弦楽器関係では、弦楽四重奏3曲、ヴァイオリン・ソナタ3曲、ヴィオラ・ソナタ、チェロ・ソナタ、2つのヴァイオリンとピアノのソナティネ、ヴァイオリンとチェロのソナティネ、無伴奏ヴァイオリン・ソナタなどがある。が、多くは若書き。ヴァイオリン・ソナタを仕上げて、1920年にヴィオラ・ソナタ、チェロ・ソナタ、2つのヴァイオリンとピアノのソナティネが書かれている。そのあと数年内に「ダヴィデ王」や「パシフィック231」が書かれて一躍名を轟かすのだ。交響曲を書き出すのは1940年代になってからである。
ヴィオラ・ソナタはモーリス・ヴィユーのために書かれた。どういう経緯でヴィオラのソナタなどに手を染めたのか、わたしの見た限りでは明記されているものはなかった。
三楽章制で15分ほどの作品である。第1楽章はアンダンテとヴィヴァーチェの交代。冒頭の跳躍の多いピアノからして、無調的で、時代の空気を写している感じだが、あまりオネゲルらしくないのが第一印象。しかし、聴き込んでいくと、沈んだ面持ちの中の真摯な祈りのようなものが感じられてきて、第3交響曲「典礼風」の第1楽章が連想されてきた。第2楽章アレグレット・モデラートは苦悩を噛み締めつつ慰めを求める歌になる。しかし、中間部で突如ピアノに春のような明るい旋律が登場し、ヴィオラと対位法を奏でていく。ここのぱっとした輝きは非常に印象的だ。そしてまた苦みを含んだ歌になる。終楽章アレグロ・ノン・トロッポは前向きな音楽だが、悲しみを乗り越えて進んでいこうとするような決然とした表情がある。
ちょっと取っつきは悪いが、聴き込むと毅然とした美しさのある曲である。
いわゆるフランス6人組に数えられるオネゲルだが、実はスイス人。ジュネーヴ生まれだから、フランス語圏スイスの出ではあるが、その作風は典型的なフランス風とは一線を画す。演奏上では、単純化するならフランス風とドイツ風の間で様々な表現があり得る。
前述のオネゲル室内楽全集ではクセルブXeurebのヴィオラで収録されている。これはフランス的な粋がある演奏だと思う。
Chamber Music (Box)/Honegger
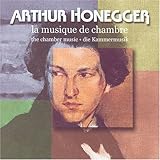
Amazon.co.jp
旧東ドイツのマンフレート・シューマン(なんて立派な名前だろう)の演奏は、オネゲルのベートーヴェン的な真摯さを捉えた演奏。私はこちらの方が好き。ただし、それは好みの問題で優劣ではない。
このほかに私が持っているのはオネゲル生誕100年にリリースされたPragaのシュペリーナ盤のみである。ニュー・ヨーク・ヴィオラ協会のディスコグラフィーを見ると、11種の録音があるが、古い録音が多い。最近は流行らない曲なのだろうか。
Music for Viola & Piano/Shostakovich
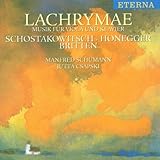
Amazon.co.jp