(25) ミハイル・コロンタイ(1952-):ヴィオラ協奏曲(1980)
ピアノの和音が鳴らされると、即ヴィオラのソロ。エレキギターで弾いたらロックになりそうな旋律。若干の楽器がからみつつ、技巧的なカデンツァになっていく。主題は弦楽に受け継がれ、金管や打楽器がはいってくると、いかにもソヴィエト音楽という響きになる。しかしまたピアノの打撃でヴィオラが戻り、オーケストラの楽器が室内楽的にからむなか、ヴィオラがこれでもかというくらいのたうち回る。
コロンタイとはまた奇妙な名前で得体が知れなかったが、とにかくバシュメトが弾くヴィオラ協奏曲ということで、手に入れた。これは大当たり。シュニトケ的に様々な要素が投入された坩堝のような曲。第1楽章アンダンテ・コン・モートはそんな調子で15分以上、目眩くヴィオラの技巧と多様な曲想と、抒情と攻撃性と、詰め込むだけ詰め込んだような音楽。後半、サックスがヴィオラにからみ出すとジャズのようになるあたりも、臆面がないというか、灰汁が強いことといったら。これもバシュメトのための協奏曲のひとつ。バシュメト以外のプレイヤーは考えられないようなヴィオラの大暴れである。
コロンタイというのはペン・ネームのようなもので、本名はミハイル・イェルモラーエフというらしい。ロシア人らしくない名字だと思ったが、Kollontaiで検索すると、マルキシズムの画家アレクサンドラ・コロンタイという人物が出てくる。
コロンタイの曲、他には無伴奏ヴァイオリン・ソナタとか合唱曲、ピアノ曲のCDがあるようだが、私はヴィオラ協奏曲しか知らない。
第2楽章アレグロはスケルツォ的楽章。ちょっと日本人の作曲家のような節回しがあるのが面白い。約8分突っ走り続けると、第3楽章アレグロはトランペットの弱奏で奇妙に始まり、むしろ中間楽章のような抒情的・歌謡的な音楽が、終結に向かって輝かしく盛り上がっていく。なかなかオリジナリティのある楽章構成ではないか。第3楽章は約12分、全体で35分ほどになるなかなかの大曲である。
バシュメトのヴィオラ、フェドセーエフ指揮モスクワ放送チャイコフスキイ響。モスクワ放送チャイコフスキイ響のアニヴァーサリー・ディスクである。ヴィオラ好きには是非聴いて頂きたい曲だが、Amazonではもう廃盤扱い。HMVではカタログに生きている。
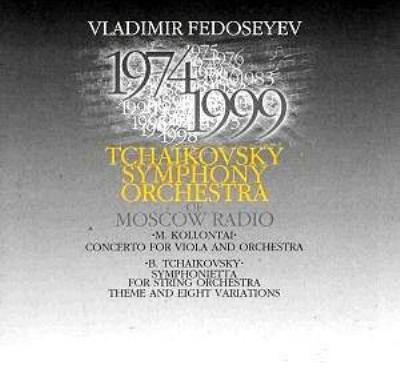
HMV ONLINE

Kollontai: Viola Concerto/Boris Tchaikovsky
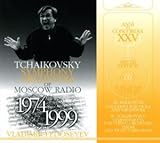
Amazon.co.jp
ピアノの和音が鳴らされると、即ヴィオラのソロ。エレキギターで弾いたらロックになりそうな旋律。若干の楽器がからみつつ、技巧的なカデンツァになっていく。主題は弦楽に受け継がれ、金管や打楽器がはいってくると、いかにもソヴィエト音楽という響きになる。しかしまたピアノの打撃でヴィオラが戻り、オーケストラの楽器が室内楽的にからむなか、ヴィオラがこれでもかというくらいのたうち回る。
コロンタイとはまた奇妙な名前で得体が知れなかったが、とにかくバシュメトが弾くヴィオラ協奏曲ということで、手に入れた。これは大当たり。シュニトケ的に様々な要素が投入された坩堝のような曲。第1楽章アンダンテ・コン・モートはそんな調子で15分以上、目眩くヴィオラの技巧と多様な曲想と、抒情と攻撃性と、詰め込むだけ詰め込んだような音楽。後半、サックスがヴィオラにからみ出すとジャズのようになるあたりも、臆面がないというか、灰汁が強いことといったら。これもバシュメトのための協奏曲のひとつ。バシュメト以外のプレイヤーは考えられないようなヴィオラの大暴れである。
コロンタイというのはペン・ネームのようなもので、本名はミハイル・イェルモラーエフというらしい。ロシア人らしくない名字だと思ったが、Kollontaiで検索すると、マルキシズムの画家アレクサンドラ・コロンタイという人物が出てくる。
コロンタイの曲、他には無伴奏ヴァイオリン・ソナタとか合唱曲、ピアノ曲のCDがあるようだが、私はヴィオラ協奏曲しか知らない。
第2楽章アレグロはスケルツォ的楽章。ちょっと日本人の作曲家のような節回しがあるのが面白い。約8分突っ走り続けると、第3楽章アレグロはトランペットの弱奏で奇妙に始まり、むしろ中間楽章のような抒情的・歌謡的な音楽が、終結に向かって輝かしく盛り上がっていく。なかなかオリジナリティのある楽章構成ではないか。第3楽章は約12分、全体で35分ほどになるなかなかの大曲である。
バシュメトのヴィオラ、フェドセーエフ指揮モスクワ放送チャイコフスキイ響。モスクワ放送チャイコフスキイ響のアニヴァーサリー・ディスクである。ヴィオラ好きには是非聴いて頂きたい曲だが、Amazonではもう廃盤扱い。HMVではカタログに生きている。
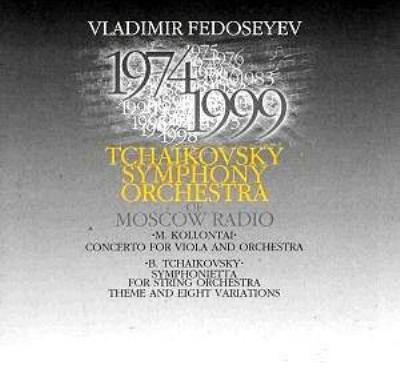
HMV ONLINE
Kollontai: Viola Concerto/Boris Tchaikovsky
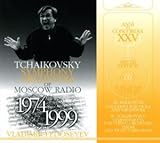
Amazon.co.jp