(18) サイモン・ベインブリッジ(1952-):ヴィオラ協奏曲(1976)
サイモン・ベインブリッジが何者かもわからぬまま、ヴィオラ協奏曲だというだけで買ってきたディスク。一聴するなり「当たり」という感触があった。そういつも当たりではないのが、辛いところだが、この曲はそうした希有な1例だったので、印象深い。私の感触を裏付けるように、Continuumというレーベルから出ていて入手困難となっていた、このディスクもNMCで再発された。
ベインブリッジはオリヴァー・ナッセンと同年生まれのイギリスの作曲家。つまり1952年。この年生まれには印象的な作曲家が多いと思っていた。ヴォルフガンク・リーム、アドリアナ・ヘルツキー、フィリップ・マヌリ、カイヤ・サーリアホ、アラ・パヴロヴァ……
イェール四重奏団がベインブリッジの弦楽四重奏曲を1972年に演奏した時、その四重奏団のヴィオラ奏者だったヴァルター・トランプラーが協奏曲を書くことを頼んだのだという。トランプラーといえば往年のファンならご存じのように、ブダペスト四重奏団の定評高いモーツァルト弦楽五重奏曲全集にヴィオラ奏者として参加している人。ヴィオラのレパートリー拡大にも熱心で、ルチアーノ・ベリオのヴィオラのためのセクエンツァ(第6番)は彼のために書かれている。
ベインブリッジのヴィオラ協奏曲の楽章は2つ。ヴィオラのダブル・ストップが導入となって、オーケストラを導き出す。オーケストラがキラキラと瞬く様はブーレーズなどフランスの現代音楽とどこそこ似ているが、ヴィオラは線的に流れ、旋律的な要素も登場してくる。ちょっと雅楽を思わせる、高い保続音の上でグリッサンドが出てきたりする神秘的な音楽で第1楽章は終わる。第2楽章は茫洋とした音響で始まるが、やはり雅楽を参照しているらしい。もっとも日本人である私にはあまりそうには聞こえないのだが。やがて、ヴィオラの無調的な歌が登場すると、オーケストラの繊細な伴奏が繰り広げられる。種々の打楽器の音色優位の使用、舞台裏のヴィオラ、ギター(?)のトレモロ。確かにこの繊細さには東洋的な印象を感じなくもない。約28分。
演奏は委嘱者トランプラーのヴィオラ、ティルスン・トーマス指揮ロンドン・シンフォニエッタ。
Simon Bainbridge: Fantasia for Double Orchestra; Viola Concerto; Concertante in Moto Perpetuo
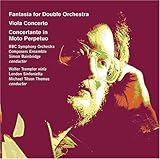
Amazon.co.jp
サイモン・ベインブリッジが何者かもわからぬまま、ヴィオラ協奏曲だというだけで買ってきたディスク。一聴するなり「当たり」という感触があった。そういつも当たりではないのが、辛いところだが、この曲はそうした希有な1例だったので、印象深い。私の感触を裏付けるように、Continuumというレーベルから出ていて入手困難となっていた、このディスクもNMCで再発された。
ベインブリッジはオリヴァー・ナッセンと同年生まれのイギリスの作曲家。つまり1952年。この年生まれには印象的な作曲家が多いと思っていた。ヴォルフガンク・リーム、アドリアナ・ヘルツキー、フィリップ・マヌリ、カイヤ・サーリアホ、アラ・パヴロヴァ……
イェール四重奏団がベインブリッジの弦楽四重奏曲を1972年に演奏した時、その四重奏団のヴィオラ奏者だったヴァルター・トランプラーが協奏曲を書くことを頼んだのだという。トランプラーといえば往年のファンならご存じのように、ブダペスト四重奏団の定評高いモーツァルト弦楽五重奏曲全集にヴィオラ奏者として参加している人。ヴィオラのレパートリー拡大にも熱心で、ルチアーノ・ベリオのヴィオラのためのセクエンツァ(第6番)は彼のために書かれている。
ベインブリッジのヴィオラ協奏曲の楽章は2つ。ヴィオラのダブル・ストップが導入となって、オーケストラを導き出す。オーケストラがキラキラと瞬く様はブーレーズなどフランスの現代音楽とどこそこ似ているが、ヴィオラは線的に流れ、旋律的な要素も登場してくる。ちょっと雅楽を思わせる、高い保続音の上でグリッサンドが出てきたりする神秘的な音楽で第1楽章は終わる。第2楽章は茫洋とした音響で始まるが、やはり雅楽を参照しているらしい。もっとも日本人である私にはあまりそうには聞こえないのだが。やがて、ヴィオラの無調的な歌が登場すると、オーケストラの繊細な伴奏が繰り広げられる。種々の打楽器の音色優位の使用、舞台裏のヴィオラ、ギター(?)のトレモロ。確かにこの繊細さには東洋的な印象を感じなくもない。約28分。
演奏は委嘱者トランプラーのヴィオラ、ティルスン・トーマス指揮ロンドン・シンフォニエッタ。
Simon Bainbridge: Fantasia for Double Orchestra; Viola Concerto; Concertante in Moto Perpetuo
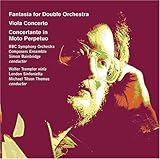
Amazon.co.jp