(57) ジョン・ハービスン(1938-):ヴィオラ協奏曲(1988)
アメリカ国内では大作曲家と遇されていても、ヨーロッパではあまり演奏されない、といった類の作曲家が少なからずいるようで、ハービスンもそれにはいるらしい。セッションズの弟子だが、ドデカフォニストではない。
すでに作曲家になる決心をしていたハービスンにとって、ヴィオラは常に物事の中庸にいて、作曲家にとってはまったく有利な位置だと思い、ヴィオラを自分の楽器と思い定めた。ところが、もっと手が大きくなったらと言い聞かされて、ヴァイオリンで我慢することとなった。しかし結局のところ手は大きくならず、学生時代にとにもかくにもヴィオラに転向した。その夏は非公式の弦楽四重奏団のヴィオリストとして、ハイドンを弾き、ハービスンにとってそれはもっとも幸福な夏だったという。しかし、よいヴィオリストにはなれず、むしろチューバのほうが上達し、ジャズ・ピアニストとしてのほうがお金を稼げた。
全4楽章、約30分。第1楽章の冒頭で茫洋とした和音が鳴らされるが、このつかみ所のなさがハービスンの体質という気がする。彼の交響曲(ブロムシュテット指揮やレヴァイン指揮のディスクがある)もそうした音響の印象が強い。
第1楽章は絶えず変転し、調的にも常にずれていくような、反復のない音楽なのに対して、フィドル風の第2楽章は反復と組み合わせで仕組まれている。そして第3楽章は拍節的に単純なのに対して、終楽章は込み入った拍節変化に溢れているといった対比が図られている。演奏時間は22~23分。
聴感上、ヴィオラの音の扱いは高音に偏り、音の質も軽めの感じで、私にはそこがいささかもの足りない。
ディスクは2種。ピッツバーグ交響楽団主席のランドルフ・ケリーのもの(ウォルター・ピストンとサミュエル・アドラーのヴィオラ協奏曲とのカップリング)とヴァイオリニストでヴィオラも弾くジェイミー・ラレードのもの(エズラ・レイダーマンの管弦楽曲とのカップリング)がある。ヴィオラらしい音色では家リー盤を推すが、ラレードの切れ味も捨てがたいものがある。
Works by John Harbison and Ezra Laderman

Amazon.co.jp
Piston, Harbison, Adler: Viola Concertos
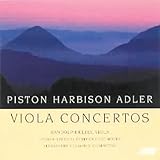
Amazon.co.jp
アメリカ国内では大作曲家と遇されていても、ヨーロッパではあまり演奏されない、といった類の作曲家が少なからずいるようで、ハービスンもそれにはいるらしい。セッションズの弟子だが、ドデカフォニストではない。
すでに作曲家になる決心をしていたハービスンにとって、ヴィオラは常に物事の中庸にいて、作曲家にとってはまったく有利な位置だと思い、ヴィオラを自分の楽器と思い定めた。ところが、もっと手が大きくなったらと言い聞かされて、ヴァイオリンで我慢することとなった。しかし結局のところ手は大きくならず、学生時代にとにもかくにもヴィオラに転向した。その夏は非公式の弦楽四重奏団のヴィオリストとして、ハイドンを弾き、ハービスンにとってそれはもっとも幸福な夏だったという。しかし、よいヴィオリストにはなれず、むしろチューバのほうが上達し、ジャズ・ピアニストとしてのほうがお金を稼げた。
全4楽章、約30分。第1楽章の冒頭で茫洋とした和音が鳴らされるが、このつかみ所のなさがハービスンの体質という気がする。彼の交響曲(ブロムシュテット指揮やレヴァイン指揮のディスクがある)もそうした音響の印象が強い。
第1楽章は絶えず変転し、調的にも常にずれていくような、反復のない音楽なのに対して、フィドル風の第2楽章は反復と組み合わせで仕組まれている。そして第3楽章は拍節的に単純なのに対して、終楽章は込み入った拍節変化に溢れているといった対比が図られている。演奏時間は22~23分。
聴感上、ヴィオラの音の扱いは高音に偏り、音の質も軽めの感じで、私にはそこがいささかもの足りない。
ディスクは2種。ピッツバーグ交響楽団主席のランドルフ・ケリーのもの(ウォルター・ピストンとサミュエル・アドラーのヴィオラ協奏曲とのカップリング)とヴァイオリニストでヴィオラも弾くジェイミー・ラレードのもの(エズラ・レイダーマンの管弦楽曲とのカップリング)がある。ヴィオラらしい音色では家リー盤を推すが、ラレードの切れ味も捨てがたいものがある。
Works by John Harbison and Ezra Laderman

Amazon.co.jp
Piston, Harbison, Adler: Viola Concertos
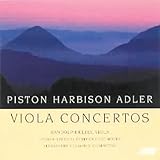
Amazon.co.jp