(21) ボフスラフ・マルティヌー(1890-1959):ラプソディ-コンチェルト (1952)
─ヴィオラと管弦楽のための
演奏する曲に困ったら、彼の作品表を見てご覧、という作曲家の一人がマルティヌー。多作家でいろんな楽器のために作曲した。とはいえ協奏曲は弦楽器とピアノのものが多く、バロックの合奏協奏曲に倣った複数楽器のための協奏曲も多い。ヴィオラのための協奏曲はこのラプソディ-コンチェルトだけ。ヴィオラのレパートリーではヴィオラ・ソナタが1曲ある。
マルティヌーはボヘミアに生まれ、プラハ音楽院でヴァイオリンとオルガンと作曲を学んだ。そこではヨセフ・スークのマスター・クラスにも参加したが、パリに移り、アルベール・ルーセルの教えを受けた。パリで次第に演奏家たちの関心を集め、クーセヴィツキー、ミュンシュ、アンセルメ、ザッハーといった指揮者の支持を得る。その後、シェーンベルクやストラヴィンスキイ、さらにはジャズの影響を受け、作風は先鋭化していく。ところが、1941年、チェコの亡命政府との関係がナチスの標的となり、アメリカ合衆国に渡る。このアメリカ時代に6曲の交響曲が書かれる。
クラシックを聴き始めて、交響曲にはまり、次々にいろんな作曲家の交響曲を聞きあさったが、マルティヌーの交響曲は苦かった。ルーセルとシェーンベルクとストラヴィンスキイの苦いところばかり取り出して混ぜ合わせ、そのうえ渋みまで付けたような。彼にとっても辛い時代だったのだろう。今はそう思って聴くと、これはなかなか味わいのある交響曲なのだが。
1952年には合衆国の市民権を得るが、翌年にはヨーロッパに戻り、余生をニースと、バーゼル近郊のプラッテルンというところで過ごした。
ラプソディ-コンチェルトはアメリカ時代の最後、1952年に書かれた。交響曲に辟易とした人もご安心あれ、これは晩年の自由闊達なスタイルで書かれた、なかなか民族色もある親しみやすい曲なのだ。敢えて訳せば狂詩的協奏曲だが、語感もよくないのでラプソディ-コンチェルトにしておこう。
楽章は2つだけ。モデラートとモルト・アダージョ。最初こそマルティヌーらしい、ゴチャゴチャした和音で始まるが、ヴィオラ独奏はドヴォルジャークに出てきそうな民謡調の旋律を朗々と歌う。すぐに早い部分になり、ラプソディ的な性格を顕わにする。あれこれ走り回ったあと、最初の民謡調が回帰。牧歌的世界にはいって、第1楽章は終了。第2楽章は晦渋なテーマで始まる。ヴィオラ独奏も無調と民謡の間を彷徨うような微妙な旋律を描いていく。テンポが上がって少し明るくなっていく。ショスタコーヴィチのようなギャロップ。そしてまた「新世界交響曲」みたいなメロディ。これがまた何とも郷愁を誘う。短いカデンツァがはいると、舞曲調の早い部分になる。ジャズとはいわんまでもかなりモダンな調子になる。現代的なカデンツァの経過のあと、また、郷愁たっぷりな民謡調。曲は静かに終わる。約20分。
リヴカ・ゴラーニのヴィオラ、ペーター・マーク指揮というのを最初に聴いたと思うが、Conifer盤なので、今はもう手にはいらないだろう。今井信子盤は現役だけれどもソロが引っ込んだ録音がいまひとつ。スーク盤は孫のほうのヨセフ・スークがヴァイオリン協奏曲2曲とラプソディー-コンチェルトのソロを持ち替えて弾いている。オケはノイマン/チェコ・フィルというお国もの。やはり民謡への共感があるのだろうなという演奏。ファースト・チョイスはこれかも。
しかし、お勧めは新しい録音。タベア・ツィンマーマン(ヴィオラ)ジェイムズ・コンロン指揮ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団。これはこの曲の民族風なところと、先に「苦い」と表現した要素の残渣がまるでモザイクのように融け合わされず提示されていて、私には頗る面白かった。
Bohuslav Martinu: Rhapsody for Viola; Concerto; Concertino; Lidice [Hybrid SACD]
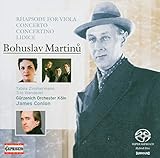
Amazon.co.jp
─ヴィオラと管弦楽のための
演奏する曲に困ったら、彼の作品表を見てご覧、という作曲家の一人がマルティヌー。多作家でいろんな楽器のために作曲した。とはいえ協奏曲は弦楽器とピアノのものが多く、バロックの合奏協奏曲に倣った複数楽器のための協奏曲も多い。ヴィオラのための協奏曲はこのラプソディ-コンチェルトだけ。ヴィオラのレパートリーではヴィオラ・ソナタが1曲ある。
マルティヌーはボヘミアに生まれ、プラハ音楽院でヴァイオリンとオルガンと作曲を学んだ。そこではヨセフ・スークのマスター・クラスにも参加したが、パリに移り、アルベール・ルーセルの教えを受けた。パリで次第に演奏家たちの関心を集め、クーセヴィツキー、ミュンシュ、アンセルメ、ザッハーといった指揮者の支持を得る。その後、シェーンベルクやストラヴィンスキイ、さらにはジャズの影響を受け、作風は先鋭化していく。ところが、1941年、チェコの亡命政府との関係がナチスの標的となり、アメリカ合衆国に渡る。このアメリカ時代に6曲の交響曲が書かれる。
クラシックを聴き始めて、交響曲にはまり、次々にいろんな作曲家の交響曲を聞きあさったが、マルティヌーの交響曲は苦かった。ルーセルとシェーンベルクとストラヴィンスキイの苦いところばかり取り出して混ぜ合わせ、そのうえ渋みまで付けたような。彼にとっても辛い時代だったのだろう。今はそう思って聴くと、これはなかなか味わいのある交響曲なのだが。
1952年には合衆国の市民権を得るが、翌年にはヨーロッパに戻り、余生をニースと、バーゼル近郊のプラッテルンというところで過ごした。
ラプソディ-コンチェルトはアメリカ時代の最後、1952年に書かれた。交響曲に辟易とした人もご安心あれ、これは晩年の自由闊達なスタイルで書かれた、なかなか民族色もある親しみやすい曲なのだ。敢えて訳せば狂詩的協奏曲だが、語感もよくないのでラプソディ-コンチェルトにしておこう。
楽章は2つだけ。モデラートとモルト・アダージョ。最初こそマルティヌーらしい、ゴチャゴチャした和音で始まるが、ヴィオラ独奏はドヴォルジャークに出てきそうな民謡調の旋律を朗々と歌う。すぐに早い部分になり、ラプソディ的な性格を顕わにする。あれこれ走り回ったあと、最初の民謡調が回帰。牧歌的世界にはいって、第1楽章は終了。第2楽章は晦渋なテーマで始まる。ヴィオラ独奏も無調と民謡の間を彷徨うような微妙な旋律を描いていく。テンポが上がって少し明るくなっていく。ショスタコーヴィチのようなギャロップ。そしてまた「新世界交響曲」みたいなメロディ。これがまた何とも郷愁を誘う。短いカデンツァがはいると、舞曲調の早い部分になる。ジャズとはいわんまでもかなりモダンな調子になる。現代的なカデンツァの経過のあと、また、郷愁たっぷりな民謡調。曲は静かに終わる。約20分。
リヴカ・ゴラーニのヴィオラ、ペーター・マーク指揮というのを最初に聴いたと思うが、Conifer盤なので、今はもう手にはいらないだろう。今井信子盤は現役だけれどもソロが引っ込んだ録音がいまひとつ。スーク盤は孫のほうのヨセフ・スークがヴァイオリン協奏曲2曲とラプソディー-コンチェルトのソロを持ち替えて弾いている。オケはノイマン/チェコ・フィルというお国もの。やはり民謡への共感があるのだろうなという演奏。ファースト・チョイスはこれかも。
しかし、お勧めは新しい録音。タベア・ツィンマーマン(ヴィオラ)ジェイムズ・コンロン指揮ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団。これはこの曲の民族風なところと、先に「苦い」と表現した要素の残渣がまるでモザイクのように融け合わされず提示されていて、私には頗る面白かった。
Bohuslav Martinu: Rhapsody for Viola; Concerto; Concertino; Lidice [Hybrid SACD]
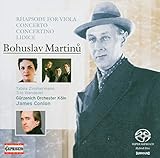
Amazon.co.jp