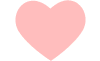NHKが今回の名古屋場所の生中継放送見送りを決定しましたね
。
NHKに寄せられた多くの意見の7割近くが放送反対だったそうですから、当然でしょう。
古くから天皇の御前で相撲をとる「相撲節会(すまいのせちえ)」が行われていたのは
七夕と同じ七月七日でした。
垂仁天皇の前で 奈良の當麻蹶速(たいまのけはや)Vs 出雲の野見宿禰(のみのすくね)が捔力(すもう)をとったのが 垂仁天7年7月7日(旧暦)だったから。
その縁の深い七月七日の前日に放送中止が決定したのは皮肉な話です。
モンゴル・ロシア・ブルガリアなど世界中から相撲取りになろうと人が集まっているなか、日本人力士だけが賭博に手を出していたという恥かしい不祥事。
野球のルールがわからないからというのも一つだそうですけれど、インタビューを聞いていると 他人に流されない『自分』というものをきちんと持っているから手を出さなかったように思われました。
相撲協会のこれからの方針の中に「暴力団とのつながりの排除方法」がちゃんと明示されていない今の段階では わたしたちの受信料で大相撲中継を放送されるのはいかがなものかと思ってしまいますよね。
相撲は日本の国技である!と胸を張って言えるように相撲協会全体の意識改革をどうかお願いします。
■風俗博物館 六条院四季の移ろい 文月(七月)
七夕は節句の一つでその風習は他の節句(桃の節供・端午の節句など)同様中国から伝わったものです。
中国から伝わったお祭りの名前は『乞巧奠(きこうてん・きこうでん・きっこうてん・きっこうでん)』
巧くなりますようにと乞い願いお供え(お香典の正字 香奠と同じ)をすること、おまつりすること。 っていう意味だそうです。
正倉院御物にもお裁縫の上達を願ったのか 糸を通したまま残された儀式用の大きな針が伝わっています。
お菜箸ほどもある長い針3本と短い針4本 合わせて七本で1セット
名前を「七孔針」というそうです。
一本に7子穴が開いているわけじゃないんですね。
今も京都に残る公家の末裔「冷泉家」では 「星の座」という乞巧奠用の特別なお供えの並べ方が伝わっているそうです。そう平成の今も伝統のお祭りをしているんですね。すごいわー。
先月まで開かれていた京都文化博物館で開催された
「冷泉家 王朝の和歌守(うたもり)展」では本物が見られたそうです。惜しかった><
■朝日新聞社 展覧会紹介(2) 乞巧奠(きっこうてん)の祭壇「星の座」 より
吉備大臣入唐絵巻のお話の元になった「江談抄」の語り手「大江匡房」が書いた平安時代の有職故実の書「江家次第」によると
乞巧奠 … 「宮中の清涼殿の東庭に長筵(ながむしろ)を敷き、
その上に朱塗りの高机四脚をすえ、
桃・梨・茄子・熟瓜・大豆・大角豆・干鯛・薄蚫(あわび)などのほか
楸(ひさぎ)(赤芽柏)の葉に金・銀の針各七本を刺して供える。
これには五色の糸を通してある。
また琴一張を机の上に置き、傍らに香炉を置いて
終始そらだきを絶やさぬようにする。
机の周囲やその間に九本の灯台を置いて明かしを灯す。
天皇は庭に椅子を出されて二星の会合のさまをご覧になり、
管弦や和歌・詩文などを楽しまれる。」
朱塗りではありませんが高机の前に長筵が敷かれていてお琴も備えられているのがわかります。
五色の糸を通した針は楸(ひさぎ)の葉に刺しておくと書いてありますね。
木偏に秋と書いて楸。 前回の椿に続いて季節を表す木なのでしょうね。
旧暦だと 1.2.3月が春
4.5.6月が夏
7.8.9月が秋
10.11.12月が冬でした。
秋に入って最初のお祭りに 秋の字の入った楸の葉に針を刺すのはとても象徴的に思えてなりません。
キササゲ もアカメガシワ もどちらもが「楸」であるようです。
どっちでしょうねえ?
そうそう乞巧奠で短冊ではなくて「梶」という木の葉っぱ七枚に歌を書いたそうです。
上の乞巧奠の写真の左上 布の幕にくっついている葉っぱが梶の葉です。
梶の木 は製紙に使われたりしたそうです。だから歌も書くのかしら?
神聖な木として神木になっていたりlこの葉にお供え物を載せたり、梶の木の皮から取った白い繊維で織った布は「御幣(ごへい)」として神にささげられました。(白和弊-しらにきて・しらにぎて)
諏訪大社の御神紋はこの梶の葉です。
またこの木の繊維で織った布を白栲(しろたえ)と言ったそうです。
春過ぎて 夏きにけらし 白たへの 衣干すてふ 天香具山
という持統天皇の御歌の白妙の衣は梶の木から出来ていたのかも!
麻や楮や梶の木から取れるあらい繊維で織った素朴な布を『倭文(しず)』といい、文献には残っていても実 物が残っていない幻の布、それが白栲だったなんてなんだか古代のロマンを感じてしまいます。
■津山瓦版> 岡山県北観光情報 >気になるスポットをチェック>倭文(しとり)地区 >倭文織(しづおり)
★上の地区名「倭文」と書いて「シトリ」 織物の他に 「紙工」と書いて「シトリ」とも読むこともあるらしいので 倭文の布と紙は密接な関係がありそうです。
吉野紙の名産地奈良県の吉野で義経と別れた静御前が
鎌倉の頼朝の前で義経をしのんで舞いながら歌った歌
しづやしづしづのおだまきくりかへし むかしを今になすよしもがな
緒環(おだまき)は麻の繊維(お)をつないだ糸をまとめた物のこと。
「静や 静よ と私を繰り返し呼んだ義経様のいらっしゃった昔みたいには戻れないの」という意味と
倭文織りの しづがかかっている 糸や織物に関係している女が詠んだ巧みな歌だと思うんですよ。
悲しいけど。
やっぱり静御前は当時一流の芸能人だったんだわ・・・
紙作りと倭文織りにも関係していそう。
■ちょっと歴史 その壱 賎の小田巻(しずのおだまき)
ここにもっと詳しい解説がりました。静御前がいかに教養人だったか、また流人上がりの頼朝もそれがわかるだけの教養人であり この歌の裏にウチが読み取った以上の深い意味が込められていたというのがわかります。
紙作りと倭文織りが関係していそうっていうのは短絡的だったのかな。
京都の秋の時代祭 女人行列の中に『梶(かじ) 』という名前の人が居ます。江戸時代の人です。
時代祭では丸に梶の葉の紋付を着ています。
彼女は祇園で茶屋を営んでいた人ですが独学で歌をよく詠んだので 星の座を今に伝える和歌守りの冷泉家の中興の祖 冷泉為村にその歌才を愛でられたそうです。
彼女が民間女性で初めて出した歌集の名前は『梶の葉 』でした。冷泉家の人に愛でられる優れた歌詠みの歌集にふさわしい名前ですよね。
手に持っているのが笹に見える・・・気になる!
祖父から教えてもらったおまじないに
「七夕の短冊は里芋の葉っぱにたまった朝露を集めてすった墨で書く。」
すると書道が上達するんだそうです。
里芋が生えてる畑がそばに無いから集めに行ったことは一度もありませんけれど。
縫い物・織物・書道・琴などの芸事・・・あなたは星に何をお願いしますか?
旧暦の七夕までまだ時間はありますよ^^
天の川見れるといいな
*
2013/06/20追記
祇園の茶汲女「お梶」の紋になってる「梶の葉」を水差しのフタに使うお茶のお手前があるそうで、2010/7/9「七夕考」に動画を載せました。また梶の葉を乗せた水差しの写真もありますのでよろしかったらお読みください。