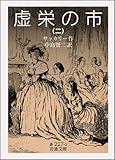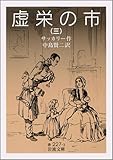いやあ、久しぶりに長い話を読み終えて、これはこれで満足感があるものですなあ。
ウィリアム・サッカレーの「虚栄の市」、岩波文庫一冊あたり400ページ余で全4巻。
かなり日にちがかかってしまいましたけれど。
そも何ゆえにこの長尺ものに手を出してしまったかと言いますれば、
先に「インドカレー伝」を読んだことで、サッカレーとは「カレー」つながり…てな理由であるはずもなく、
カレーが食文化として根付いていく当時の英国のようすがよく示されているようなふうに
紹介されていたからでありまして。
かねて「虚栄の市」とのタイトルからは「ソドムとゴモラ」的頽廃の都の話でもあろうかと想像し、
およそ手に取ることもあるまいと踏んでいたですが、どうやらそういう話ではなさそうなので、
これも何かの縁とばかりに挑んだわけでありますよ。
で、「虚栄の市」(Vanity fair)とはジョン・バニアンの小説「天路歴程」で
良きキリスト者となっていくために通過する苦難などをもたらす場所のひとつとされているそうな。
サッカレーは、18世紀前半の英国、主としてロンドンを舞台に、
目先の煌びやかさ(金やら地位やら名誉やら)に踊らされて生きている人たちが集う場所として
「虚栄の市」という言葉を当てはめたのですな。
先にカレーが食文化として根付いていく頃と言いましたですが、
どうやらインド植民地バブルといった感じに受け止められる社会情勢のようでして、
東インド会社に絡む人たちは妙に羽振りがいいお大尽でもあるかのよう。
実際にサッカレー自身、インド生まれで父親も祖父も東インド会社に係わっており、
あれこれ苦労はあったものの、かなりの放蕩息子ぶりを発揮していた時期も伝わるようで。
そうした自らの経験も含めて、虚栄の市に集って踊る人々の姿を活写していったのでありましょう。
本書によって一躍サッカレーはディケンズとも並ぶ小説家として知られるようになったそうですが、
ディケンズのように社会の最底辺にある人たちを描くのでなく、もそっと中流から上に目を向けた分、
読み手にとってはたくさんの登場人物のうち、こんな人もあんな人もいる、いると感じさせて、
そうした人たちを揶揄するものとして「ああ、スカッとした!」的な受け止め方も
多くされたのではなかろうかと。
「たくさんの登場人物」と言いましたですが、タイトルには「主人公のいない小説」と添えられています。
物語の始まりこそ、レベッカとアミーリアが女学校を卒業して世に出て行くところからになりますけれど、
いずれも全編通しての主人公ではなく、彼女たちが相互に、また離れ離れになりつつ、
それぞれが係わる人々(恋人やその家族、一族郎党、従僕たちに至るまで)のことが
縦横無尽に書き綴られていくという。
まとまりを欠いているとも言えるかもしれませんが、虚栄の市がそもそもかなりの雑踏であって、
いろいろな立場の人たちが交錯する場所であることからすれば、こういう描き方であることは
むしろ前向きに受け止めても良いのかもしれません。
それでも、敢えていうなれば最初から登場するレベッカという女性。
出自にあやふやなところがあり、女学校もお情けでいさせてもらたようなふうなだけに、
(その時代であればやむなきことかもですが)周囲を一切合財踏み台にして
上流・名流を目指していく姿はよくも悪くも強い印象を残すもので、
「ベッキー(レベッカ)を主人公としたピカレスク・ロマンと見ることも可能であろう」との
巻末解説の一文はむべなるかなでありますね。
ま、それ以外の登場人物たちもいろいろな意味で(例えば人が好すぎるてなことも含めて)
「こいつはどうよ」的な人たちばかりで、そこには誇張が多く含まれているにせよ、
当時の英国ばかりでなく、今のご時世であっても「いる、いる」てな感じもするとなれば、
小説の出来不出来にあれこれ意見があるとしても、もそっと読まれてもいい小説かもしれんなあと、
そんなふうに思った「虚栄の市」でありました。