ふたたびジョージ・オーウェルに戻ります。
オーウェル評論集 (1982年) (岩波文庫)/岩波書店

¥525
Amazon.co.jp
“だがここで、前にふれた点にもどってみたい――すなわち世間一般にユダヤ人差別があることは誰もが認めるくせに、自分もその一人だということは認めたがらないという事実である。
教養のある人びとは、ユダヤ人差別は許すべからざる罪であり、ほかの人種差別とは別格のものだと考えている。自分がユダヤ人を差別していないことを証明するためなら、誰もが長口舌をふるう。
というわけで、1943年には、ポーランドのユダヤ人のために神の救いを祈る礼拝式が、セント・ジョンズ・ウッドのシナゴーグで催されたのだった。
ロンドン市当局はぜひ出席したいという意向を明らかにして、当日は官服に鎖をさげたロンドン市長、各地区の教会代表、英国空軍、国防市民軍、看護婦、ボーイスカウトなどの代表が出席した。
表面だけ見れば、これh不幸なユダヤ人との連帯をしめす感動的な催しであった。だが本質的には、これは正しいことをしようという意識的な努力だったのであって、出席者それぞれの本音は、まずほとんどが別物だったである。
この地区はロンドン市内でもなかばユダヤ人地区であって、ユダヤ人差別の強い所である。シナゴーグでわたしのまわりにいた人びとの中にもその傾向のある人があきらかにまじっていた。
それどころか、国防市民軍でわたしの小隊長だった人物など、集会の前から「りっぱに成功させなければ」ととくに熱心だったけれども、この人物は以前はオズワルド・モズリーの黒シャツ隊の一員だったのである。”

オズワルド・モズレーはイングランド下級貴族出身の人物。1932年に英国ファシスト連合(British Union of Fascists)を結成し、英国でファシズム政権樹立を目指します。そのファシスト連合の暴力部門がNational Defence Force、通称「黒シャツ隊(Blackshirts)」ということになります。
この英国ファシスト連合の在英ユダヤ人への対応は、「我々はユダヤ人差別をしたいのではない。ただ、反英のユダヤ人に出ていけと言いたいだけだ」・・・どっかの誰かさんたちと同じです。

ここでリンクしたのは1998年放映のテレビドラマ『MOSLEY』から。
1936年10月4日の日曜日。その黒シャツ隊を率いてモズレーは、ユダヤ人街を中心に多くの移民が住むイーストエンドで数千人規模のデモ行進をしようという計画を立てました。
これに対し、ロンドンの数万人以上の市民に左翼やアイルランド人も加わり、「やつらを通すな!(They shall not pass!)」を合言葉に集結しカウンターをかけます。ここでも「¡No pasarán!」です。
このデモ行進を警備しようとする警官隊とカウンターが衝突。これを「ケーブル・ストリートの戦い(Battle of Cable Street)」と呼び、それ以上の混乱を恐れる当局の意を汲んでモズレーと黒シャツ隊はデモ行進を中止。
そして、モズレーは言うのです。「ユダヤに金で雇われたギャングが我々を襲撃しようとしたから」・・・これもどっかの誰かさんたちが同じこと言ってますね。
ところがそれだけの猛威をふるった英国ファシスト連合はこのケーブル・ストリートの戦い以降、急激に規模を縮小していきます。そして、英国がドイツと開戦するとなれば、この英国ファシスト連合の主要メンバーは、モズレーを筆頭に、今度は彼らが売国奴やスパイの疑いをかけられ、戦争が連合国の勝利で終わるまで逮捕拘禁されることになるのです。
ただ、逮捕されなかった下級のメンバーはドイツとの戦争になれば、コロッと立場を変え、ドイツと戦うユダヤ人に連帯を示そうと今度はこのオールドカマーのユダヤ人の多く住むウエストエンドのシナゴーグに集まっていた、それがオーウェルの見た光景です。
ちなみに、オーウェルの『1984年』をはじめとして、『V for Vendetta』など英国がファシストによって支配されている、という設定のディストピア作品のイメージ・ヴィジュアルとして、このモズレーと英国ファシスト連合が使われることが多いです。知らなかったという人でもどっかで見たような記憶はないですか?この党章を。
“ドイツでのユダヤ人迫害は、むしろユダヤ人差別の問題が真剣に検討されなくなるという弊害を生んだ。
英国では一、二年前に世論調査機関が短期間の不充分な調査をおこなっているが、ほかにもこの問題に関する調査はおこなわれていると考えられるのに、その結果は極秘のままで公表されていない。
また思慮ある人びとも、ユダヤ人がうさんくさいようなことは意識して言わないようにしている。1934年以後は、絵葉書からも、新聞雑誌からも、ミュージック・ホールからも、「ユダヤ人を種にしたジョーク」はまるで魔法のように消えてしまったし、小説などにかんばしからぬユダヤ人を登場させるのも、ユダヤ人差別だと見なされるにいたった。パレスチナ問題のときにも、進歩的文化人のあいだでは、ユダヤ人の主張が当然だとして、アラブ側の主張にはいっさい耳を貸さないことが当然の礼儀だった。
この態度は、それなりに理由のある正しいものだったのかもしれない。だが問題はその態度の根本が、ユダヤ人は苦しんでいるのだから彼らを批判してはならないという感情だった点にある。
つまりヒットラーのおかげで、ジャーナリズムはいっさいユダヤ人を批判しないという事実上の自己規制に入り、反面個人の心にひそむユダヤ人差別は上向きとなって、感受性も知性もある人びとのあいだにさえかなりひろまるという、不幸な状況に陥ったのである。”

1934年8月、ヒトラーはドイツ総統の座に就きます。
敵国ドイツがユダヤ人を迫害するのならば、英国は「かわいそうなユダヤ人」を守ってあげなくてはならない。「かわいそうなユダヤ人」を守ってあげれば、我々の戦争にも協力してくれるだろうから批判するのは止めておこうという“自己規制”ですね。差別そのものを問題視して止めておくのではなく、あくまでも戦時中の利害から止めた、そうオーウェルには見えていたのでしょう。
こうして、1945年の段階でパレスチナ問題に言及しているところに彼の先見の明を感じますが。
で、戦争を理由に無理に押し隠した差別感情は心のなかでかえって反動を引き起こすわけです。
“この現象は、1940年に亡命者たちが拘留されたときにとくに目についた。
当然のこととして、心ある人びとはすべて、不幸な外国人を見境なく留置したりすることには抗議しなければならないと思ったのだ。こうした外国人の大部分は、ヒットラーに反対だから英国へ来たにすぎない人びとなのである。
だが個人的な話になると、その感想はまるで違っていた。亡命者のなかには少数ながらきわめて無分別なまねをするものもいて反感を買ったのだが、この反感の底には、彼らの多くがユダヤ人だというので、やはりユダヤ人差別の意識がひそんでいたのだった。
労働党のある大立者――名前はあげないが、英国ではもっとも尊敬されている人物の一人である――が、わたしに向ってきわめて乱暴に言ったことがある。
「あの連中にはこっちから頼んで来てもらったわけじゃないんだからね。英国へ来たいんなら、その責任は自分でとってもらおうじゃないか」。
当然ながら全てのユダヤ人が「かわいそうなユダヤ人」ではないでしょう。人間ですから上品な者もいれば下品な者もいる。ナチスから必死の思いで逃げてきて、なりふり構う余裕のない人も少なくなかったでしょう。けれども「ユダヤ人」とくくってしまうとそれはすぐに差別へと結びついてしまいます。どうしたって、少数であったとしても下品なほうが悪目立ちするものですから。
ただ、なかなか分けて考えられないのも人間なんですよね。
“こういうユダヤ人差別というのは罪悪であり恥辱であって文明人ならそんなことは考えないという気持、それがこの問題を理性的に処理する上での障害になるのである。
それどころか、この問題をふかく追求するのがこわいという人さえいくらでもいるのだ。
つまり世間にユダヤ人差別があるというだけではすまず、自分も同じ意識をもっていることを認識するのがこわいのである。”
Ultimate/Pet Shop Boys
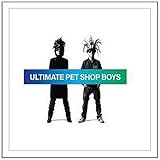
¥1,451
Amazon.co.jp
リンクしてあるのは、Pet Shop Boysの「West End Girls」。
オーウェル評論集 (1982年) (岩波文庫)/岩波書店

¥525
Amazon.co.jp
“だがここで、前にふれた点にもどってみたい――すなわち世間一般にユダヤ人差別があることは誰もが認めるくせに、自分もその一人だということは認めたがらないという事実である。
教養のある人びとは、ユダヤ人差別は許すべからざる罪であり、ほかの人種差別とは別格のものだと考えている。自分がユダヤ人を差別していないことを証明するためなら、誰もが長口舌をふるう。
というわけで、1943年には、ポーランドのユダヤ人のために神の救いを祈る礼拝式が、セント・ジョンズ・ウッドのシナゴーグで催されたのだった。
ロンドン市当局はぜひ出席したいという意向を明らかにして、当日は官服に鎖をさげたロンドン市長、各地区の教会代表、英国空軍、国防市民軍、看護婦、ボーイスカウトなどの代表が出席した。
表面だけ見れば、これh不幸なユダヤ人との連帯をしめす感動的な催しであった。だが本質的には、これは正しいことをしようという意識的な努力だったのであって、出席者それぞれの本音は、まずほとんどが別物だったである。
この地区はロンドン市内でもなかばユダヤ人地区であって、ユダヤ人差別の強い所である。シナゴーグでわたしのまわりにいた人びとの中にもその傾向のある人があきらかにまじっていた。
それどころか、国防市民軍でわたしの小隊長だった人物など、集会の前から「りっぱに成功させなければ」ととくに熱心だったけれども、この人物は以前はオズワルド・モズリーの黒シャツ隊の一員だったのである。”

オズワルド・モズレーはイングランド下級貴族出身の人物。1932年に英国ファシスト連合(British Union of Fascists)を結成し、英国でファシズム政権樹立を目指します。そのファシスト連合の暴力部門がNational Defence Force、通称「黒シャツ隊(Blackshirts)」ということになります。
この英国ファシスト連合の在英ユダヤ人への対応は、「我々はユダヤ人差別をしたいのではない。ただ、反英のユダヤ人に出ていけと言いたいだけだ」・・・どっかの誰かさんたちと同じです。

ここでリンクしたのは1998年放映のテレビドラマ『MOSLEY』から。
1936年10月4日の日曜日。その黒シャツ隊を率いてモズレーは、ユダヤ人街を中心に多くの移民が住むイーストエンドで数千人規模のデモ行進をしようという計画を立てました。
これに対し、ロンドンの数万人以上の市民に左翼やアイルランド人も加わり、「やつらを通すな!(They shall not pass!)」を合言葉に集結しカウンターをかけます。ここでも「¡No pasarán!」です。
このデモ行進を警備しようとする警官隊とカウンターが衝突。これを「ケーブル・ストリートの戦い(Battle of Cable Street)」と呼び、それ以上の混乱を恐れる当局の意を汲んでモズレーと黒シャツ隊はデモ行進を中止。
そして、モズレーは言うのです。「ユダヤに金で雇われたギャングが我々を襲撃しようとしたから」・・・これもどっかの誰かさんたちが同じこと言ってますね。
ところがそれだけの猛威をふるった英国ファシスト連合はこのケーブル・ストリートの戦い以降、急激に規模を縮小していきます。そして、英国がドイツと開戦するとなれば、この英国ファシスト連合の主要メンバーは、モズレーを筆頭に、今度は彼らが売国奴やスパイの疑いをかけられ、戦争が連合国の勝利で終わるまで逮捕拘禁されることになるのです。
ただ、逮捕されなかった下級のメンバーはドイツとの戦争になれば、コロッと立場を変え、ドイツと戦うユダヤ人に連帯を示そうと今度はこのオールドカマーのユダヤ人の多く住むウエストエンドのシナゴーグに集まっていた、それがオーウェルの見た光景です。
ちなみに、オーウェルの『1984年』をはじめとして、『V for Vendetta』など英国がファシストによって支配されている、という設定のディストピア作品のイメージ・ヴィジュアルとして、このモズレーと英国ファシスト連合が使われることが多いです。知らなかったという人でもどっかで見たような記憶はないですか?この党章を。
“ドイツでのユダヤ人迫害は、むしろユダヤ人差別の問題が真剣に検討されなくなるという弊害を生んだ。
英国では一、二年前に世論調査機関が短期間の不充分な調査をおこなっているが、ほかにもこの問題に関する調査はおこなわれていると考えられるのに、その結果は極秘のままで公表されていない。
また思慮ある人びとも、ユダヤ人がうさんくさいようなことは意識して言わないようにしている。1934年以後は、絵葉書からも、新聞雑誌からも、ミュージック・ホールからも、「ユダヤ人を種にしたジョーク」はまるで魔法のように消えてしまったし、小説などにかんばしからぬユダヤ人を登場させるのも、ユダヤ人差別だと見なされるにいたった。パレスチナ問題のときにも、進歩的文化人のあいだでは、ユダヤ人の主張が当然だとして、アラブ側の主張にはいっさい耳を貸さないことが当然の礼儀だった。
この態度は、それなりに理由のある正しいものだったのかもしれない。だが問題はその態度の根本が、ユダヤ人は苦しんでいるのだから彼らを批判してはならないという感情だった点にある。
つまりヒットラーのおかげで、ジャーナリズムはいっさいユダヤ人を批判しないという事実上の自己規制に入り、反面個人の心にひそむユダヤ人差別は上向きとなって、感受性も知性もある人びとのあいだにさえかなりひろまるという、不幸な状況に陥ったのである。”

1934年8月、ヒトラーはドイツ総統の座に就きます。
敵国ドイツがユダヤ人を迫害するのならば、英国は「かわいそうなユダヤ人」を守ってあげなくてはならない。「かわいそうなユダヤ人」を守ってあげれば、我々の戦争にも協力してくれるだろうから批判するのは止めておこうという“自己規制”ですね。差別そのものを問題視して止めておくのではなく、あくまでも戦時中の利害から止めた、そうオーウェルには見えていたのでしょう。
こうして、1945年の段階でパレスチナ問題に言及しているところに彼の先見の明を感じますが。
で、戦争を理由に無理に押し隠した差別感情は心のなかでかえって反動を引き起こすわけです。
“この現象は、1940年に亡命者たちが拘留されたときにとくに目についた。
当然のこととして、心ある人びとはすべて、不幸な外国人を見境なく留置したりすることには抗議しなければならないと思ったのだ。こうした外国人の大部分は、ヒットラーに反対だから英国へ来たにすぎない人びとなのである。
だが個人的な話になると、その感想はまるで違っていた。亡命者のなかには少数ながらきわめて無分別なまねをするものもいて反感を買ったのだが、この反感の底には、彼らの多くがユダヤ人だというので、やはりユダヤ人差別の意識がひそんでいたのだった。
労働党のある大立者――名前はあげないが、英国ではもっとも尊敬されている人物の一人である――が、わたしに向ってきわめて乱暴に言ったことがある。
「あの連中にはこっちから頼んで来てもらったわけじゃないんだからね。英国へ来たいんなら、その責任は自分でとってもらおうじゃないか」。
当然ながら全てのユダヤ人が「かわいそうなユダヤ人」ではないでしょう。人間ですから上品な者もいれば下品な者もいる。ナチスから必死の思いで逃げてきて、なりふり構う余裕のない人も少なくなかったでしょう。けれども「ユダヤ人」とくくってしまうとそれはすぐに差別へと結びついてしまいます。どうしたって、少数であったとしても下品なほうが悪目立ちするものですから。
ただ、なかなか分けて考えられないのも人間なんですよね。
“こういうユダヤ人差別というのは罪悪であり恥辱であって文明人ならそんなことは考えないという気持、それがこの問題を理性的に処理する上での障害になるのである。
それどころか、この問題をふかく追求するのがこわいという人さえいくらでもいるのだ。
つまり世間にユダヤ人差別があるというだけではすまず、自分も同じ意識をもっていることを認識するのがこわいのである。”
Ultimate/Pet Shop Boys
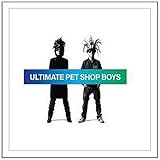
¥1,451
Amazon.co.jp
リンクしてあるのは、Pet Shop Boysの「West End Girls」。