こんなテーマ・タイトルにしてみましたが、これはメイブンでもミョウブンでもナワケでも好きに読んでください。
ここでは名前とか翻訳とか色々と、普段は気に留めずに使っている言葉が、つい気になってしまった時に使うテーマにしようかと考えています。
普通の日本語の使い方とは異なるかもしれませんが“名前を分類する”とでも思ってみてもらえれば。
Legendary Weapons/Wu-Tang
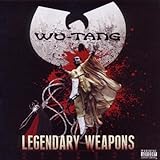
¥1,466
Amazon.co.jp
私自身は、ネットで買い物をするよりも店で直接に買う方が好き、というよりも何を買うかも決めずに本屋での立ち読みやレコード店の試聴コーナーで新しい情報に出会える方が面白いと思っています。
ネットだとどうしても趣味の幅が狭まってしまうように思えるのですよね。
で、このアルバムはウータン・クランという米国東海岸のヒップホップ・グループの新譜です。
ずいぶんと久しぶりに聞きましたが、相変わらずカンフーをテーマに音楽をやっているのだと、ある意味感心。
このグループ・・・据わりが悪いな・・・バンドにしよう・・・このバンドの名前なんですが、どこから採られたものか分かりますか?
漢字で書くと“武当派”って意味なんです。
武当派とは何だろうと思う方も多いでしょうが、中国拳法の流派の名前でして、すごく簡単に説明すると“太極拳”を使う流派になります。
少林寺が仏教僧たちの武術であったのに対して、武当山に集まる道教の道士たちの武術であると理解してもらえれば、けっこうです。ただちょっと単純にすぎるかもしれませんが。
もし、こうした中国武術の名前で楽しむのでしたら、武侠小説というジャンルがありまして、中国文化圏では根強い人気があり、私も以前にはすっかりハマって、翻訳されていないものまで中国系移民の店などで探してしまったほどです。
このジャンルの第一人者に金庸という作家がいますが、彼の作品ならば翻訳されて文庫でも売られているので、試しに読んでみたらいかがでしょう。40年前のライトノベルとして楽しめると思いますよ。
天龍八部一 剣仙伝説 (徳間文庫)/金庸
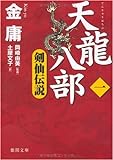
¥720
Amazon.co.jp
これなんて、現在の日本のアニメでも全然おかしくないようなキャラクターの割り振りがされています。
で、このウータン・クランのジャケットを見るとおかしな感じですよね。道士系の武術であるはずなのに、衣装は仏教風のものになっています。ニューヨークの黒人系のお兄ちゃんたちがアチョー!とか言いながら決めたので、あんまりアジア文化の区別がついていないのでしょう。もう20年くらい続いているバンドなのに・・・。
ここから、やっと本題に入ります。
ここでは武当派の“派”を“クラン(clan)”と翻訳しています。
宗教的な背景のある流派なので、正確には“セクト(sect)”と訳すべきですね。
クランとは一般的には“氏族”と日本では翻訳してきました。
このあたりは私たちがそれぞれ“親戚”という言葉で思い浮かべる人たちの顔や人数が、個人個人で異なるのと同じように簡単に一般化するには複雑過ぎます。
クランという単語を日本関係の資料を英文で読んでいる時に見かけるのは、戦国時代のものが多いのは、例えば、武田信玄の武田家を翻訳すればタケダ・クランになるからなので、バトル・オブ・ナガシノではタケダ・クランとオダ・クランが激突したという翻訳になります。

さて、この時点で既に翻訳に混乱がありますよね。武田氏と書くべきか武田家と書くべきか迷うところです。
武田氏自体は、他にも諸派がありますので、武田信玄が全タケダ氏族を率いていたわけではありません。甲斐源氏という一派ですから。
そうすると概念としては、リニエージもしくはリネージュと日本でカタカナ表記される単語があります。
伝説的に共通する先祖を同じくするクランよりももう少し範囲が狭まり、歴史的に共通の先祖を同じくした集団を呼ぶためのものです。
そうすると武田家の配下にいる甘利家や板垣家も甲斐源氏ですから据わりが良くなるように思えます。
さらに、ファミリーにしてみましょうか。“家”そのものになりますね。
大名に対しては、さらにハウスというそのものずばりの呼び方もありますが。
当然ながら、最初に書いたように個々人が親戚と聞いて思い浮かべる人数が異なるように、簡単には単語を当てはめるのは難しいのです。
ここから続ける話題は、こんな言葉を頭に入れつつ読んでいただけると、分かりやすくなると思いますが、もし混乱したら、私の文才の欠けることにあるとツッコミつつ読んでください。
ここでは名前とか翻訳とか色々と、普段は気に留めずに使っている言葉が、つい気になってしまった時に使うテーマにしようかと考えています。
普通の日本語の使い方とは異なるかもしれませんが“名前を分類する”とでも思ってみてもらえれば。
Legendary Weapons/Wu-Tang
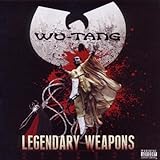
¥1,466
Amazon.co.jp
私自身は、ネットで買い物をするよりも店で直接に買う方が好き、というよりも何を買うかも決めずに本屋での立ち読みやレコード店の試聴コーナーで新しい情報に出会える方が面白いと思っています。
ネットだとどうしても趣味の幅が狭まってしまうように思えるのですよね。
で、このアルバムはウータン・クランという米国東海岸のヒップホップ・グループの新譜です。
ずいぶんと久しぶりに聞きましたが、相変わらずカンフーをテーマに音楽をやっているのだと、ある意味感心。
このグループ・・・据わりが悪いな・・・バンドにしよう・・・このバンドの名前なんですが、どこから採られたものか分かりますか?
漢字で書くと“武当派”って意味なんです。
武当派とは何だろうと思う方も多いでしょうが、中国拳法の流派の名前でして、すごく簡単に説明すると“太極拳”を使う流派になります。
少林寺が仏教僧たちの武術であったのに対して、武当山に集まる道教の道士たちの武術であると理解してもらえれば、けっこうです。ただちょっと単純にすぎるかもしれませんが。
もし、こうした中国武術の名前で楽しむのでしたら、武侠小説というジャンルがありまして、中国文化圏では根強い人気があり、私も以前にはすっかりハマって、翻訳されていないものまで中国系移民の店などで探してしまったほどです。
このジャンルの第一人者に金庸という作家がいますが、彼の作品ならば翻訳されて文庫でも売られているので、試しに読んでみたらいかがでしょう。40年前のライトノベルとして楽しめると思いますよ。
天龍八部一 剣仙伝説 (徳間文庫)/金庸
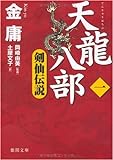
¥720
Amazon.co.jp
これなんて、現在の日本のアニメでも全然おかしくないようなキャラクターの割り振りがされています。
で、このウータン・クランのジャケットを見るとおかしな感じですよね。道士系の武術であるはずなのに、衣装は仏教風のものになっています。ニューヨークの黒人系のお兄ちゃんたちがアチョー!とか言いながら決めたので、あんまりアジア文化の区別がついていないのでしょう。もう20年くらい続いているバンドなのに・・・。
ここから、やっと本題に入ります。
ここでは武当派の“派”を“クラン(clan)”と翻訳しています。
宗教的な背景のある流派なので、正確には“セクト(sect)”と訳すべきですね。
クランとは一般的には“氏族”と日本では翻訳してきました。
このあたりは私たちがそれぞれ“親戚”という言葉で思い浮かべる人たちの顔や人数が、個人個人で異なるのと同じように簡単に一般化するには複雑過ぎます。
クランという単語を日本関係の資料を英文で読んでいる時に見かけるのは、戦国時代のものが多いのは、例えば、武田信玄の武田家を翻訳すればタケダ・クランになるからなので、バトル・オブ・ナガシノではタケダ・クランとオダ・クランが激突したという翻訳になります。

さて、この時点で既に翻訳に混乱がありますよね。武田氏と書くべきか武田家と書くべきか迷うところです。
武田氏自体は、他にも諸派がありますので、武田信玄が全タケダ氏族を率いていたわけではありません。甲斐源氏という一派ですから。
そうすると概念としては、リニエージもしくはリネージュと日本でカタカナ表記される単語があります。
伝説的に共通する先祖を同じくするクランよりももう少し範囲が狭まり、歴史的に共通の先祖を同じくした集団を呼ぶためのものです。
そうすると武田家の配下にいる甘利家や板垣家も甲斐源氏ですから据わりが良くなるように思えます。
さらに、ファミリーにしてみましょうか。“家”そのものになりますね。
大名に対しては、さらにハウスというそのものずばりの呼び方もありますが。
当然ながら、最初に書いたように個々人が親戚と聞いて思い浮かべる人数が異なるように、簡単には単語を当てはめるのは難しいのです。
ここから続ける話題は、こんな言葉を頭に入れつつ読んでいただけると、分かりやすくなると思いますが、もし混乱したら、私の文才の欠けることにあるとツッコミつつ読んでください。