今日は、図書館内の本の置き方について、書こうと思います。
書店と図書館、本の置き方が違うと思われた方、おられませんか? その悩みも一挙に解決です。
まず、
図書館の本の置き方には、決まりがあります。
適当じゃないんです!!
毎年、年度初めに児童にはレクリエーション説明するので、児童は覚えてくれているのですが、案外、先生方が覚えてくれていないです。
何年も一緒に勤めているのに、先生の中には、司書である私が覚えやすいところに、適当に置いていると、思っていた方もいらっしゃいました。
丸つけに必死過ぎです、先生!! たまには、私の話も児童と一緒に聞いてください。とは、本人に言えないので、ここでつぶやく。
公共図書館でも、学校図書館でも、そうなのですが、本の背表紙に「ラベル」が貼ってあるのは、ご存知でしょうか?
この「ラベル」、上の図は3段ラベルですが、図書館によっては、1段だったり、2段だったりします。
「作者名の頭文字」もわかる、「本の巻数」もわかる、が「分類番号」って?
日本十進分類法 第一次区分
0 総記 (百科事典とか図鑑とかもここのことがある)
1 哲学 (心理学とか宗教。占いとかもここ)
2 歴史 (歴史とか地理。伝記マンガとかもここ)
3 社会科学 (社会科関係。昔話とか戦争ものもここ)
4 自然科学 (理科とか算数とか)
5 技術 (工業とか家庭科。手芸やお料理もここ)
6 産業
7 芸術 (美術、音楽、スポーツ、室内遊び。マンガとか映画の本もここ)
8 言語
9 文学 (小学校では、文学の中でも絵本は「E」などとして別に分類しているところも多いです)
たとえば、「ONE PIECE」の1巻が、
- ONE PIECE 1 (ジャンプ・コミックス)/尾田 栄一郎
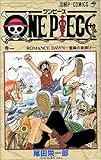
- ¥410
- Amazon.co.jp
もし我が校にあるとしたら、
72(マンガの分類番号。別の分類にするところもあります)
お(尾田栄一郎の頭文字)
1(1巻)
という風にラベルを作ります。うちに「ONE PIECE」ないけどね。
で、本にラベルが貼れましたら、
分類番号順 > 作者名のあいうえお順 > 巻数順
と本棚に並べていきます。
ですので、
「書店では出版社別に並んでいるのに、図書館では作者順?」
と思われていた方も多いと思いますが、この為なのです。図書館では探しやすさ優先、書店では発注のしやすさ優先といった並びであろうと思われます。ちなみに、書店では出版社が目録(出版リスト)を送ってこられて、それを観て在庫確認や発注作業をしたりします。(一昔前の話で、今は都心とかハイテク化してるかも?)
話は戻って、図書館内の本の並べ方ですが、
図書館の入り口から入って左手から、図書館内をぐるりと右へ向かって置きます。
本棚の中では、左上から右下へ向かって順に並べ、次の本棚へとなっています。
我が校の場合は、ざっくりと↓こんな感じです。
もちろん本棚や、よく貸し出しされる分類、などなどによって、それぞれの図書館の配置は若干変わってきます。
見学に行った、県立高校の学校図書館では、概ねこの並び方で専門分野だけ特設コーナーが設けられていました。国立大学は、数階建ての大きな図書館だったので、階数ごとに分野別になっていましたが、本棚の並び方は概ねこの通りでした。
この分類を覚えておくと、どこの公共図書館でも本を簡単に探す事ができる、小学校から中学校に行っても、すぐに探せるということで、
確か、小学校3年生の国語で、この図書館についての勉強をする為、近くの公共図書館に見学に行ったり、調べ学習したりしています。
私は、この配置を覚えてもらうレクリエーションの時に、
ひとクラスを何チームかに分て、リーダーにタイトルだけを書いた紙を渡し、
「『その紙』と、『そのタイトルの本』と、『そのタイトルの本の中に入っているしおり』を名探偵コナンのように推理して、探してくるように」
というゲームをします。
いわゆる宝探しです。
注意点は、
1 リーダーが必ず、『タイトルの紙』を綺麗に持つ事。他の者が触ってはいけない。
(紙を奪ってひとりで探す子どもの防止)
2 チーム全員で探し、チーム全員で持ってくる事。
(仲間はずれ防止)
3 このゲームでは興奮して騒ぐ人がたまにいるが、コナンのようにスマートに探し、カッコよく持ってくる事。
(騒ぐの防止)
4 探し終えたチームから、本の返却・貸し出し。
(遊んで探さないの防止)
としておくと、『タイトルの紙』と壁に貼ってある分類表、図書館の配置図を見比べて、静かに協力して本を探します。宝探しは面白いので、静かに盛り上がります。うるさいと、私が怒って、
「キミら失格~」
と紙を取り上げるので。
ちなみに、チームもリーダーも、この机の者同士とか、出席番号4の倍数とか決めます。好きな者同士にしない、リーダーはランダムとしています。
で、これを毎年、学年が上がる度にしているので、児童は本の探し方を覚えます。
が、最初に戻りますが、先生方が案外覚えてくれません。
一緒にゲームに参加してくれる先生は覚えてくれてるみたいです。
もっと図書館に興味を持ってもらいたいなぁ。
ということで、今日はこの辺りで。