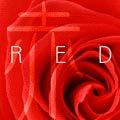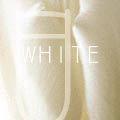色彩、脳科学、食という側面から
 美しさ
美しさ を様々な角度から追求し続けています。
を様々な角度から追求し続けています。
美 し い 女 性 と は ?
メイクやジュエリーで身を調えた方の事でしょうか?
どんなに表面をとりつくろってみても
細胞からの輝きでないと美しいとは言えません。
美しさは、毎日の食事からです。
その目的に応じた色の食物を取り入れることで、
内蔵や皮膚などあらゆる細胞が美しくなり、輝きを増します。
匂いたつような美しさは、脳が司る生体内の
ホルモンバランスや心理から創出されます。
シ リ ー ズ コ ラ ム
「踊りの中で、関係性が立ち上がるとき」
皆様こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。私は昨日のアルゼンチンタンゴのステップに酔いしれ、体幹を整えるためにストレッチやヨガに勤しんでいます。
社交ダンスももちろん大好きですが、アルゼンチンタンゴの哀愁に満ちた関係性の表現が、たまらなく好きです。
社交ダンスもパートナーのリードで踊るダンスですが、アルゼンチンタンゴは少し性質が違います。
たとえるなら
![]() 社交ダンスは、完成された振付のある映画。
社交ダンスは、完成された振付のある映画。
![]() アルゼンチンタンゴは、その場で会話をしながら進む物語。
アルゼンチンタンゴは、その場で会話をしながら進む物語。
社交ダンスでは、「次はこれをする」とある程度決まっているため、安心して大きく、のびやかに動くことができます。二人で同じ方向を見て、美しい形を作っていく感覚です。
一方でアルゼンチンタンゴは、次に何が起こるか、直前までわかりません。
一歩出るのか、止まるのか。近づくのか、少し距離を取るのか。相手の呼吸や体のわずかな動きを感じながら、その場で選んでいきます。言葉を使わない、静かな会話のようなものです。だからアルゼンチンタンゴには、どこか切なさや、哀愁が漂います。近づいたと思ったら離れ、離れたと思ったら、また引き寄せられる。
人生の人間関係に、少し似ているのかもしれません。
そんなことを考えていたら、
本日Netflixで『10DANCE』が公開されると知り、とてもワクワクしています。
『10DANCE』は、この二つのダンス「形の美しさを極めた社交ダンス」と「関係性を踊るラテン」が出会う物語。
ダンスを知らなくても、人と人がどう向き合うのか、どう距離を縮め、どう信頼を築くのか、きっと感じ取れる作品だと思います。
私自身も、社交ダンスで身体を整え、アルゼンチンタンゴで心をほどきながら、二つのダンスから多くのことを教えてもらっています。
今夜は『10DANCE』を通して、スクリーンの向こうに描かれる
二つのダンスの世界と、そこに流れる感情を、
じっくり味わいたいと思います。
皆様にとっても、
難しいことを考えずに、
ただ「心が動く」時間がありますように。
似合う色が、静かに変わっていく頃
日本の色と時間の話
皆様こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。日差しはやわらかく心地よいものの、風の強さによってはまだ冷たさを感じる日もありますね。
四季を通して、日本のさまざまな色を感じられることを、私はとても幸せなことだと感じています。春の淡さ、夏の強さ、秋の深み、冬の静けさ。日本の色は、季節とともに移ろいながら、私たちの暮らしや感覚にそっと寄り添ってきました。
先日、色彩を研究する前、正確には大学院に入学する前から「いつか手元に置きたい」と思っていた日本の色見本の本を、思いがけずいただきました。
長い間、心のどこかに残っていた憧れの一冊です。振り返ってみると、私は色を体系的に学ぶ以前から、自然と色に親しんできたように思います。
着物の色合わせや季節ごとの取り入れ方に心を惹かれ、またオーラソーマを通して、色が持つ象徴性や内面への作用にも触れてきました。理論よりも先に、感覚として色と向き合っていた時間だったのかもしれません。
幼い頃の記憶にも、色にまつわる小さな出来事があります。
七五三の着物を選ぶ際、私はどうしてもピンクがいいと母に主張しました。けれど実際に用意されたのは、オレンジ色の着物でした。当時の私はどこか不本意で、「どうしてこの色なのだろう」と思っていたことを覚えています。
それから長い年月が経ち、ふとアルバムを開いてその写真を見返したとき、思わず納得してしまいました。
そこには、無理のない表情で写る自分がいて、「なるほど、あの頃の私にはオレンジの方が似合っていたのだな」と、静かに腑に落ちたのです。
日本の伝統色の中で、いわゆるオレンジは、単に明るく元気な色というだけではありません。
橙(だいだい)、柑子色(こうじいろ)、黄丹(おうに)など、少しずつ表情を変えながら、祝いの場や人生の節目に用いられてきました。
赤の力強さと黄色のやわらかさを併せ持ち、外へと開きながらも、人を包み込む温度を感じさせる色です。
七五三という節目に選ばれたオレンジの着物は、可愛らしさよりも、健やかさや生命力、これから育っていく芯の強さを、そっと先取りしていた色だったのかもしれません。
色は、時に本人の意思よりも少し先を見て、選ばれることがあるのだと、今では思います。
その後、デザインや素材、光や空間と向き合う仕事を重ねる中で、色の捉え方も少しずつ変わっていきました。
色は「選ぶもの」から、「感じ取るもの」へ。
強さや分かりやすさよりも、にじみや揺らぎ、季節の移ろいの中で生まれる微妙な違いに、心が留まるようになりました。
更年期を迎えてからは、「似合う」と感じる色にも、はっきりとした変化を感じています。
以前は惹かれていた色が強く感じられたり、逆に、これまで選ばなかった色が、すっと身体に馴染むように感じられたりします。
それは流行や気分ではなく、身体の内側のリズムが変化していることと、深く関係しているように思います。
今、心地よいと感じるのは、はっきりとしたコントラストの色よりも、曖昧さを含んだ色合いです。
にごりを含んだ白、深みのある土の色、夕暮れに近い橙、影を含んだ緑。
それらは主張するのではなく、呼吸を整えるように、静かに寄り添ってくれます。
若い頃の「似合う」は、どれだけ映えるか、どれだけ目を引くか、だったのかもしれません。
けれど今は、「疲れない」「落ち着く」「長く付き合える」という感覚が、何より大切になりました。
色は外見を飾るものから、心と身体を調律する存在へと、役割を変えているように感じます。
今回手にした日本の色見本を開くと、そこに並ぶ色たちは、決して声高に語ることなく、静かにこちらに語りかけてきます。
それらは完成された色というよりも、時間を含んだ色。
若い頃には気づけなかった奥行きが、今は自然に目に入ってきます。
色は、目で見るものだけではなく、人生の段階ごとに受け取り方が変わるもの。
今だからこそ、この色たちと向き合える。
そう思えたこと自体が、この本が今の私のもとにやってきた理由なのかもしれません。
これからも色とともに、変化を拒まず、その時々の自分を受け入れながら、生きていきたいと思います。
身体の状態が分かる冬のセルフケア:Apple Watchとスマートリングが導く自律神経バランス
皆様こんにちは、いかがお過ごしでしょう。
冬らしい凛とした空気の中にも、まるで薄絹を通すような日差しが差し込み、季節が静かに表情を変えゆくのを感じる朝となりました。
私は家を整えながら、自身の身体と心のケアにも丁寧に向き合っています。
アルゼンチンタンゴでは身体の中心軸が一筋の光のように通り、ライドでは風と呼吸の波が静かに調和し、岩盤の温熱の中で行う筋整ヨガでは、深層に閉じ込められていた緊張が、まるで氷が溶けるようにほどけていきます。
そしてバレトンでは、全身が静かに目覚めるように動き始め、身体の巡りがひとつの優雅な循環となって響き合います。
岩盤のあたたかさに身をゆだねていると、身体を包むエネルギーのレイヤーが静かに整い始めます。
スピリチュアルの世界では、熱は“内なる聖域を開く鍵”とされ、心身の波動が澄んだ領域へと導かれるといわれています。
一方で、科学的にも深部体温の上昇は血管を開き、自律神経を整えることでメンタルの安定をもたらすことが明らかになっており、まさに目に見えない領域と見える領域が優雅に交差する時間です。
さらに最近は、Apple Watchとスマートリングが、私の“静かな観察者”となっています。
心拍変動(HRV)の揺らぎ、睡眠の深度、運動後の回復指標―どれも、身体の奥に潜むリズムを繊細に映し出してくれるもの。
スピリチュアルでは「内なる声を聞く」といいますが、現代の科学はその声を数値として優美に翻訳し、気づきを与えてくれます。
自分という小さな宇宙が、テクノロジーの光に照らされてゆっくりと開示されていくようで、そこには穏やかな神秘さが漂います。
家を整える行為もまた、ひとつの祈りのようです。
不要なものを手放すと空間のエネルギーが軽やかに澄み渡り、滞っていた“氣”が美しい循環を取り戻します。
科学的には、視覚情報が整理されることで脳の前頭前野が解放され、思考が澄み、感情が落ち着く現象として説明されますが、スピリチュアルのまなざしで見ると、それは“魂の居場所を整える”ことに他なりません。
このように暮らしの営みは、
「家 → 心 → 身体」
と静かに連なり、ひとつの美しい螺旋のように私を整えてくれます。
冬の冷たい空気の中で、ふと差し込む光が空間を金色に染める瞬間のように――
日々の中に潜む小さな神秘と、科学がもたらす確かな理解。
その両方に支えられて、今日の私はまたひとつ、豊かに整っていくのを感じました。